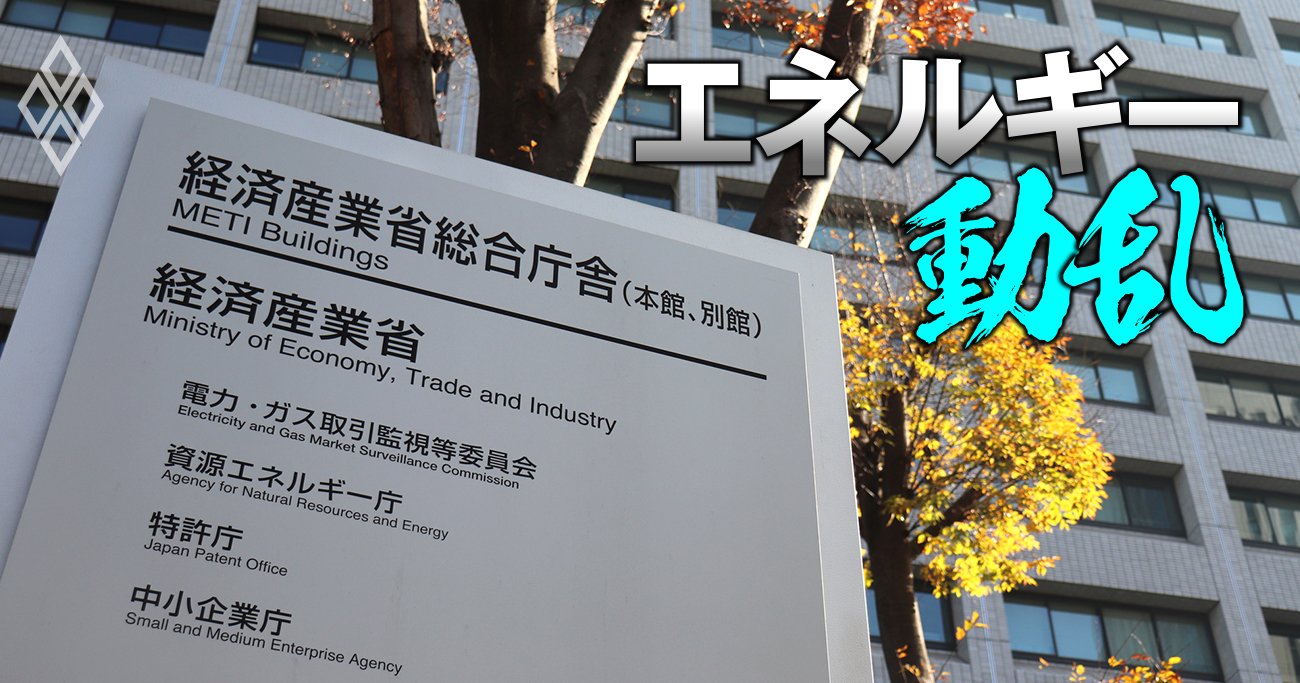 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
国のエネルギー基本計画の改定議論が本格的にスタートした。国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が求める「2035年に60%削減(19年比)」を目標とした電源構成が検討されると一般的にはみられている。長期連載『エネルギー動乱』の本稿では、今後の議論のポイントを整理する。(エネルギーアナリスト 巽 直樹)
エネルギー基本計画は
今年が更新期限
岸田文雄首相は今年3月28日、本年度予算および税制法案成立後の記者会見において、「2024年度中をめどとするエネルギー基本計画改定に向けて、議論を集中的に行う」ことを表明した。
エネルギー基本計画はエネルギー政策基本法の定めにより「少なくとも3年ごと(同法12条5)」に見直され、必要に応じて変更される。現行の第6次エネルギー基本計画は21年10月22日に閣議決定されたため、今年は更新期限の年となる。
同法には、経済産業相の諮問機関である総合資源エネルギー調査会へ意見を聞いて計画案を作成することが定められている。よって、この集中的に行うとされている議論は前回と同様、同調査会に設置された基本政策分科会を中心に、電力・ガス事業分科会などの各分科会における審議の中で進められる。
現行のエネルギー基本計画では、30年度において温室効果ガス46%削減(13年度比)を目標とすることを前提とした電源構成が示された。そして、イギリス・グラスゴーで開催されたCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)の直前に国連へ提出されたNDC(国が決定する貢献)の根拠ともなった。
よって、次の第7次エネルギー基本計画でも、国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が求める「35年に60%削減(19年比)」を目標とした電源構成が検討されると、一般的にはみられている。このような状況の中、今月15日に基本政策分科会が開催され、次期計画の策定に向けた議論が本格的に開始されたのである。







