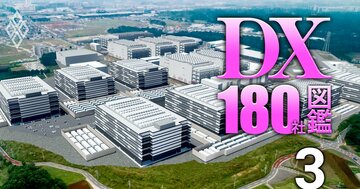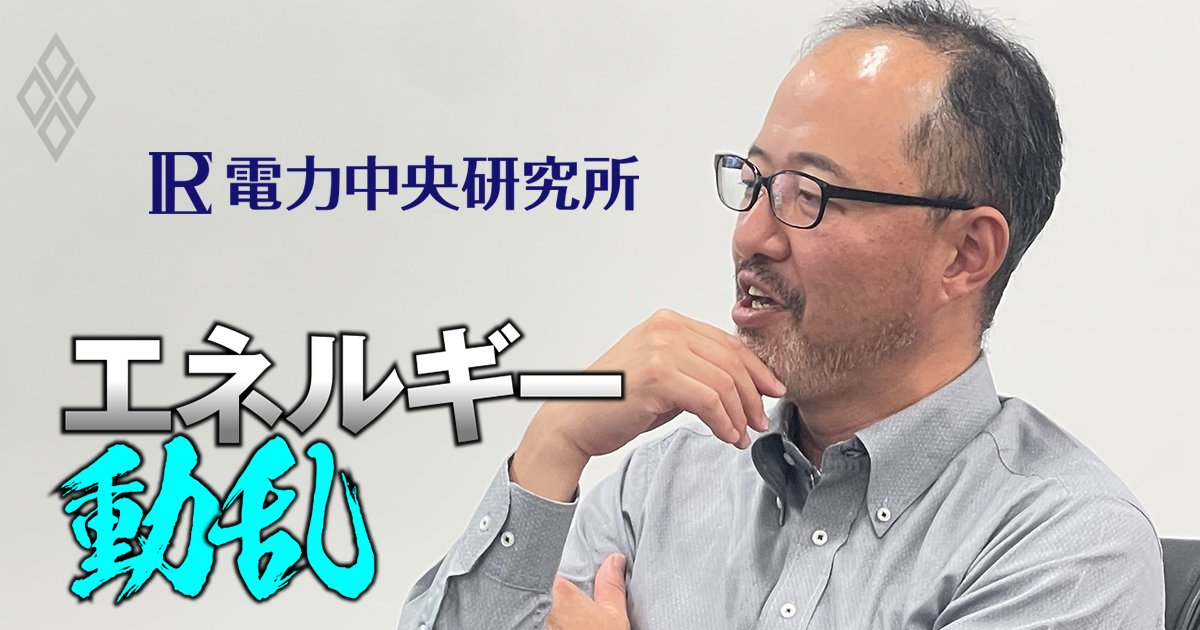 写真:アクセンチュア提供
写真:アクセンチュア提供
急激なAI普及がデータセンターの建設ラッシュを巻き起こしていることから、電力需要が大幅に伸びる可能性が高まっている。これに電力供給が追いつかない場合、将来において大幅な供給力不足が懸念されている。そもそも需要予測は難しく、電源開発や送配電網整備には時間がかかる。長期連載『エネルギー動乱』の本稿では、これらが引き起こしている複雑な問題について、電力中央研究所社会経済研究所の朝野賢司副研究参事に聞いた。(アクセンチュア ビジネスコンサルティング本部マネジング・ディレクター 巽 直樹)
「衝撃的」と報道された
OCCTOの報告書
――2025年7月に公表された電力広域的運営推進機関(OCCTO)での「将来の電力需給シナリオに関する検討会」の報告書が話題になっています。一部では「衝撃的」といった表現をかざして報道がなされています。一方で、エネルギー業界での受け止め方はさまざまです。朝野さん自身は一連の動向をどのように分析されていますか。
この報告書は、2040年と2050年における将来の電力需給バランスを複数シナリオで示したものです。一方、今年2月に示された第7次エネルギー基本計画では、2040年の電力需給見通しとして発電電力量(kWh)と電源構成の内訳が示されていました。この報告書では、同計画で示されなかった電源ごとの設備容量(kW)が、複数のシナリオとして提示されました。
「衝撃的」とされるのは、火力発電所の経年によるリプレースが行われなかった場合、2040年と2050年の全てのシナリオで供給力(kW)が不足するとされているためです。また、需要が最も伸びて、2050年に1.25兆kWh(2024年度実績比約45%増)となるシナリオでは、全ての火力のリプレースが行われても供給力が不足しています。将来、安定供給が損なわれる懸念を示し、火力リプレースの重要性を指摘したとされています。
しかし、火力リプレースに向けた具体的な制度設計への示唆はほぼありません。発電事業者にとっても、この報告書を根拠とした将来の事業計画策定は困難です。確かに、「必要な供給力を確実に確保するためには、電源投資の回収予見性を高める事業環境整備が重要」ということは読み取れますが、これは既にエネルギー基本計画でも繰り返し強調されているのです。
例えば、この報告書の目的の一つは、「長期脱炭素電源オークション(脱炭素電源の供給力を20年契約で確保する入札)」の募集容量の根拠を議論することでしたが、具体化には遠かったと言えます。
――数字としてのインパクトはかなり大きいものがあるため、十分な説明責任を果たすべきだということでしょうか。