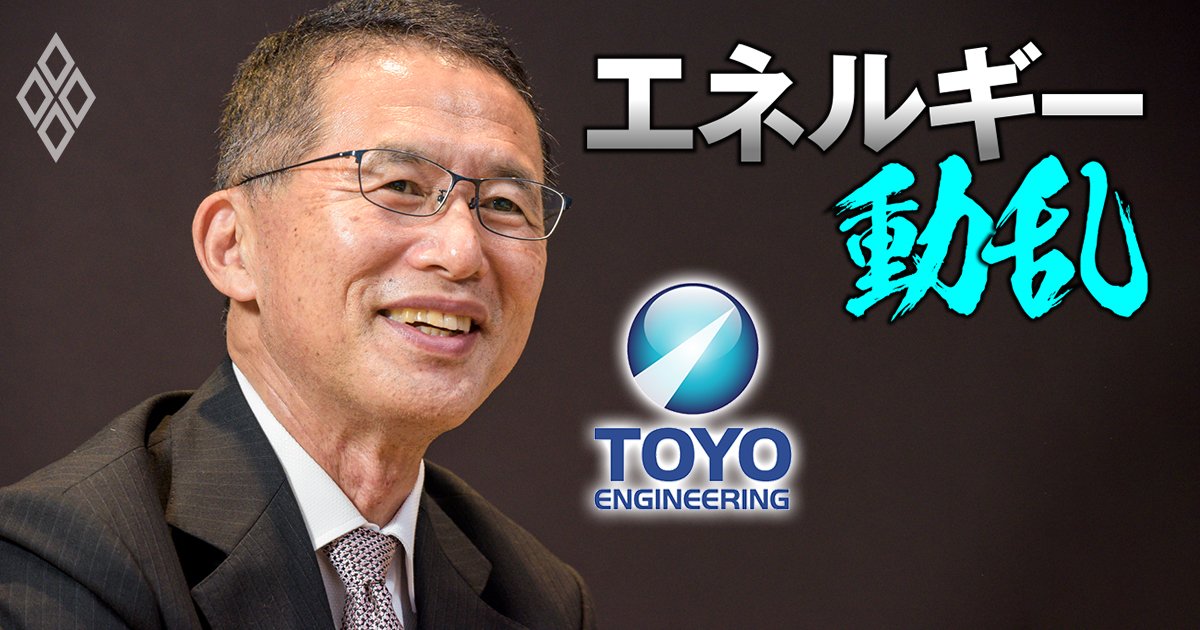 Photo by Tohru Sasaki
Photo by Tohru Sasaki
エンジニアリング大手3社の一角、東洋エンジニアリングの経営が安定している。過去には海外の大型プロジェクトで繰り返し損失を計上、業績が大きく上下するボラティリティーの高さに悩まされてきたが、足元では経営も安定化し同社の株価も大きく上昇している。長期連載『エネルギー動乱』では、東洋エンジニアリングの細井栄治社長を直撃し、ボラティリティーの高さの解決策と、今後さらに業績を伸ばしていく方策を明らかにしてもらった。細井氏は、来年度以降の業績は乱高下しないと断言。来年度以後の新たな中期経営計画期間も「超安定志向でいく」と明言した。(聞き手/エネルギージャーナリスト 宗 敦司)
特異なビジネスモデルの東洋エンジ
今年度までの中計で経営安定化進める
東洋エンジニアリングは、日揮ホールディングスや千代田化工建設が柱とする大型LNGプロジェクトを扱っておらず、石油化学プラントのEPC(設計、調達、建設)を中核としてきた。日本のエンジニアリング会社として珍しい尿素肥料のライセンス事業を展開するほか、海外拠点が独立的にEPC事業を手掛けるなど同業他社に比べてユニークなビジネスモデルだ。
しかし過去には度重なる損失計上が続き、経営が安定してこなかった。米国のエチレンプラント建設プロジェクトで大きな損失を出して以後、2021年度から今年度までの中期経営計画では、EPC事業の強靭化を図る「ブルー戦略」、脱炭素関連の新規分野の拡大を図る「グリーン戦略」を展開。またリスクの高いプロジェクトを受注しない選別受注や、利益率の高い非EPC案件へのシフトにより、経営安定化を図っている。
同社の売上高は2025年3月期に2780億円となり、2期連続の増収。25年3月期の純利益は20億円と24年3月期の98億円から減少したが、24年3月期は本社売却益の計上があった。25年3月期の純利益は23年3月期以前と比べると着実に伸びている。
ただし、カーボンニュートラル(温暖化ガス排出実質ゼロ)の失速など想定外の要因もあり、来年度以降の新中期計画での方向性が問われている。次ページでは、細井栄治社長にこれまでに収益の安定化をどのように進めてきたかを明かしてもらう。また、今後力を入れていく事業や受注高が多いFPSO(浮体式原油生産貯蔵出荷設備)事業の動向も解説してもらった。
――過去5年で株価が6倍になっていますがこれまでの改革が評価されたと感じていますか。







