
巽 直樹
東京電力ホールディングスの柏崎刈羽原子力発電所の再稼働によって原子力政策に関心が向けられる裏で、火力発電が正念場を迎えている。脱炭素の推進とともに存在感が薄まりつつあるが、高まる電力需要に対応するためには化石燃料の存在は無視できない。本稿では、未来がないと考えられてきた石炭火力にスポットを当て、国際競争力の観点から提言する。

前編では、エネルギー業界のマクロ動向を左右するテーマを取り上げた。後編では、このマクロのアジェンダを念頭に置きつつ、より深刻度を増すミクロ動向の五大テーマを取り上げる。OCCTOショックが突き付けた現実、原子力推進を阻む真の障壁、そしてAI活用の真価とは。2026年、日本が集中すべき「モア・フロム・レス」の道筋と、そこで起きる産業構造の激変について解説する。

2026年のエネルギー産業を動かす起点は、エネルギー自身ではなく「AI産業」や「金融市場」などの外部要因になる可能性がある。「高市政権の誕生」がエネルギー産業における課題解決を加速させる要因となり得るかも最注目点の一つである。
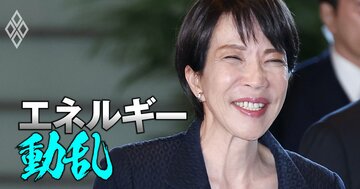
急激なAI普及がデータセンターの建設ラッシュを巻き起こしていることから、電力需要が大幅に伸びる可能性が高まっている。これに電力供給が追いつかない場合、将来において大幅な供給力不足が懸念されている。そもそも需要予測は難しく、電源開発や送配電網整備には時間がかかる。これらが引き起こしている複雑な問題について、電力中央研究所社会経済研究所の朝野賢司副研究参事に聞いた。
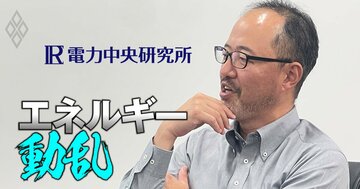
7月、関西電力は福井県にある同社美浜発電所でのリプレース(建て替え)に向けた自主的な調査の再開を発表し、大きな話題を呼んでいる。一方これより約半年前、原子力事業本部で初となる女性役員の就任を公表した。野地小百合執行役常務・原子力事業本部長代理に、原子力部門における多様性の推進と組織変革への挑戦を伺った。

世界のエネルギー政策・産業が大きな曲がり角を迎えているなか、日本のGX政策の方向性はおおむねブレてはいない。GX推進での重要な役割が期待されている「ワット・ビット連携」の提唱者であり、日本の電力ネットワークのキーパーソンである東京電力パワーグリッド取締役副社長執行役員CTO(最高技術責任者)の岡本浩氏へのインタビュー後編をお届けする。
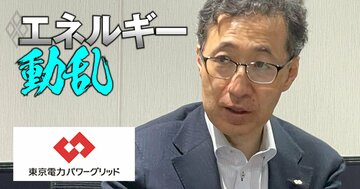
世界のエネルギー政策・産業が大きな曲がり角を迎えているなか、日本のGX政策の方向性はおおむねブレてはいない。GX推進での重要な役割が期待されている「ワット・ビット連携」の提唱者であり、日本の電力ネットワークのキーパーソンである東京電力パワーグリッド取締役副社長執行役員CTO(最高技術責任者)の岡本浩氏へのインタビュー前編をお届けする。

激動の世界情勢の中でエネルギー政策とビジネスの潮目が変わりつつある。日本のエネルギー政策はどうあるべきか、企業戦略の方向性はどうなるのか。リアリティーの高いエネルギー経済政策を提言している慶應義塾大学産業研究所所長の野村浩二教授へのインタビュー後編をお届けする。
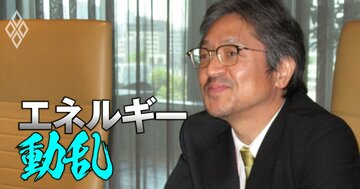
激動の世界情勢の中でエネルギー政策とビジネスの潮目が変わりつつある。日本のエネルギー政策はどうあるべきか、企業戦略の方向性はどうなるのか。リアリティーの高いエネルギー経済政策を提言している慶応義塾大学産業研究所所長の野村浩二教授へのインタビュー前編をお届けする。

各国のエネルギー安全保障や国際競争力の維持のためには「脱炭素」ではなく「低炭素がちょうどよい」という認識で世界は落ち着くのであろうか。「大転換点になった2025年」と見なされる可能性もある今年、世界の様々な動向から、ますます目が離せない。

大きな政治的転換に取り掛かったアメリカと、矛盾が一気に噴出しているドイツ。「エネルギー政策における失敗」は国家を傾かせるインパクトを秘めていることを改めて教えてくれる。エネルギーの専門家が両国を比較して論評し、米大統領令のエネルギー関連項目についても詳細に解説する。
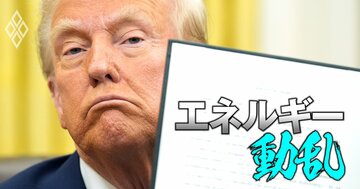
2025年のエネルギー業界の重要テーマは米国によるエネルギー政策の大変更、それによりもたらされる世界へのさまざまな影響である。日本のエネルギー・環境政策にどのような影響があるのか。当面は米国の動向をいやが上にも注視するしかない。エネルギーの専門家が25年の10大テーマを挙げた。本稿では後編をお送りする。

2025年のエネルギー業界の重要テーマは米国によるエネルギー政策の大変更、それによりもたらされる世界へのさまざまな影響である。日本のエネルギー・環境政策にどのような影響があるのか。当面は米国の動向をいやが上にも注視するしかない。エネルギーの専門家が25年の10大テーマを挙げた。本稿では前編をお送りする。

第7次エネルギー基本計画策定に向けた政府の各種会合での議論に注目が集まっている。9月27日には自民党総裁選挙の投開票も控えており、エネルギーに関連するものについての議論にも熱が帯びると期待している。

今年は世界中の国・地域で、今後の政治の方向性を大きく左右する「選挙イヤー」であることが、各所で話題になっている。7月に入り、いよいよ後半戦へと突入。14年ぶりの政権交代が起きた英国のエネルギー政策の方向性について考察する。

国のエネルギー基本計画の改定議論が本格的にスタートした。国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が求める「2035年に60%削減(19年比)」を目標とした電源構成が検討されると一般的にはみられているが、何がポイントになってくるのか。
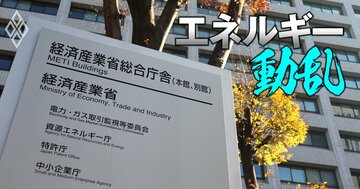
エネルギー問題における将来の見通しを持つためにも、世界の政治イベントの情勢分析が欠かせない上に、結果がもたらす意味を理解しておく必要がある。今年欧米で控える選挙とその影響予想を整理しておきたい。

能登半島地震で改めて注目が集まった原子力発電。COP28での議論でも分かったように世界は原発推進のメガトレンドにある。日本はどうするのか。

来年のエネルギー業界の重要な話題について国内と海外でそれぞれ5つずつ選び、2回に分けてお届けする「2024年エネルギー業界の超重要テーマ」の後編。今回は海外の話題を取り上げる。

来年のエネルギー業界の重要なテーマについて国内と海外でそれぞれ5つずつ選び、「2024年エネルギー業界の超重要テーマ」として、2回に分けてお届けする。前編の今回は国内のエネルギー業界だ。
