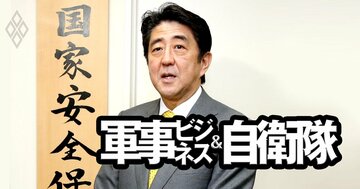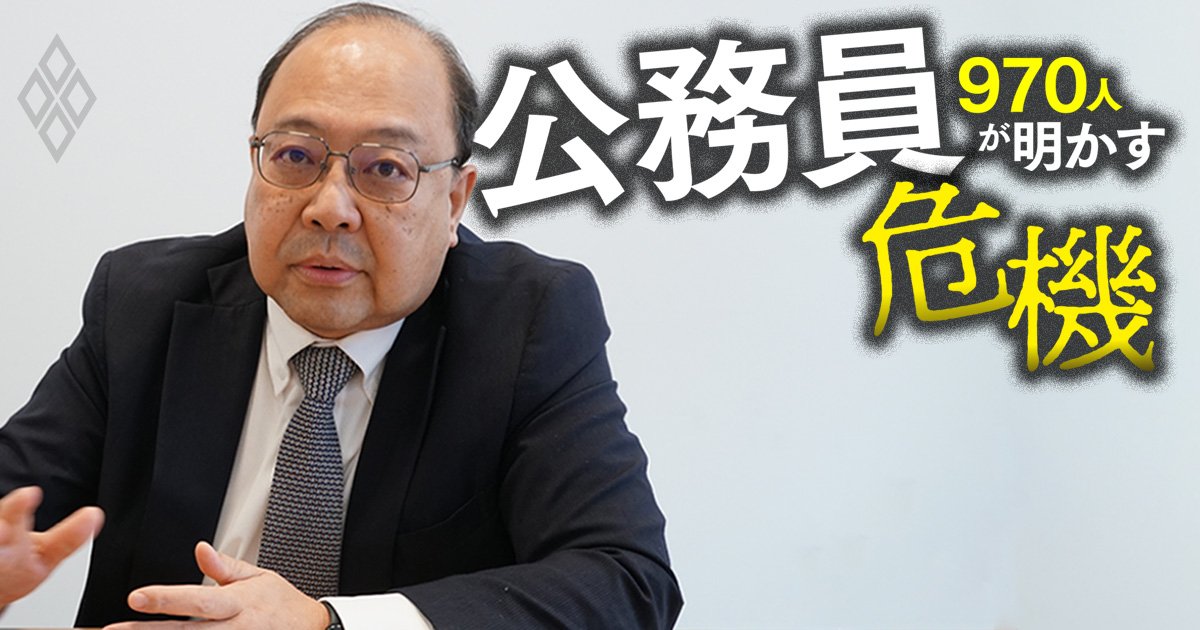 たにわき・やすひこ/1960年生まれ。84年郵政省(現総務省)入省。2005年電気通信事業部料金サービス課長、07年電気通信事業部事業政策課長、08年情報通信政策課長、13年内閣審議官・内閣サイバーセキュリティセンター副センター長、16年情報通信国際戦略局長、17年政策統括官、18年総合通信基盤局長、19年総務審議官を経て21年総務省退官。22年よりインターネットイニシアティブ取締役副社長。 Photo by Hirobumi Senbongi
たにわき・やすひこ/1960年生まれ。84年郵政省(現総務省)入省。2005年電気通信事業部料金サービス課長、07年電気通信事業部事業政策課長、08年情報通信政策課長、13年内閣審議官・内閣サイバーセキュリティセンター副センター長、16年情報通信国際戦略局長、17年政策統括官、18年総合通信基盤局長、19年総務審議官を経て21年総務省退官。22年よりインターネットイニシアティブ取締役副社長。 Photo by Hirobumi Senbongi
菅内閣が実施した携帯電話料金の値下げは、国民から支持を集めた政策といえるだろう。特集『公務員970人が明かす“危機”の真相』の#9では、この政策を推し進めた谷脇康彦・元総務審議官に、行政官の仕事の流儀を聞いた。同氏は、NTTからの接待問題で辞職した経緯があるが、それでも、あえて官民の情報交換の重要性を強調する。「役所の中にいても政策のネタは一つもない。教えを請いに外に出なければ、ひらめきはない」と断言する谷脇氏の真意とは。(聞き手/ダイヤモンド編集部副編集長 千本木啓文)
官僚が政策メニューを示せない状況は
政治家にも国民にも不幸である
――谷脇さんは総務省時代、携帯電話の値下げを実現したことで名をはせました。大手通信キャリアなどから抵抗があったと思いますが、どのように改革を進めたのですか。
私は、携帯ビジネスの改革に2回取り組みました。1回目は課長のときです。ガラケーのいわゆる「ゼロ円携帯」の問題を是正しました。
それには「きっかけ」がありました。街の商店街を歩いているとき、ドラッグストアと携帯ショップを数えたら同数だったのです。何万円もする携帯を売る店と、ティッシュペーパーなどの生活用品を売る店の数が同じということに違和感があった。
当時はゼロ円携帯が多く、 高校生は3カ月に1回は機種変更している。新しい携帯がもらえるからです。一方、お年寄りは3年ぐらい大事に使っている。これは、どう考えたっておかしい。通信会社は、高校生が得する分のコストを、さまざまな世代が払う通信料金で賄っているのですから。
「負担の不公平感をなくしましょう」ということを言って、端末代金と通信料金を分け、消費者が何に対し幾ら対価を払っているのかを分かるようにしました。
それにより端末の販売台数が減ったので、業界から「谷脇不況」などといわれました。欧州などでも端末価格と通信料金は分かれていましたから、日本だけおかしなことをやったわけではありません。
――安倍内閣で、当時の菅義偉官房長官が携帯の料金の値下げを宣言しました。格安を売りにする楽天モバイルが通信事業に新規参入するなどして料金が大幅に引き下げられました。
その当時が、携帯ビジネスに関わった2回目ということになります。私は、ずっと通信会社は公平公正な条件で競争すべきだという問題意識があったので、さらにそれを進め法改正も行いました。
菅さんは総務副大臣の頃から携帯の問題について話をされていました。官房長官になられてからも、「携帯は高いよな、料金が分かりにくいし」とよくおっしゃっていました。だから、携帯市場の改革について同じ思いを持っていたということです。
――行政官としては幸運で、いい巡り合わせでしたね。
そうだと思います。
――改革マインドが高かった安倍内閣、菅内閣から岸田内閣に変わって、国家公務員の仕事や働きがいは変わりましたか。
政権が代わったからといって、役人の働き方が変わることはあまりないと思います。政権が目指すものは当然、政治から示されます。役人にとって大事なのは、政治が目指すものに対して、厚みのある政策メニューを提示することです。私自身も常にそれを心掛けていました。
――政権交代があって方針が変わっても、自分なりの選択肢を常に考えておくということですか。
そうですね。民主党政権では、総務相に就任された原口一博さんが求めることを踏まえて自分の引き出しから政策メニューを示して、良ければ採用していただくということもやりました。
ただし、政権に迎合するような政策を提示するということではないのです。通信政策でいうと、競争をどれだけ促進させるかということがベースにありました。支配的な事業者への規制や消費者の保護などです。国際的な通信政策のルール作りなども含め、自分の政策のフレームワークは常に持っていました。変えてはいけない部分と、その時々にメニューとして提示できるものを両方持っていないといけません。
なぜ中央省庁に入ったのか。給料は安かったですが、若いうちから国のルールに関わる大きな仕事をやらせてもらえるというメリットがあった。そういった仕事に携われるのが働きがいでした。今霞が関を目指す人たちも同じ気持ちだと思います。
――現在の中央省庁の政策立案能力をどう評価していますか。
他省庁は知らないので、総務省の情報通信行政について言うと、 かなり頑張っていると思います。技術が急速に変化する中、海外のルールと調和を図りつつ、国内のさまざまな意見を丁寧に吸い上げた上で、政策をなるべく論理的に説明するということはできている。
――課題は何でしょうか。
人が足りないことです。米国には共和党系、民主党系の政策シンクタンクがいろいろあります。日本にはそれがあまりないので、霞が関がシンクタンクのような役割を担っています。だから、さっき言ったように政策メニューをどんどん提示しないといけない。しかし、業務の量は減らず、むしろ増え、落ち着いて考える時間が少ない。その結果、その提案に深みがなくなっているなら憂慮すべき事態じゃないでしょうか。
次ページでは、谷脇氏に、採用の責任者として経験した苦労や、官民の情報交換が不可欠だと考える理由を語ってもらった。