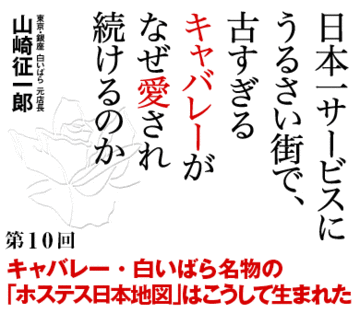Illustration by MIHO YASURAOKA
Illustration by MIHO YASURAOKA
【前回までのあらすじ】芸能界で活躍する夢を諦めつつあったレイ子は、右翼青年、鬼頭紘太から「政界の黒幕」といわれる老人の世話をする仕事を紹介される。政治や権力に興味を抱いていた彼女は、不安を覚えつつその仕事をやってみることにした。(『小説・昭和の女帝』#5)
政界の黒幕のよからぬ性癖とは…
神楽坂の商店街を歩いていて、なつかしい声を聞いた。店から聞こえてくるBGMが、所属していたコーラスグループの歌声だったのだ。曲には聞き覚えがなかった。立ち止まって耳を傾けると、最近、流行りの軍歌だった。「月月火水木金金」――。歌詞もメロディーも、悪趣味だと思った。
レイ子が歌手を目指していたころは、もう少しましな時代だった。彼女は、西洋の女性のように振る舞う、自由と解放を象徴するスターになりたいと思っていた。だが、時代はそういうスターを求めていなかった。
かつての仲間が歌う軍歌を聞いて、コーラスをやめてよかったと思った。と同時に、だからといって現在の自分の生活が幸せかどうかは別だと、複雑な気持ちになった。
真木甚八の屋敷に住み込みで働くようになって3年余りがたった。政界も財界も殺気立ってきていた。夏にアメリカが石油の対日輸出を禁止して、いよいよ対米開戦が避けられなくなったようだった。
◇
赤坂の事務所で書類の整理をしていると、突然の来客があった。彼女を甚八に紹介した鬼頭紘太だった。久しぶりに見る彼は、負け戦から帰ってきたかのように人相が変わっていた。大陸で軍のために働いていると聞いていた。
いま思えば、出会ったころは、まだ幼さが残っていた。当時26歳だった彼には、かつて主導したクーデター未遂を誇っているような青臭さや、次のテロリズムに備えるような危うさがあった。彼が五・一五事件の直後、別のクーデターに関わり、懲役3年半の判決を受けて収監されていたことを甚八から聞いていた。
軍の下請けをしているという鬼頭の顔は、仮面のようだった。いまでは戦争を遂行する体制側の人間として、多数の人間の生死を左右している。そういう男がつける鉄の仮面だった。戦争に勝つために必要なことをやるしかないという覚悟と諦念が四囲ににじんでいた。
「久しぶりだね。すっかり真木先生のお気に入りだそうじゃないか」
「おかげさまで」
鬼頭は、レイ子が記憶している彼よりも馴れ馴れしかった。
昭和の女帝
小説・フィクサーたちの群像
千本木啓文著
<内容紹介>
自民党の“裏面史”を初めて明かす!歴代政権の裏で絶大な影響力を誇った女性フィクサー。ホステスから政治家秘書に転じ、米CIAと通じて財務省や経産省を操った。日本自由党(自民党の前身)の結党資金を提供した「政界の黒幕」の娘を名乗ったが、その出自には秘密があった。政敵・庶民宰相との壮絶な権力闘争の行方は?