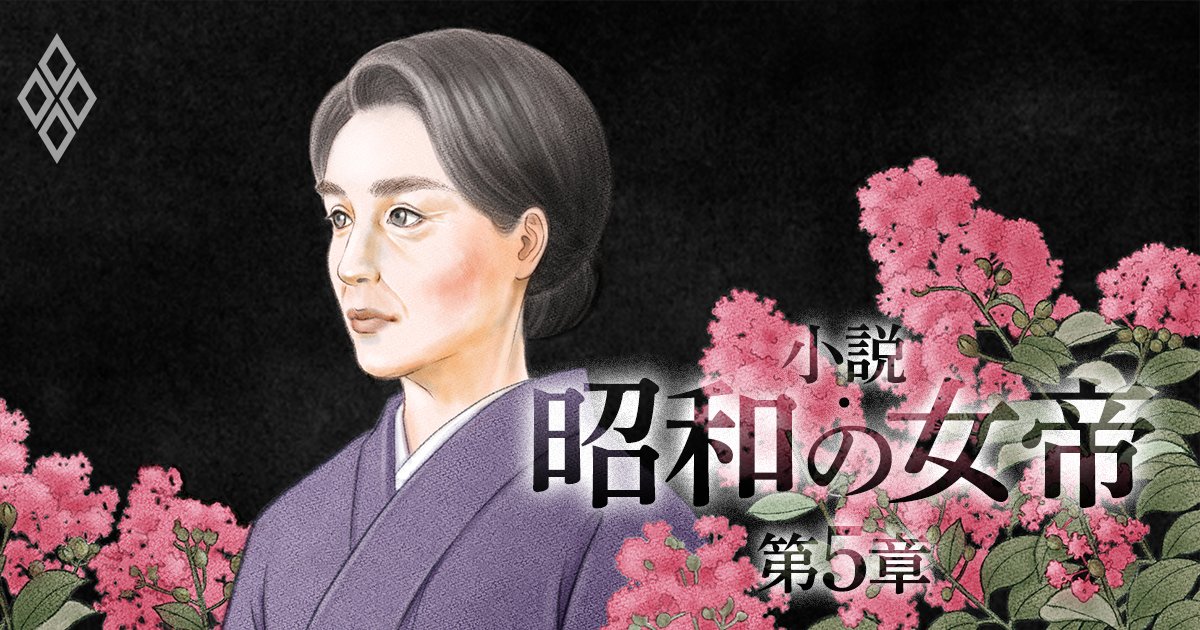 Illustration by MIHO YASURAOKA
Illustration by MIHO YASURAOKA
【前回までのあらすじ】「昭和の女帝」真木レイ子は、ライバルで元総理の加山鋭達の秘書兼愛人、小林亜紀の訪問を受ける。L社事件の裁判で加山に有罪判決が出た直後だった。加山が裁判で不利になるような動きをレイ子がしていたこともあって、二人の会話はぎくしゃくしたまま終わる。(『小説・昭和の女帝』#40)
弟分の政治家が明かした政界大再編の野望
1984年の師走、レイ子の母が泉下に没した。
宮澤喜一をはじめとした宏池会の幹部がその日の夕方のうちに弔問してくれた。
自宅から斎場まで霊柩車で移動するとき、信号はすべて青に変わりノンストップだった。警察庁長官が気を利かせてくれたようだった。
通夜は憂鬱だった。夕方、降り出した雨がみぞれに変わった。参列客たちは斎場に着くと、傘を振ったり、トントンと石畳に打ち付けたりして氷の粒を落とそうとする。そう簡単には落ちないと分かると、忌々しそうに傘をたたみ、本堂に入る。その繰り返しだった。レイ子は喪主として、半ば機械的にお辞儀を繰り返した。みぞれが雪に変わったころ、来年度の予算編成で多忙を極めているはずの大蔵省幹部たちが顔を見せた。国会議員や馴染みの秘書仲間もやって来た。
しかし、レイ子は空々しいものを感じていた。政界関係者はお悔やみを言ってくれるが、彼女や母が歩んできた数奇な人生を知っているわけではない。芸者だった母は私生児のレイ子を産み、新聞店の経営者と結婚。その後、レイ子が「真木レイ子」になってから、母も無理やり「根本トシ」から「真木トシ」に改名させられ、新聞店の経営者とは離婚を強いられた。これから、鬼頭が都内に建てた甚八の墓に入ることになる。母のお骨は、本当の夫婦でないばかりか、面識さえない甚八の隣に納められるのだった。
政界関係者は、神妙な面持ちで集まってくるが、永田町での人間関係など所詮、打算的なものにすぎない。加山鋭達が総理大臣へと上り詰めていくに従って、政治家や官僚がレイ子に寄り付かなくなったとき、彼らの薄情さを思い知らされた。
そのように自分の人間関係を振り返ってみると、気を許せる人は結局、母一人だけだったのかもしれないとも思う。
葬儀を終えたレイ子は、クリスマス、大晦日を独りで過ごした。元日は例年、自邸で新年会を開くので賑やかだったが、その年は静かだった。
◇
正月休みの最終日、レイ子の弟分で大蔵官僚から参院議員になり、衆院議員にくら替えした藤本久人がやって来た。
「お姉さまが大変なときに傍にいることができず申し訳ありませんでした」
「いいのよ。母の葬儀に来てくれただけで。皆さんに参列いただいて、ありがたかったわ」
藤本は官僚時代、竹下登と二階堂進という2人の加山派の官房長官に秘書官として仕えた縁で加山派に所属していた。レイ子の母の葬儀に出席するだけでも、加山派内で白い目で見られかねず、政治的にはリスキーなはずだった。
政界入りしてからの苦労の表れなのか、藤本の額は後退し、白髪が増え始めていた。
「それで、今年はどうなりそう。加山派はどんな様子?」
「それが……、どうも良くありません。というか、分裂は避けられそうにありません。喪に服しているお姉さまには悪いのですが、来月、娘の結婚式があるんです。そこで加山派から、加山先生ご本人と、二階堂先生、竹下先生を招待して来賓のあいさつをいただくことにしたんですが」
「何かあったの」
「ご存じの通り、加山派は、あくまでオヤジを立てようという保守派と、いつまでもオヤジに従っていては政治を変えられないという独立派に分かれています。二階堂先生は保守派ですから、披露宴でのごあいさつは、保守派2人に対して、独立派は竹下先生だけ、1人になってしまいます。そこで、独立派の金丸信先生が、自分も招待するように、と電話で言ってきたんです。保守派を2人呼ぶなら、独立派も2人呼べという意味です。加山派の亀裂は決定的です」
「つまらない張り合いをしているわね。あなたも娘さんも、お歴々4人の祝辞を聞かなきゃいけないなんて……」
昨年末、金丸が、加山派の若手を築地の料亭に集め、独立派の勉強会を立ち上げる決起集会を開いていた。今年2月に正式に勉強会が発足し、橋本龍太郎、小渕恵三、梶山静六、小沢一郎ら鋭達の子飼いたちが参加すると見られていた。勉強会とはいえ、独立派のトップである竹下を総理総裁に押し上げるための新たな派閥の立ち上げに等しかった。
独立派の不満は人事だった。加山派は最大派閥として君臨しているにもかかわらず、自派から総理大臣を出さなかった。鋭達が、「自分より若い子分が総理になれば、自らの影響力がなくなるのではないか」と恐れているからだった。結果として、大平正芳、鈴木善幸、中曽根康弘という非加山派の3人を首班とする加山傀儡政権が誕生したが、その間、加山派は良くて大臣止まり、大臣になるのですら他派閥より遅れる議員が出てくる始末だった。不満は、爆発寸前だった。
「あなたも大変ね。出馬するように言われたときは、『権力闘争は好かないから』と政界入りを断っていたけど、結局は権力争いに巻き込まれてしまったわね」
「まあ、そういうことです。でも、お姉さま、議員になってよかったと最近では思っているんです」
「あら、政治家としての使命でも見つけたの?」
「その通りです。私の使命は、時代遅れの加山派を潰すことです」
藤本は真剣な表情で言った。
昭和の女帝
小説・フィクサーたちの群像
千本木啓文著
<内容紹介>
自民党の“裏面史”を初めて明かす!歴代政権の裏で絶大な影響力を誇った女性フィクサー。ホステスから政治家秘書に転じ、米CIAと通じて財務省や経産省を操った。日本自由党(自民党の前身)の結党資金を提供した「政界の黒幕」の娘を名乗ったが、その出自には秘密があった。政敵・庶民宰相との壮絶な権力闘争の行方は?















