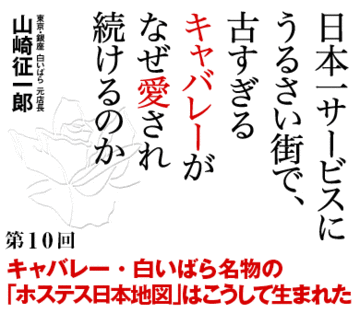Illustration by MIHO YASURAOKA
Illustration by MIHO YASURAOKA
【前回までのあらすじ】昭和の女帝は19歳のころ、芸能界を目指しつつも、新橋のバーで女給をしていた。彼女はバーで、政治家や官僚、経営者らと会話を交わす中で、「権力」の魔力に見せられていく。(『小説・昭和の女帝』#4)
悩める昭和の女帝に、芸能マネージャーが紹介した男とは
七夕の日、北京郊外の盧溝橋付近で日本軍と中国軍が衝突し、本格的な戦争が始まった。加山鋭達がバーに現れてから2カ月後のことだった。
レイ子は、兵隊になった加山が大陸に渡り行軍する姿を想像したが、ちょび髭を生やした彼の顔に軍服は何とも似合わず、思わず苦笑いしてしまった。
実は、加山と同様、レイ子も人生の転機を迎えていた。所属していたコーラスグループは歌劇団の一部だったが、軍部から求められた国威発揚の音楽をやる一派と、初志貫徹でオペラを志向する一派とに分裂することになったのだ。
レイ子は軍歌が嫌いだったので、後者のグループに入りたかった。しかし、そうもいかない事情があった。後者を選ぶのは音大出身の裕福な人が多いが、彼女にそのような経済的な余裕はなかった。母の結婚相手は、レイ子の芸能活動を面白く思っていなかった。それはいまに始まったことではない。幼いころ、やめろと言われている三味線をこっそり練習しているのがばれて、三味線をたたき割られたことがあった。育ての父にとって、芸事は時間ばかり食うわりに一銭にもならない無駄なお遊びなのだった。
レイ子の歌劇団での活動が、コーラスからオペラに格上げとなれば、衣装代やレッスン代もこれまで以上にかさむ。それは、ホステスの給料でどうにかなる金額ではなかった。
しかも、彼女には、家を出ていけという圧力がかかっていた。朝早くから働く新聞配達店の実家に、バーで働く彼女の生活は馴染まなかった。たばことアルコールの臭いをさせて深夜に帰宅すると、継父から露骨に嫌な顔をされた。
ただ、そうした圧力は渡りに船でもあった。継父に親しみを覚えることはなかった。それどころか、最近は、いやらしい視線を感じることもあった。レイ子がそれに気づいた素振りをしても、じっとりと視線が張り付いてくる。汚らわしく、許し難いことだった。母もそれに気づいていたが見て見ぬふりをした。
レイ子は年を重ねるにしたがって、母との性格の違いを認識せずにはいられなかった。母は意見を表に出さず、長い物に巻かれる。そんな母に反発を覚えてきたが、いよいよ許せないほどになっていた。
家を出て、自由になりたい。だが、下宿をすれば出費が増える。経済事情からすれば、オペラに挑戦するなど夢のまた夢だった。
彼女は、歌劇団のマネージャーに家の事情を打ち明けた。マネージャーとはぶつかることも多かったが、酸いも甘いも噛み分けているようなところがあり、信頼していた。
マネージャーは、彼女の話を聞くと、「それなら、ちょうどいい話がある」とニヤリと笑い、日本橋である人物に会うように言った。「オーディションではないので、地味な服で行ったほうがいい」と助言した。そこで、レイ子が出会う人物こそ、彼女の運命を変えることになる鬼頭紘太、その人であった。