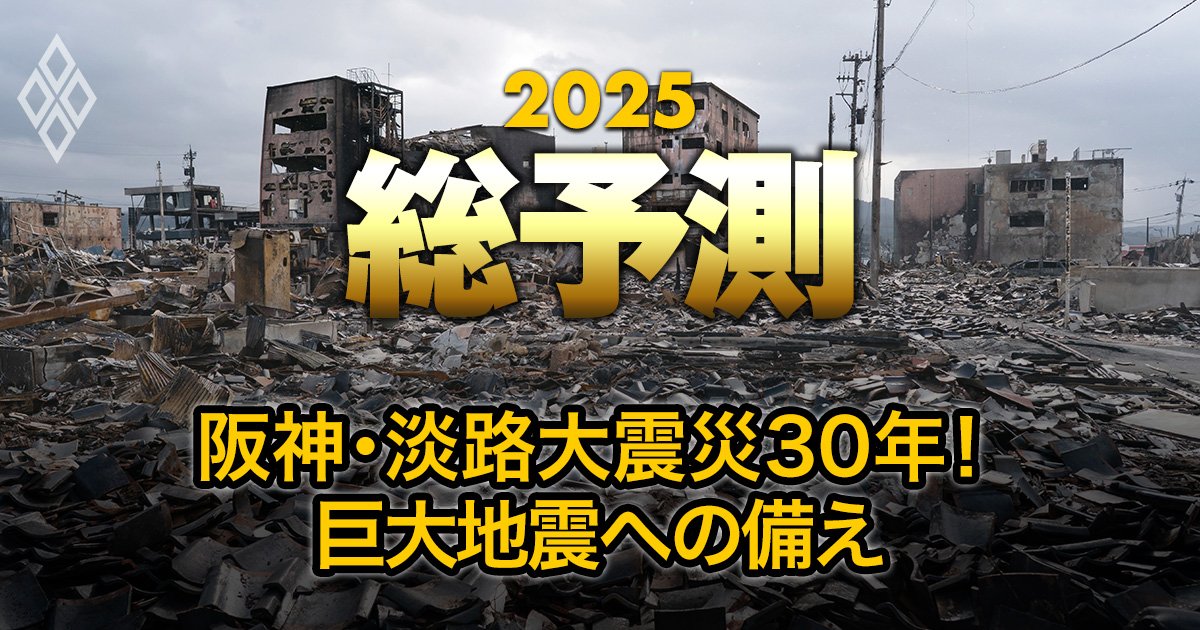 Photo:Tomohiro Ohsumi/gettyimages
Photo:Tomohiro Ohsumi/gettyimages
2025年は阪神・淡路大震災の発生から30年の節目を迎える。震災がもたらした教訓をどのように生かし、首都直下地震や南海トラフ地震などの巨大地震に備えて行くべきなのか。特集『総予測2025』の本稿では、大阪・関西万博なども控える25年の地震防災について、関西大学特任教授の河田恵昭氏に話を聞いた。(聞き手/ダイヤモンド編集部 澤 俊太郎)
南海トラフ臨時情報の意義
現実的な行動に結びつく
 かわた・よしあき/1946年生まれ、大阪市出身。京都大大学院博士課程修了。関西大特別任命教授で防災学が専門。人と防災未来センター(神戸市)のセンター長で、多数の防災研究会等委員会を歴任。 Photo by Sawa Shuntaro
かわた・よしあき/1946年生まれ、大阪市出身。京都大大学院博士課程修了。関西大特別任命教授で防災学が専門。人と防災未来センター(神戸市)のセンター長で、多数の防災研究会等委員会を歴任。 Photo by Sawa Shuntaro
――2024年は地震災害を考える上で、どのような年だったと思いますか。
24年8月に南海トラフ地震臨時情報が発表されましたが、これは非常に大きな意義がありました。精度が悪かったという反省はあるものの、南海トラフ地震が起きることにひとごとだった人々が、備蓄の問題や避難所の確認など、現実的にどう行動しなければいけないか、一斉にメディアを通じて知らされた。被害を少なくするという観点では大きな意義があった年だと思います。
――25年は阪神・淡路大震災から30年の節目を迎えます。あの震災の教訓は今にどう生きているんでしょうか。
30年の節目を迎える阪神・淡路大震災。次のページでは、震災の教訓をもとに、25年に開催される大阪・関西万博における地震対策の死角を明らかにする。







