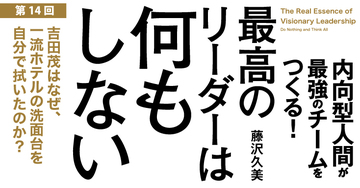Illustration by MIHO YASURAOKA
Illustration by MIHO YASURAOKA
【前回までのあらすじ】「昭和の女帝」真木レイ子は、鳩山一郎、吉田茂らによる保守合同に向けた話し合いに同席するなど権力の中枢にいた。他方、鬼頭紘太の力は低下していた。アメリカにとって鬼頭の価値は、戦争に欠かせないレアアースなどを調達するのに役立つことだったが、朝鮮戦争が休戦となったことで重要人物ではなくなったのだ。政界で稼ぎづらくなった鬼頭は、財界に手を出し始めた。(『小説・昭和の女帝』#21)
インドネシア大統領と19歳の女性が「お見合い」そのときレイ子は?
自由民主党発足前夜、衆院議長を務める粕谷英雄の部屋に、鳩山一郎総理と吉田茂前総理が集まった密談から4年――。密談の給仕を務めた真木レイ子は41歳になっていた。
毎朝目覚めると、紅茶を飲みながら新聞5紙に目を通す。
庭では、紫のあじさいが見事に咲き誇っていた。敷地224坪、建坪80坪の屋敷は鬼頭紘太が用意したものだが、庭だけは彼女の趣味で造り直した。桜、しょうぶ、あじさい、さるすべりなど四季の草木を植え、年を通じて花が咲くようにした。
真木甚八の屋敷に親しんでいた彼女にとって庭は特別な存在だった。庭園というものは、一人の主が単一の美意識で作り込まなければいけない。石垣や石畳といった地味なものも含めて、全体が調和していなければ醜くなってしまう。鬼頭から与えられた屋敷を、落ち着ける空間にするためには庭の改造が最優先だった。
リビングのガラス窓に映る姿は、二十代のころから衰えていない。毎日会食続きでもウエストが引き締まっているのは甚八の言いつけを守って酒を控えているからだ。
彼女の美貌や権力に引き寄せられ、好意を示す政治家や財界人はいるにはいた。だが、最後の一押しのところで腰砕けになる男ばかりだった。彼女は右翼の大立者の娘であり、現在の後ろ盾は鬼頭紘太だ。
鬼頭の恐ろしさ、残忍さは広く知れ渡っていた。歯向かってきた人間は、たとえ国会議員でも社会的に抹殺する。それが、鬼頭のやり方だった。彼の悪事を国会で暴こうとしたある野党議員は、女性関係などの恥部を調べ上げられて首根っこを押さえられただけでなく、見せしめにそれを暴露され、国会議員のバッジを外さざるを得なくなった。
男たちにとって、レイ子に手を出すということは、虎のしっぽを踏みに行くようなものなのだ。
彼女は鬼頭の傘の下にあり、抑えつけられている身ではあったが、永田町での影響力は増す一方だった。「永田町のスーパーレディー」と称されていたころは、美貌と才覚が賞賛されていた。いまではそこに権力が加わっていた。岸内閣で粕谷が副総理に就任したときには、新聞紙面で「初の女性副総理秘書官」などとはやされた。
番記者まで付く秘書は、永田町広しといえども彼女だけだった。大蔵大臣の佐藤栄作や、通商産業大臣の池田勇人といった官界出身の政治家は資金力がなく、カネ集めも下手だから、とりわけレイ子を大事にした。佐藤や池田と太いパイプを持つ彼女は、大臣室にふらっと立ち寄ることができる。そうした姿を目撃したマスコミ関係者からは「政権を操る女帝」などと表現されることさえあった。
ただし、秘書の仕事はこうした華々しいものばかりではない。粕谷の地元からの陳情をさばいたり、就職の斡旋をしたりと、地味な仕事も山のようにあった。粕谷の支援者からの相談事が一日に30件を超えることもざらだった。
レイ子は自宅に迎えに来た黒塗りのセダンに乗り込んだ。その日の行き先は、いつもの永田町方面ではなく、等々力の鬼頭邸だった。どんなに忙しくとも、呼び出しがかかれば従わないわけにはいかないのだった。
◇
鬼頭邸の庭にも、あじさいが咲き誇っていた。レイ子は、自邸と同じ花が咲いていることにすら嫌悪感を覚えた。救いは、彼女の庭のあじさいは紫色の花で、鬼頭の庭にあるのは白だということだった。
案内されたのは、いつもの書斎ではなく、応接間だった。二人だけでの話し合いのときはプライベートの書斎に通される。応接間で会うのは、第三者がいるときと決まっていた。
鬼頭の家には、暴力団や芸能関係者、財界人などが人目を忍んで訪れる。
その日、応接室にいたのは細身のビジネスマンだった。鬼頭の周辺は脂ぎった政界関係者や、おしゃれに気を使わない運動家のような男たちが多い。その中で、仕立ての良いスーツに身を包んだ男は異色だった。
ふと、伊藤忠商事に入社した元大本営参謀の瀬島龍三はこの男かと思った。防衛装備品の調達で、鬼頭邸に出入りするようになったと聞いていた。
昭和の女帝
小説・フィクサーたちの群像
千本木啓文著
<内容紹介>
自民党の“裏面史”を初めて明かす!歴代政権の裏で絶大な影響力を誇った女性フィクサー。ホステスから政治家秘書に転じ、米CIAと通じて財務省や経産省を操った。日本自由党(自民党の前身)の結党資金を提供した「政界の黒幕」の娘を名乗ったが、その出自には秘密があった。政敵・庶民宰相との壮絶な権力闘争の行方は?