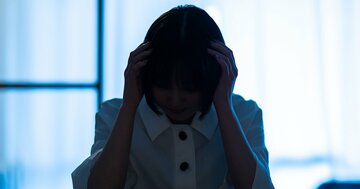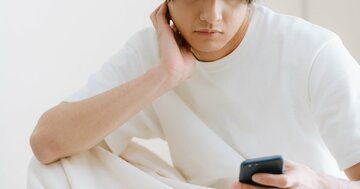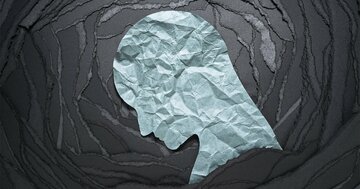消費者に不利な判断を促す
「ダークパターン」とは
「ダークパターン」ということばを耳にしたことはありますか。消費者庁の公式サイトには「消費者が気付かない間に不利な判断・意思決定をしてしまうよう誘導する仕組みのウェブデザインなどを指す」と記されています。
例示を要約すると、「『残り〇分』などと得になる期間をカウント表示しているけれど、実質は、いつ購入しても同じ条件だった」「サブスクリプションの登録後、解約方法を不明瞭にして解約を困難とするもの」、相談例として「安価な費用で化粧品を購入したら、定期購入になっていて注文時にその表記はなかった」などが挙げられています。
 『その医療情報は本当か』(集英社新書)
『その医療情報は本当か』(集英社新書)田近亜蘭 著
消費者庁が毎年実施する「詐欺防止月間」の2023年のテーマは、「ダークパターン」でした。ウェブデザイン企業が同年11月に発表した調査結果では、799人(18~69歳)へのアンケートで「ダークパターンにひっかかったことがある人は46.1%」「ダークパターンに関する知識をもっている人ほどダークパターンに気づきやすい」「ダークパターンは認知バイアスを利用し、消費者を巧妙にだますように仕組まれている」などの報告をしています。
数字の読み取りかたをはじめとする情報の適切な解釈や判断は、医療や健康の分野にかかわらず、政治、経済、社会とあらゆるニュースに、そして日常の消費生活に大きく影響します。ウェブサイトやアプリの情報で、「この商品は安い、超お得!」と直感した場合、その印象は事業者によって操作されているのかもしれません。
意思決定をする際には、思い込み、大げさな数字に振り回されることがないよう、こうした現実を念頭に置きたいものです。