「できごと→感じたこと」の順で質問すると
回答の解像度がグッと上がる
もしも、あなたが「電話をとるときです」と答えたとしたなら、私はさらに次のような質問をします。
すると、「そういえば、会社名を相手に1回で聞きとってもらえなくて困っている」といったように、かなり解像度の高い言葉で答えやすくなるでしょう。
このほうが会社名への思いや意見をいきなりストレートに聞かれるよりも、ずっと言語化しやすいはずです。
このように、人は具体的な「できごと」はわりと簡単に言語化できますが、少し抽象的な思いや意見、つまり「感じたこと」はなかなか言語化できません。いきなり「感じたこと」を聞かれると、人は戸惑ってしまうのです。
ですが、少し工夫して、話を聞く順番を「できごと→(そのできごとで)感じたこと」に変えるだけで、一気に答えやすくなります。
まさに、この「できごと→感じたこと」の順番で問いかけていくことが、言語化につながる聞き方のコツなのです。
さきほどの会社名のネーミングの事例も、まったく同じです。
社長の場合は、以前働いていた会社の名前が長くて、頭文字をとって省略して使っていたという「できごと」がありました。
無意識のうちに、長い会社名をわずらわしいと感じていたのでしょう。
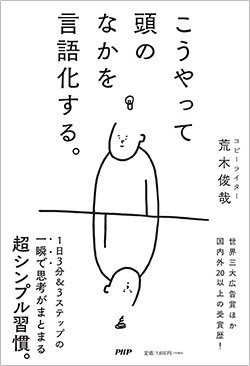 『こうやって頭のなかを言語化する。』(PHP研究所)
『こうやって頭のなかを言語化する。』(PHP研究所)荒木俊哉 著
だからこそ、「今回は短くて言いやすいものにしたい」という思いが、コピーライターの問いかけをきっかけに言語化されていきました。
さらに、「はじめてのお客さんに会社名の由来を聞かれた」というもう1つの「できごと」を思い出し、「今回は会社や事業への思いが説明しやすい会社名にしたい」という思いも言語化することができました。
このように、まずは、過去の印象的な「できごと」を、できるだけ具体的に思い出してもらえるような問いかけをする。
そのうえで、その「できごと」のなかで、どんな気持ちや感情になったのか、つまり「感じたこと」を思い出してもらう。
この順番で相手に問いかけていくことが、思いや意見を言語化しやすい聞き方のコツになります。







