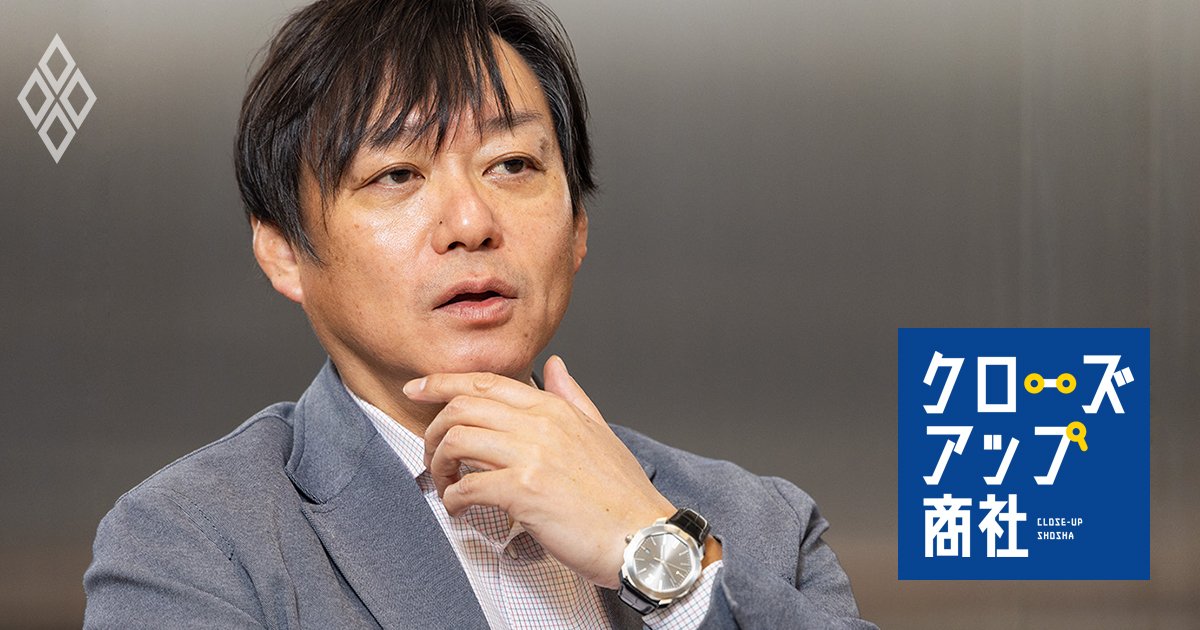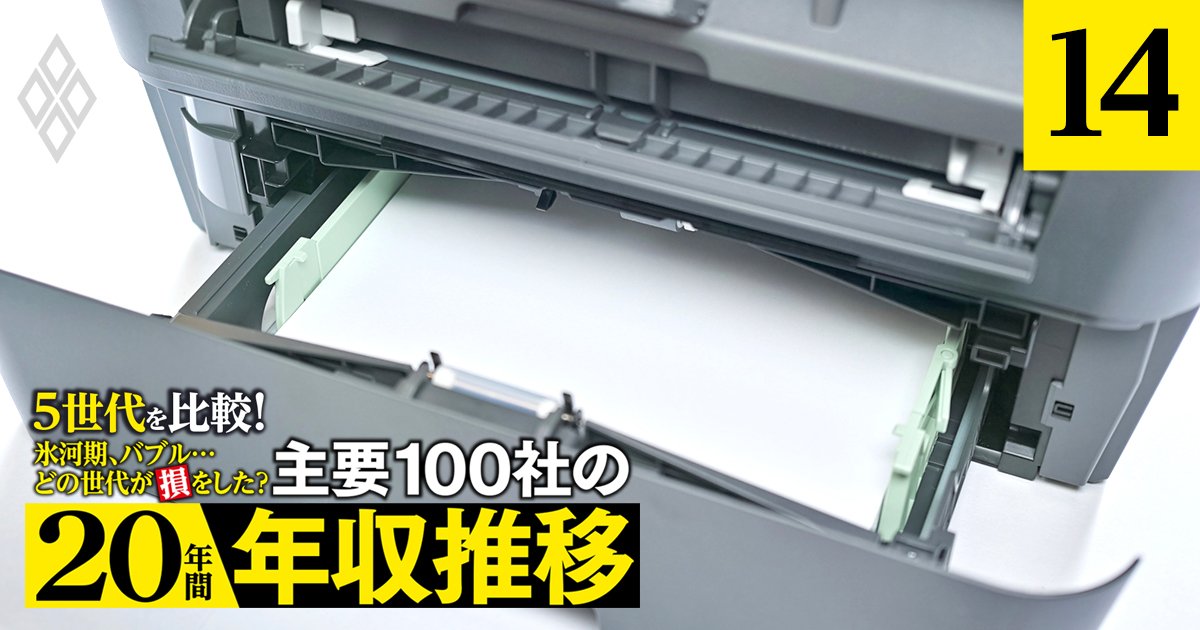――どうやってアレンジしていけば、いいのでしょうか?
塾の授業についていけない、どこが分からないのかも分からない子は、まず、国語力を鍛えましょう。どの教科も根本的に分かっていない子は、国語でつまずいている場合が多いからです。
先生が言っていることが理解できない、教科書に書いてあることが分からない、何を問われているのかも分からない、といった子は、中学受験層にも結構います。親が気づいていないだけです。
そういった最低限がきちんとできるようになると、ようやくどの教科も伸びる可能性が出てきます。つまり、国語のテストで点数を取るための国語ではなく、それより手前の国語力が大切。それを身につけるには、子どもが主体的に意見を言って、大人がきちんと対話することが必要です。これは、10人以下の授業ではできても、大人数の授業では難しくなります。
――アレンジ受験勉強にデメリットはないのですか?
一つの塾で全ての教科を完結するのに比べると、お金がかかることはあるでしょう。非効率に感じることもあるかもしれません。
けれど、1教科だけでも学び方を変えるだけで子どもが楽になったり、伸びたりすることはあります。今通っている塾の好きな教科だけに絞って、他の教科は違う学びの場でフォローを入れる方法もあります。
先に述べたのはごく一例で、アレンジした結果、志望校に合格できた例はたくさんあります。アレンジする人の力量も必要ですね。子どもの状態を見通すことができて、かつ4教科の全体像が見える人でないと難しいでしょう。個別教科の専門的な知識ではなく、プロデューサー的な立場でモノを言える人ですね。
――アレンジ受験に振り切るのに、どうしても勇気がいる、という場合は?
無理にやる必要はありません。けれど、親も子も違和感があるのに、目をつぶって思考停止してしまうのが問題だと思います。中学受験で親が持つべき視点は、「みんなと同じことをやるのが、良いというわけではない」ということです。
塾のカリキュラムを追うことにこだわらず、「わが子に合った学び方」を選び、志望校の過去問を自力で解けるようにする。この視点を持てば、塾に振り回されず、子ども自身が成長を感じながら理想的な進学へ導くことができるのではないでしょうか。
 現代のリベラルアーツ教育の大切さを語った矢萩邦彦さんの『正解のない教室』(朝日新聞出版)が好評発売中です
現代のリベラルアーツ教育の大切さを語った矢萩邦彦さんの『正解のない教室』(朝日新聞出版)が好評発売中です