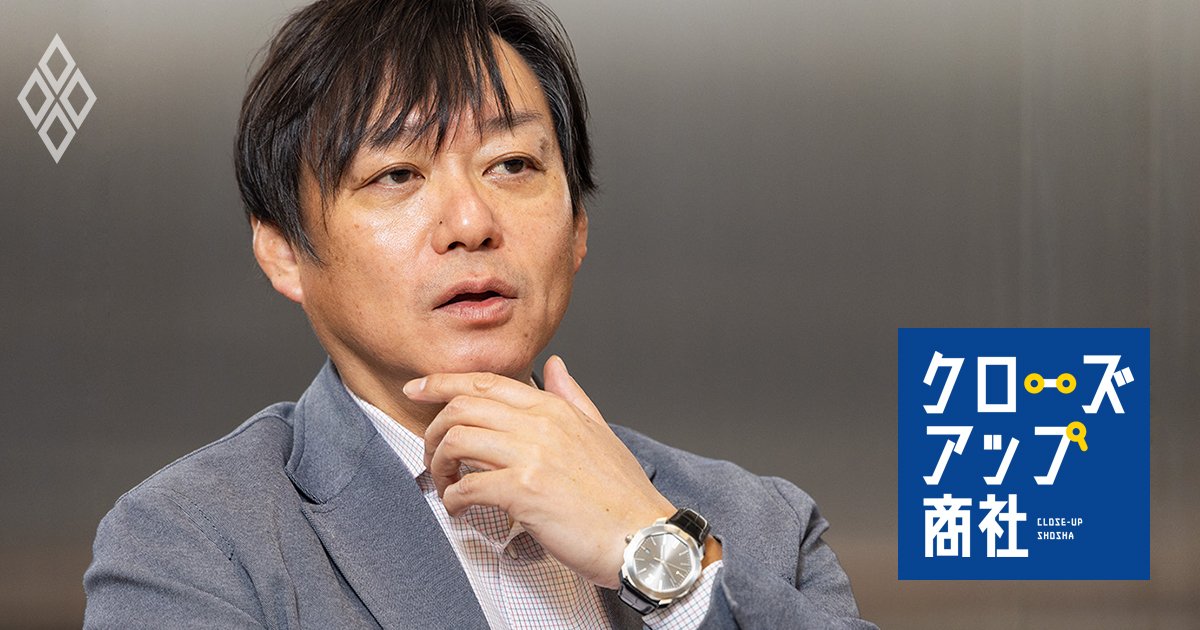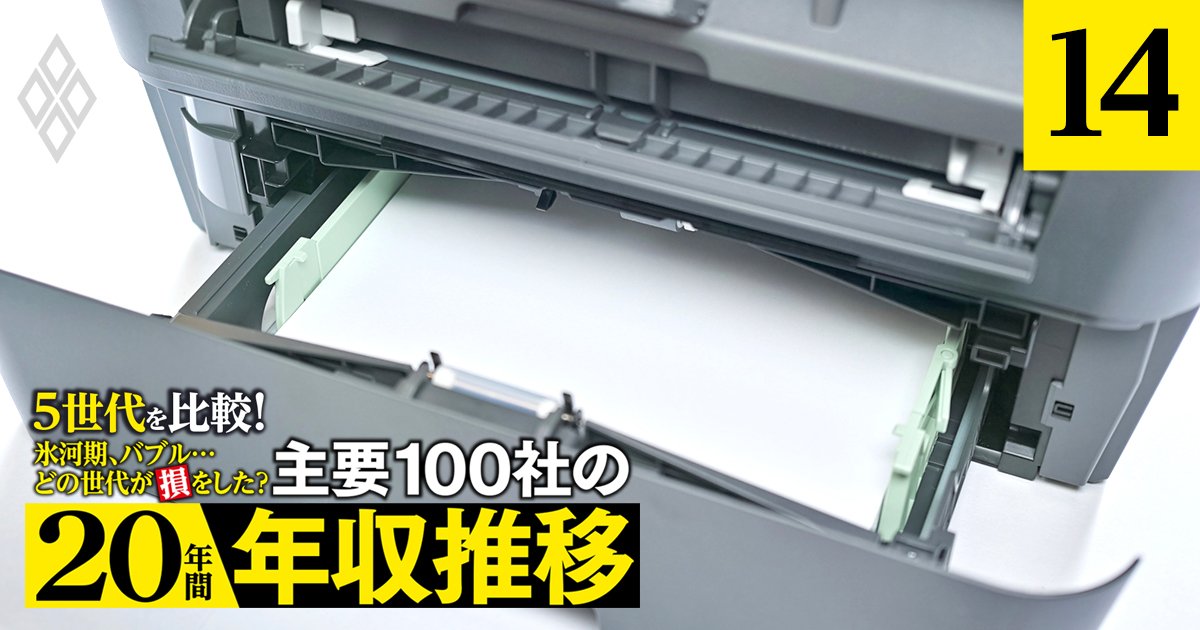集団塾のカリキュラムについていけない場合、個別指導に通わせる、家庭教師をつけるご家庭が多いと思います。しかし、そうやって補習を入れたとしても、そもそも塾での学びと本人の能力が噛み合っていないから、子どもは全く楽しくない。でも、親としては塾をやめるのは不安だから、なんとかカリキュラムに乗せようとする。それって焦点がずれていて、下手すると教育虐待にもなると思うんです。
家庭教師や個別指導を否定しているわけではありません。が、塾についていくことを念頭にするのではなく、その子が伸びるために何をすべきかを真ん中に据えて、地頭や基礎学力をつける学びを考えるべきです。
例えばですが、学びの形態を「探究型」に振り切って楽しく学んで伸ばしていく方が、よっぽど成績が上がるケースもあります。子どもってゲームに夢中になりますよね?それは、クリアするとかレベルアップしている感覚があるから楽しいんです。
それと全く同じで、本人が成長を感じられる「小さな成功体験」を積み重ねると、どんなレベルの子でも学ぶことが楽しいと思えるようになるんです。
――実際にうまくいったケースがあるのですか?
4年生の終わりに、探究的な学びをしたい、とうちの塾に相談に来た女子がいました。国語と算数でスタートしましたが、とにかく算数が全然分からない。そこで5年生の頭に算数をやめ、国語だけをしっかりやっていきました。6年生になると、本人が絶対行きたいと思える志望校ができて、それには最低、国語と算数の2教科をしっかり勉強する必要がありました。だったら算数をもう一度頑張ってみようと本人もやる気になり、算数を巻き返して勉強し、無事に志望校に合格できました。
このケースでは、国語の勉強を続けていたので、国語力は上がっていたことが功を奏しました。そして明確な志望校ができたことで、本人の主体性も出てきて、1年弱で算数も間に合ったのです。
こういうやり方は、大手塾では難しいでしょう。子どもは教科ごとの得意・苦手もあるし、時期によって成長曲線も違うわけです。
他には、算数だけ近所の塾に通って、残りの教科をうちの塾で学んでいたケースもあります。算数は苦手なので授業数を増やしたいという希望で、算数だけ切り離し、他の教科は探究的な学びを通して知識を蓄えました。6年生の秋から過去問中心の学びにシフトし、人気の中堅私立中に合格しました。
国語だけうちの塾に通って最難関といわれる中学に合格した子もいます。知識量をあまり問われない学校であれば、大手塾のカリキュラムに乗らなくても合格は可能です。
――子どもに合わせてきめ細かくカスタマイズするわけですね。
「塾のカリキュラムについていける」=「志望校に合格できる」ではありません。どんな方法で学ぶにせよ、最終的に志望校の過去問を解けるレベルに到達できるかどうかが大事。その目標設定さえぶれなければ、途中の模擬テストだとか週テストは無視して、最後の最後に追いつくようにアレンジする受験勉強は、大いに有効だと思います。