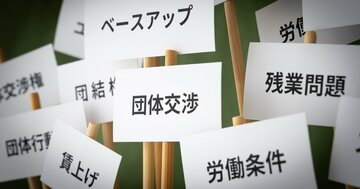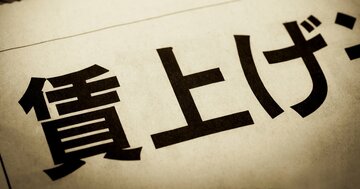金融緩和政策が大失敗
企業をぬるま湯につけた
なぜ日本の生産性が低下し、自然利子率が低下したのだろうか?その原因としてはさまざまなことが考えられる。1980年代からの世界的経済構造の大きな変化に対して、日本経済が適切に対応できなかったということもある。
それだけでなく、金融緩和政策の影響も無視できない。
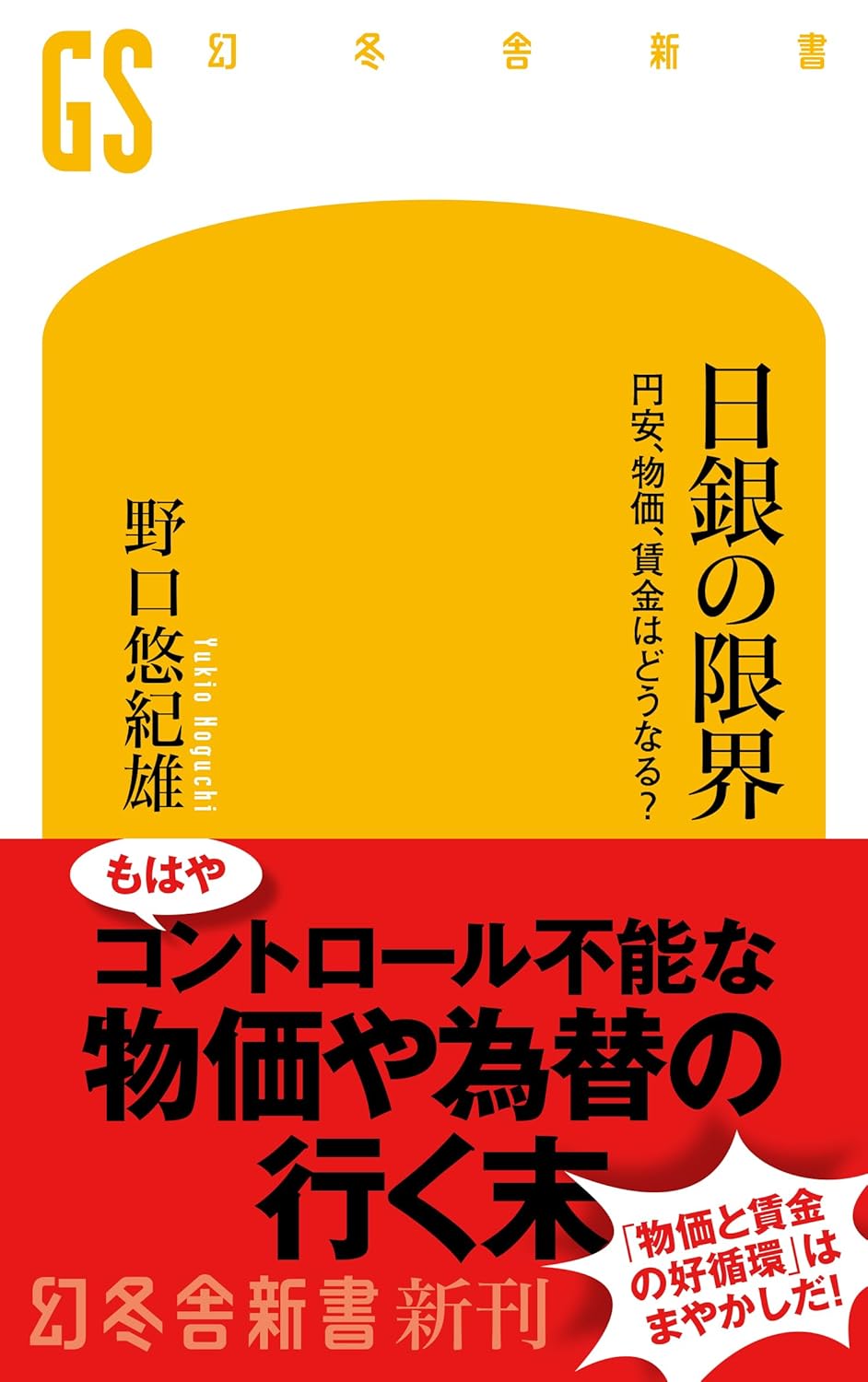 『日銀の限界 円安、物価、賃金はどうなる?』(野口悠紀雄、幻冬舎新書)
『日銀の限界 円安、物価、賃金はどうなる?』(野口悠紀雄、幻冬舎新書)
つまり、金融緩和政策が日本企業をぬるま湯につけてしまったために、企業が生産性を引き上げる努力をせず、その結果、生産性の高い投資ができなくなった可能性がある。
これは、金融緩和政策が長期的な経済成長の阻害要因になったことを示すものだ。
アメリカでは、ITやAIなどの分野でさまざまな技術革新が行なわれる。だから、潜在成長率が高くなり、自然利子率も高くなる。したがって、金利を上げることができ、その結果、ドル高になる。
他方、日本経済は生産性が低いので、自然利子率も低くなり、したがって、金利を上げることができず、その結果、円安になる。このため、消費者がますます貧しくなる。
このようなプロセスが行き着く先は、キャピタルフライト(編集部注/資本市場などから資金が逃避すること)だ。日本から資金が逃避するため、国内での資金調達が難しくなり、金利が高騰する。金利が高騰しても、円高になるのでなく、円安が進む。
日本はまだその段階に至っていないが、いつまでもそれを免れられるという保証はない。キャピタルフライトに陥らないための方策を真剣に考える必要がある。