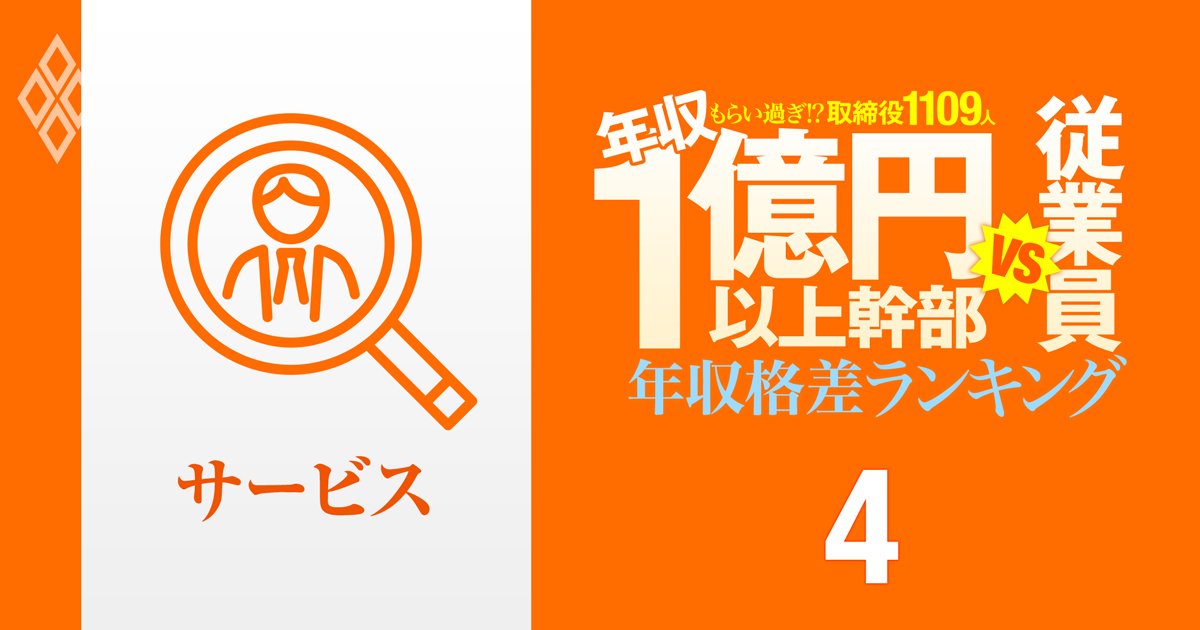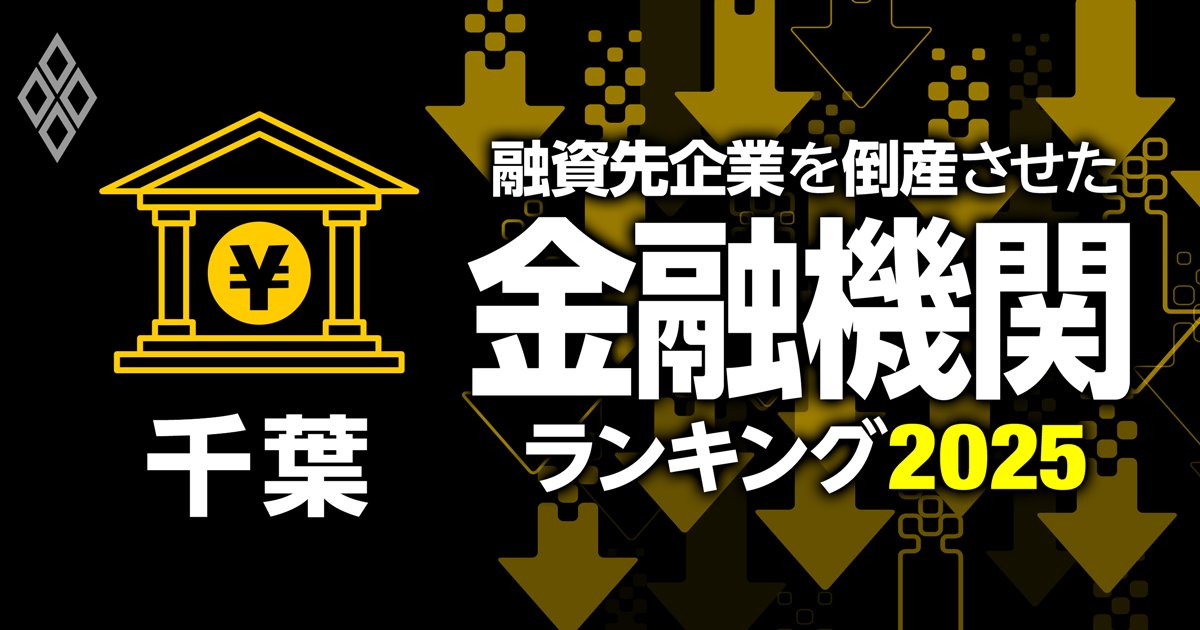筆者は、B9 e-4ORCE limitedを1200kmロードテストしたことがある。日産がクルマを通じてユーザーにどういうエクスペリエンス、ライフスタイルを提供したいのか、明快かつ的確に表現されたモデルという印象を持った。
外装は仰々しいメッキ加飾がほとんどなく、車体の造形そのものでマッシブさを上手く表現したもの。内装は高級素材を使っているわけではないが、落ち着いた色調と圧迫感の少ない造形、そして光の差し込みが浮かび上がらせる陰影が和モダン的な空気感を体現していた。
BEVユーザーが懸念する充電の受け入れも優れていて、高性能充電器で30分充電の投入電力量は、実に50kWh(走行距離350km分に相当)に達した。超急速充電網を持つテスラを例外とすれば、最高クラスの数値である。
日産はこのアリアを、新生日産のアイコンにしようとしていたのだろう。軽自動車BEVの「サクラ」やハイブリッドカーの「ノートオーラ」に、アリアのデザインエレメントを移植したことからもその意図がうかがえる。
マジョリティユーザーの信任を得るに至っていないBEVアリアをアイコンにするには、デザインを良くするだけでは不十分だ。その存在意義を高めるため日産の開発陣は、やれる限りのことをやったのだろう。初期の注目度の高さやノートオーラ、サクラの成功はその果実と言える。
ところが、である。日産はこのアリアでまさかの大失敗をした。
生産が上手くいかず、受注開始から1カ月後には受注を停止。24年3月の再開まで実に2年半以上ものブランクを作ってしまったのだ。
BEV技術は発展途上なだけに進化も急激で、この間、世界の自動車メーカーが強力な競合モデルを続々投入。21年段階では先進的だったアリアは、ライバル車に埋没し、受注再開後も以前の勢いを取り戻すことはできなかった。
果たしてアリアは、もはや選ぶ価値の希薄なモデルになってしまったのか…。筆者はもう一度長距離ロードテストを行ってみた。