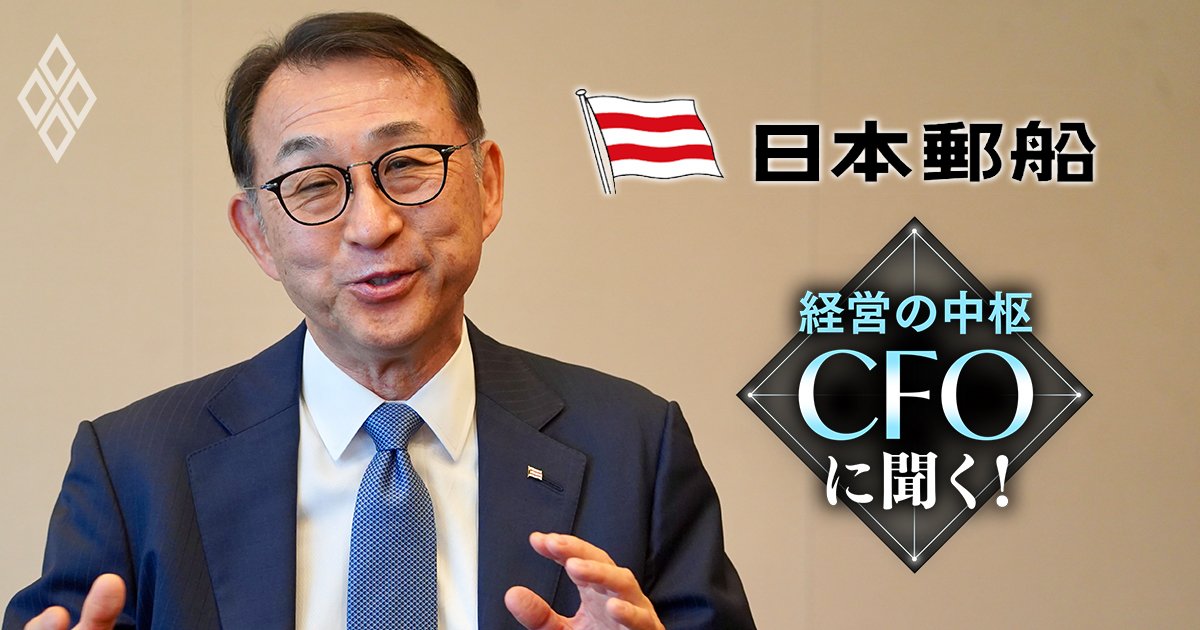お膳立てがないと動かないのは
実は上の世代も同じ
ただ、多くの上の世代はこのことに無自覚です。自分たちが「何も考えずに従っていただけ」だったことに気づかず(あるいはそれを忘れ)、「自分たちの時代は人に教えられなくても自力で道を切り拓いた」と錯覚している人が多いのです。
実際には、選択肢が少なかったからこそ、迷わず前に進めたという側面もあるでしょう。
これに対して、現代では、多様性やリベラル、フェアという考え方が根付き、「こういう生き方も、ああいう生き方もあり」という社会になりました。そんな中で若者たちは自分の行動の意味や意義を見出さなくてはなりません。
そうなると、「四の五の言わずにやれ」「石の上にも三年」というアプローチは通用しません。昔の若手が「言われたことをやってさえいれば、必ず未来が拓ける」と信じられたのに対し、今の若手は「これをやっても将来いいことがあるという保証はない。自分にどんなメリットがあるのか見えないと動けない」と感じているからです。
キャリアパスに関しても、今の若者は「会社員」以外にも、「起業する」「フリーランスになる」「海外で働く」「複業する」など、無数のレールの前に立たされ選択を迫られています。「この道で本当に良いのか」と常に自問自答しているので、仕事を与えられた場合に、丁寧な説明を求めるのはしごく当然のことと言えるでしょう。
そして、若者の納得コストが高いからというばかりでなく、仕事にはそもそも説明が必要なものです。というのは、人の成長において重要な概念に「7・2・1の法則」(ロミンガーの法則)があります。成長の7割を実際の経験から、2割を上司や他者からのアドバイスから、1割を外部研修から得るというものです。
しかし、経験だけでは、その経験が何につながるのか意味を見つけるのは難しい。人間は「意味を見出す生き物」ですが、経験の意味は往々にして後になって解釈されるものです。キャリア研究でも「キャリアは後付け」「キャリアは解釈」と言われることがあります。
これは心理学では「コンステレーション(星座)」にたとえられます。個々の星は別々に存在していますが、ある複数の星の並びがあるとき、「さそり座に見える」というふうに見出される形で、初めて星座として認識されるようになります。