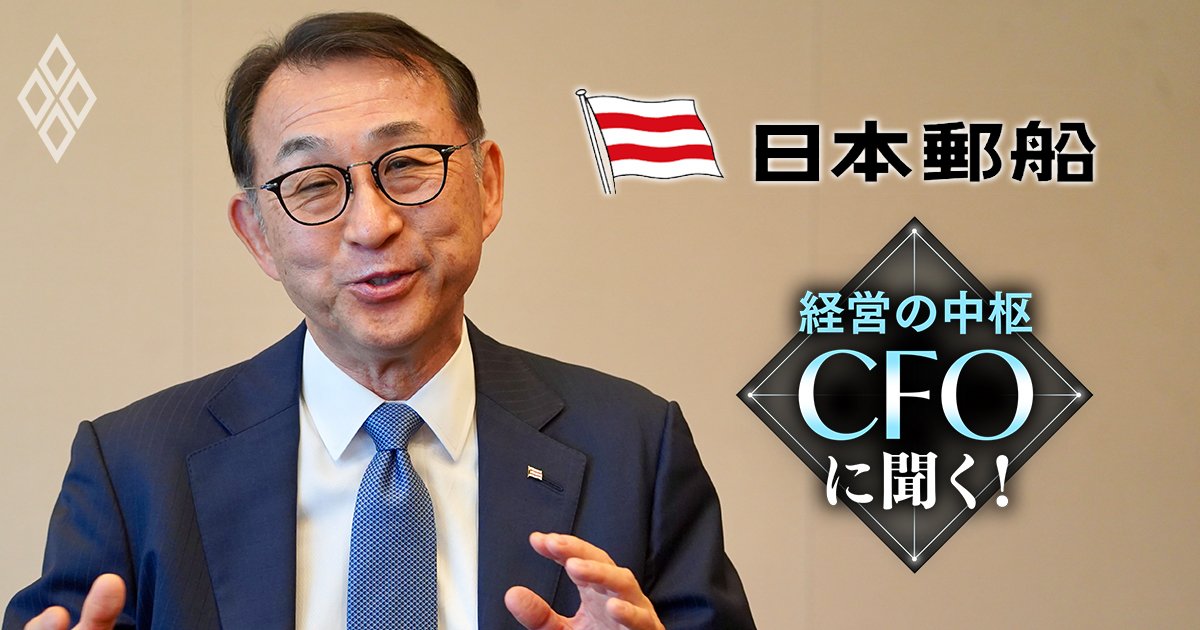キャリアも同様に、時間を経て個別の経験である点と点が繋がり、「この経験があったから今の自分がある」と解釈できるようになるものです(故スティーブ・ジョブズがスタンフォード大学の卒業式で行った有名なスピーチの一節、「点と点をつなぐ」を思い出してもいいでしょう)。
新人たちの納得コストが高いのは、この「意味づけ」の能力がまだ発達していないからとも言えます。
離職防止の解決法1
「経験のデザイン」
こうした現実を踏まえたうえで、私は離職防止の手立ては2つあると考えています。
1つ目は、若手の期待に言行一致で応え、成長を感じられる経験を意図的に作り出してあげることです。私が「経験のデザイン」と呼んでいるもので、その人が経験すべきことを計画的に割り当てるのです。
前述のとおり、人は成長の7割を実際の経験から得ますが、特に成長が著しいのは「修羅場経験」のように、既存のスキルでは太刀打ちできない難しい課題に挑戦し、それを克服したときです。
そして、そのような経験で得られるのが「自己効力感」です。これは自己肯定感とは異なります。自己肯定感が「自分はこのままでOK」という現状維持の感覚なのに対し、自己効力感は経験のない事柄に対しても「私はできると思う(I think I can)」という感覚を持てること、つまり、未知のものに挑戦できる力なのです。
なお、自己効力感は医療の世界でも重要視されており、禁煙、がん治療や透析、ダイエットなどの「継続すること」に影響しますし、教育においても自己効力感の高い学生ほど志望校への合格率が高いことが知られています。
ポイントは、その人の現在のスキルより「ちょっと背伸び(ストレッチ)した目標」を設定することです。
今できることをさせるだけでは本人は成長したという実感を持てません。かといって、難しすぎる課題では挫折してしまいます。
適度な難易度の仕事を割り当てることで、本人は試行錯誤しながらそれを成し遂げ、達成感を味わい、かつその成功体験が未知のことに対しても、「やれそうな気がする」という自己効力感を養うのです。