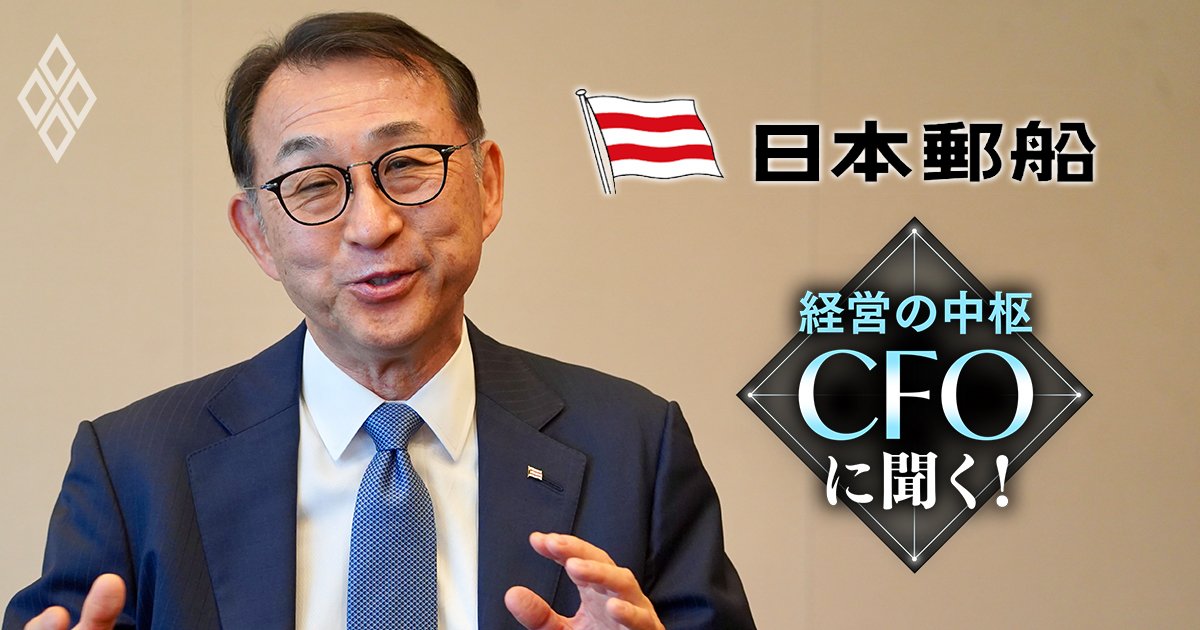 Photo by Yuito Tanaka
Photo by Yuito Tanaka
未曽有の「海運バブル」で2022年3月期に純利益1兆円を達成した日本郵船。その後も、高止まりする海運市況を背景に好調が続いていたが、米トランプ大統領の関税政策により、波乱が起きることは必至だ。不透明な地政学リスクの中でどのような進路を描くのか。長期連載『経営の中枢 CFOに聞く!』の本稿では、日本郵船副社長執行役員チーフ・フィナンシャル・オフィサー(CFO:最高財務責任者)の河野晃氏に、地政学リスクが高まる中での同社の成長戦略を聞いた。(ダイヤモンド編集部 田中唯翔)
トランプ関税で先行き不透明に
「一寸先は闇」の海運業界
――コンテナ船運賃の高騰で、純利益1兆円を計上した「海運バブル」を終え、日本郵船を取り巻く環境はどう変化しましたか。
新型コロナウイルス禍明けの2023年3月期以降は海運市況が正常化しましたが、ほぼ全ての船種(船舶の種類)において運賃は比較的高水準が維持されてきました。主な要因は地政学リスクです。
23年11月ごろから、スエズ運河を通航する船に対し、イエメンのフーシ派の攻撃が起きています。それにより船会社がスエズ運河を回避し、喜望峰を通るルートを取りました。航行日数が増えたことで船腹の供給が制約を受け、運賃水準が維持されました。
一時はイスラエルとイスラム組織ハマスとの間で和平が合意され、フーシ派も攻撃を中止する見立ても出ていましたが、現在もなお中東情勢は混沌(こんとん)としており、いつまで続くのか予測し難いです。
われわれの見解では、今また中東情勢が不安定になっているので、全ての船にスエズ運河を通航させるのは難しいと考えています。
――25年内に紅海を航行できるようになれば、運賃は下落するでしょうか。
昨年も当初は24年9月ごろには通過できるようになるとの見立てでしたが、結果的に通行できていません。以前に比べ、非常に地政学リスクが読みづらくなっています。米国でトランプ政権が発足し、ウクライナや中東では従来とは違うアプローチで和平を目指す動きが起きています。ただそれが奏功するとは限りません。
――24年7月をピークに、コンテナ船の運賃は下落しています。25年3月期の業績への影響は。
25年3月期第3四半期決算までは、運賃下落を踏まえても前年同期比で非常に好調な結果でした。2月5日には25年3月期通期の経常利益予想を従来の700億円上回る4800億円に上方修正しました。第4四半期については現在集計中ですが、予想したレベルの水準からは大きく外れないと思います。
――中期経営計画では27年3月期に2700億円の経常利益を目標に掲げています。
中計の目標を達成できるように事業を進めるつもりですが、ここに来てトランプ関税が出てきたので、先を見通すのがさらに難しくなっています。株価も変動していますし、それぞれのセクターの荷動きへの影響を現在精査している段階です。
事業環境の激変にさらされやすい海運業界は、米トランプ大統領の関税政策でさらに先行き不透明な状態になることが予想される。こうした荒波を日本郵船はどのように乗り越えていくのか。次ページで、河野晃CFO(最高財務責任者)が、トランプ関税の影響は日本郵船にとってはそこまでネガティブではないと明かす。その理由とは。またCFOとして注視しているKPIのほか、積極的に活用するとしているM&A(企業の合併・買収)戦略の方向性についても解説する。







