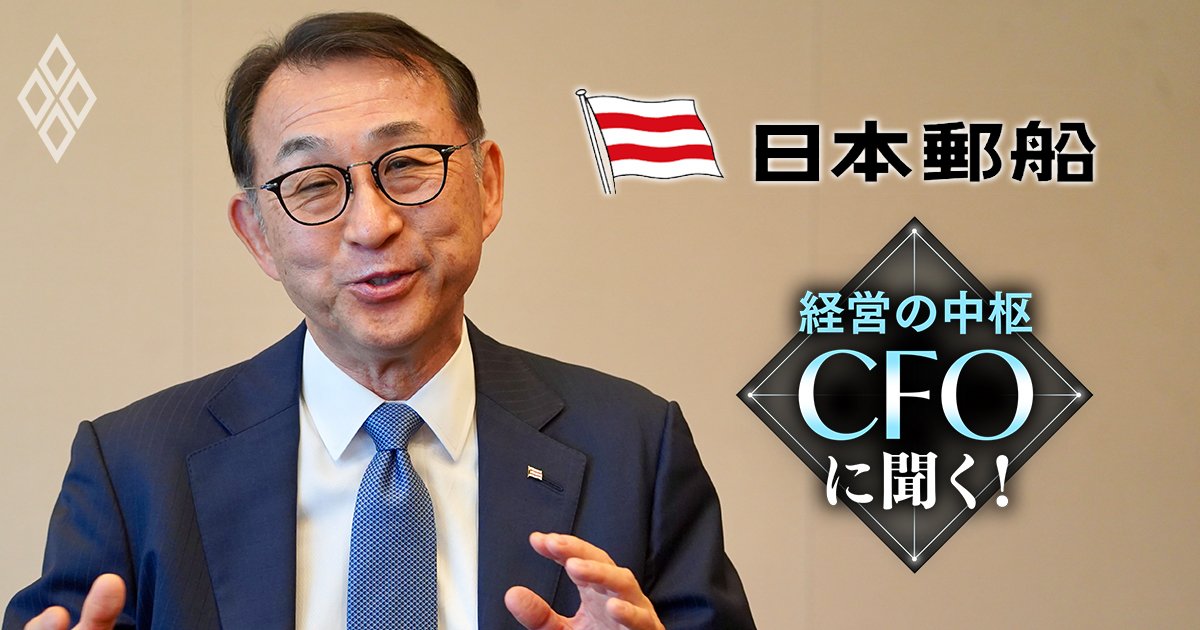ことの発端は、ChatGPT 4oによるジブリ化画像が人気となる中で、Xで「画像のジブリ化に特化したアプリを発表する」と投稿した人が、後日、「ジブリからの警告文が届いた」という画像付きの投稿を行ったことだった。その警告文には、「こうした事業を取りやめなければ法的手段をとる」旨が記されていたという。しかし、NHKが直接ジブリに確認したところ「弊社としては、警告文を出した事実はありません」との回答が返され、そのような事実はないと判明したのである(記事:AI生成の偽画像 投稿相次ぐ中 ジブリの偽の警告文書が拡散)。
筆者は、生成AIが一般化し始めた頃から、著作権との関わりについて調べたり、記事を執筆したりしてきたので、「作風や作画スタイルには著作権が発生しない」ことは承知していた。また、明らかに特定のキャラクターだとわかるイメージを生成した場合、それを公開・配布・販売すれば著作権侵害となるが、そのようなイメージであっても「私的利用の範囲内で使う限りは罪に問われない」ということも理解している。これは、かつてエアチェックや市販の音楽テープから楽曲を録音・ダビングしてミックステープを作り、個人で楽しむことが許されていたことと同様の扱いだ。実際に、文化庁のAIによる生成物と著作権に関する見解も、そのような考え方に基づいている。
具体的には、自分だけで鑑賞・利用する、家庭内で家族と共有する、ごく親しい少人数の友人との間で利用するといったことが私的利用に含まれる。逆に、不特定多数への公開、譲渡、貸与、公衆送信(SNS投稿など)は、私的利用とみなされない。
したがって、意図的に既存のジブリのキャラクターと同一、あるいは酷似したイメージを生成して公開や販売を行わない限り、ジブリ風の画像生成自体は問題ないことになる(AI画像生成サービスを提供する側が学習に利用したデータが適切なものだったか、そして、ジブリ風のイメージが蔓延することでオリジナルのジブリのコンテンツの価値が損なわれないかは、また別の話ではあるが……)。
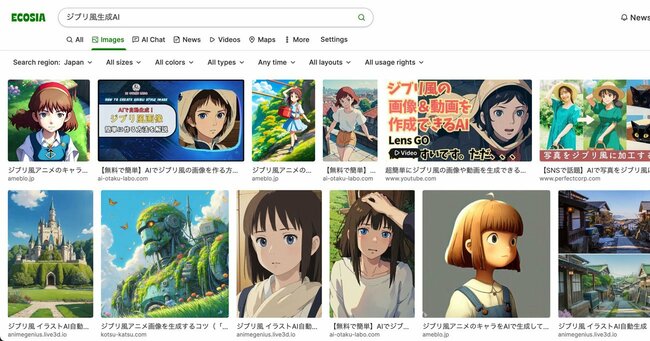 ちょっと検索するだけで、ジブリ風に加工されたAI画像や、そのやり方を示した記事が無数に出てくる(筆者がキャプチャしたもの)
ちょっと検索するだけで、ジブリ風に加工されたAI画像や、そのやり方を示した記事が無数に出てくる(筆者がキャプチャしたもの)
ジブリ側が利用者に対して特にアクションを起こさないのも、そのことをよく理解していてのことと思われる。また、スター・ウォーズのように、ファンメイドのコンテンツを大目に見ることによってファンのコミュニティやエコシステムが強化されている例もある。こうした事情で、少なくとも今のところは静観しているともいえるだろう。