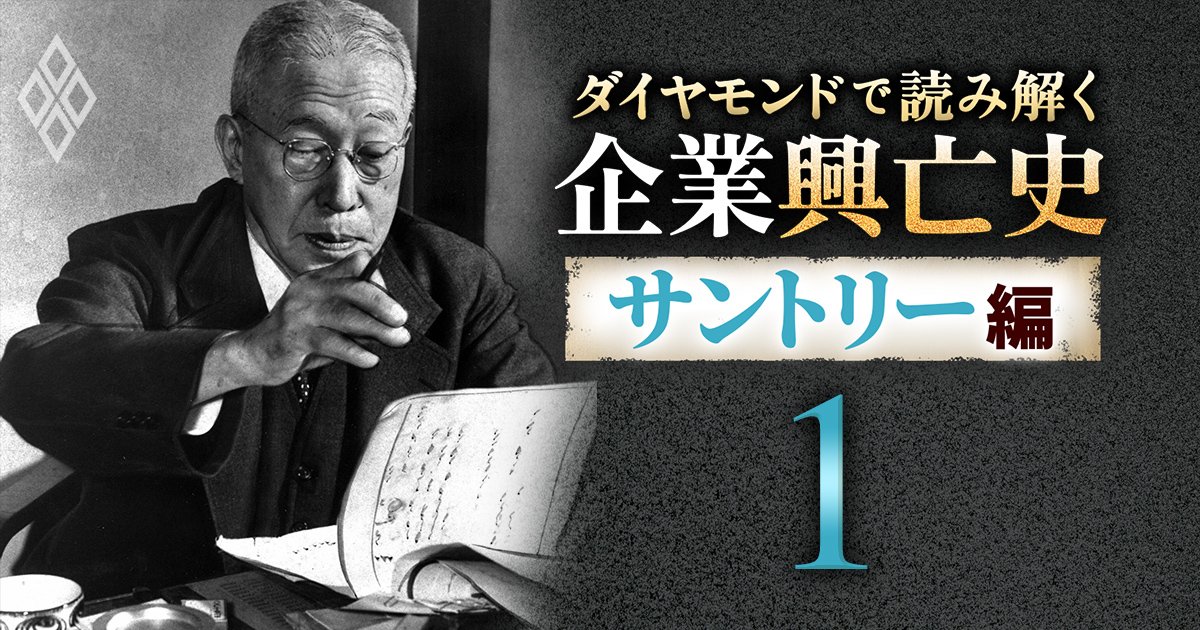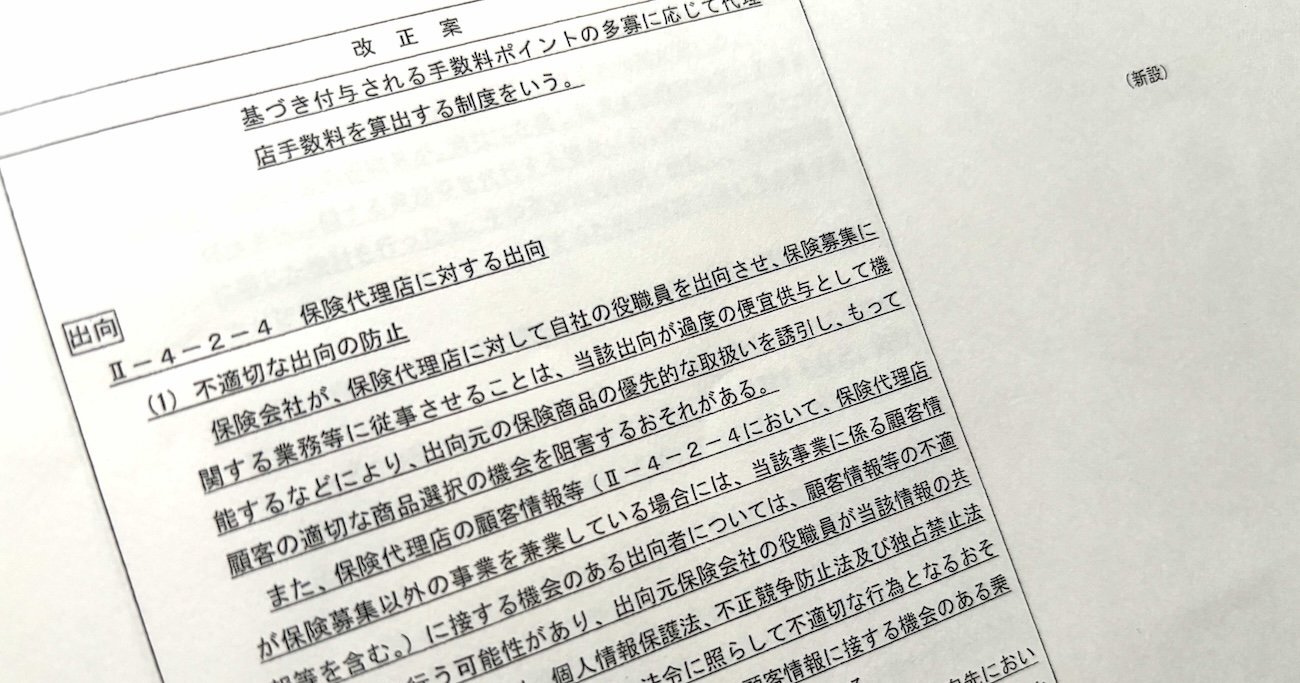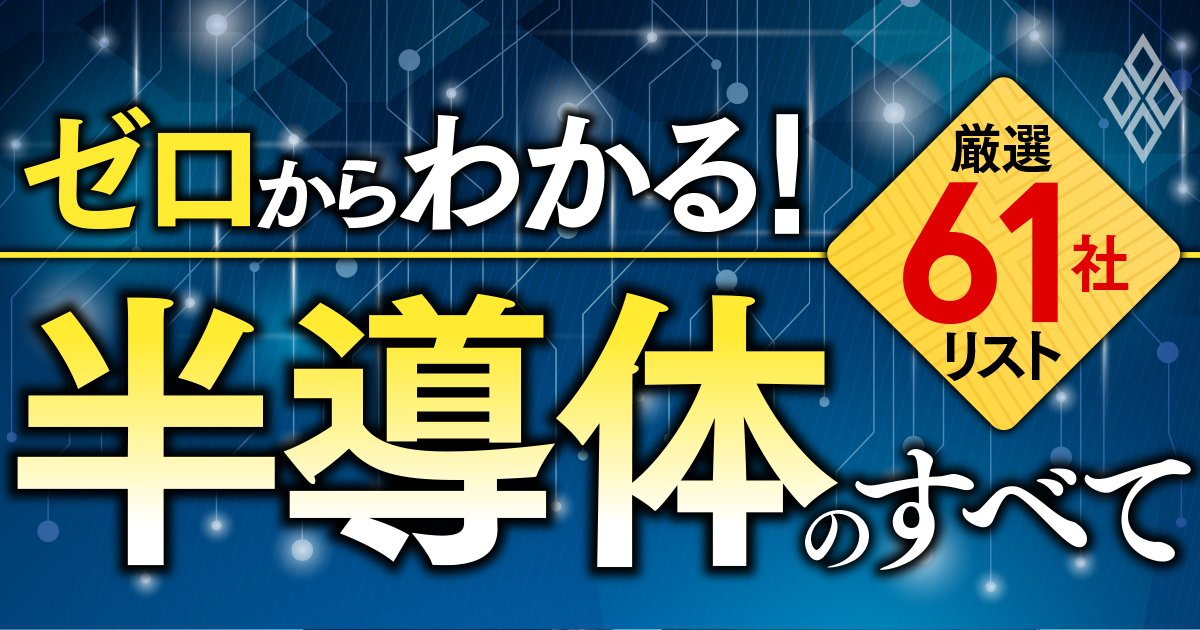リッツ・カールトンの驚くべき「過剰サービス」
高級ホテルチェーンとして知られるリッツ・カールトンでは、従業員が1人あたり1日2000ドルまでの裁量予算を持っており、顧客のために自由に使うことが許されている。
忘れ物を自宅に郵送する、誕生日のケーキを部屋に届ける、雨で濡れた靴を乾かして届ける、といった対応が、現場の判断で即座に実行される。
リッツ・カールトンのサービス哲学には「紳士淑女をおもてなしする、紳士淑女であれ」という格言があり、顧客満足を組織文化の核に据えている。徹底された個別対応と先回りした気配りが、期待を超える体験となり、世界中の顧客に記憶されている。
コメダの戦略は、まさにリッツ・カールトンの流儀に酷似している。高級ホテルと名古屋発祥の大衆向けカフェという一見かけ離れた業態であるにもかかわらず、共通しているのは「顧客が求めているものを事前に察知し、それ以上のものを与える」という姿勢である。
たとえば、喫茶店に入る前に人が思い描く「軽食」や「軽い休憩」という想像に対して、コメダはふかふかのソファと巨大なサンドイッチを差し出す。
体験のギャップが「意外性」「面白さ」「ワンダフル!」に転化し、やがて「信頼」となって定着していく。コメダが全国に1000店舗以上を展開し、海外進出まで果たすブランドに成長した背景には、こうした一貫した「過剰満足」の設計があるわけだ。
コメダは高級感やステータスを売りにしていない。おしゃれさや最先端性も掲げていない。売っているのは、くつろぎと満腹である。
一見シンプルな提供価値が、実は最も深く顧客心理に根差した戦略であり、長期的に見て競争優位となる構造であることを、経営理論も証明している。
リッツ・カールトンが5つ星ホテルで実践してきた過剰満足の思想が、大衆向けの喫茶業態に息づいている。価格を抑えながら満腹と幸福を提供しているコメダの姿は、まさに現代のマーケティング理論が体現された実例である。
もはやコメダはリッツ・カールトンそのものである。ラグジュアリーではなくボリュームで、ステータスではなく安心で、期待を超え、記憶に残る体験をつくっている。
パンに詰まったたまごの量が、リッツのコンシェルジュに勝るとも劣らない感動を生んでいる。現代のカフェ文化において、これは1つの到達点なのかもしれない