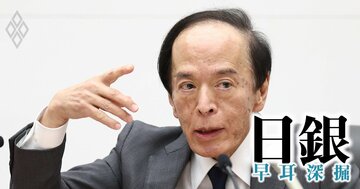Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
9月の日銀会合はETF(上場投資信託)売却決定と同時に0.75%利上げ案を退け、慎重姿勢を再確認した。デフレ期の「賃金が上がらない」ノルムから、企業ではインフレノルムが芽生えつつも、中小企業の賃上げ持続と家計のノルムの転換は確証を得られていない。トランプ関税の逆風で原資確保も難しくなっている中、次の利上げは2026年春闘の結果確認後が妥当だろう。政策金利1.0%に達するのは27年春闘前後が適切となろう。(SMBC日興証券 チーフ為替・外債ストラテジスト 野地 慎)
デフレノルムに陥った要因
賃金停滞と価格転嫁不全のスパイラル
日本銀行は9月19日の金融政策決定会合で、保有するETF(上場投資信託)の売却を決定した。
注目されたのは、高田、田村両審議委員が0.5%から0.75%への利上げを主張した点であり、ETF売却決定と同タイミングであったがために、一部市場参加者の間で臆測を呼んだが、ここで重要なのは、利上げ主張に対して、執行部を含む7人が「反対」した点である。
高田委員が「物価が上がらないノルムが転換し、物価安定の目標の実現が概ね達成された」と主張するなか、データなどにより、その確認を行うための時間が必要とするのがマジョリティーであったと換言できる。
ここで、改めて、インフレのノルムについて考えてみたい。
01年、日本政府は月例経済報告で初めて「緩やかなデフレ」を公式に認めたが、その01年(平成13年度)の内閣府「年次経済財政報告」においては、「デフレの要因は、(1)安い輸入品の増大などの供給面の構造要因、(2)景気の弱さからくる需要要因、(3)銀行の金融仲介機能低下による金融要因―の三つが挙げられる」とされている。
次ページでは、デフレのノルムについて振り返りつつ、インフレのノルムの検証と日本銀行の利上げのペースの予測をする。