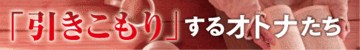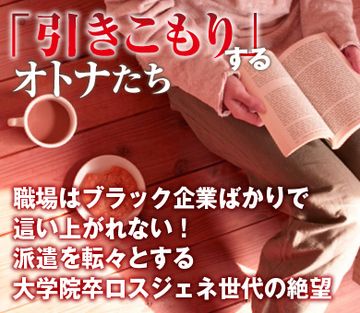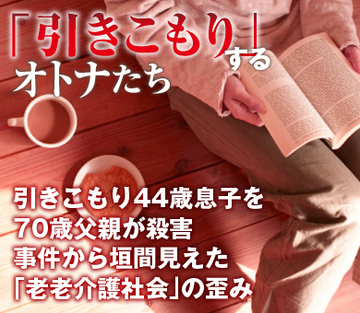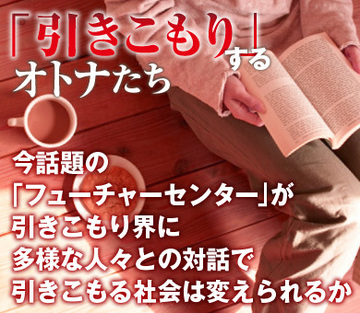2014年は、「引きこもり」たちにとって、どのような年になるのだろうか。
若い世代を中心に、お金を持たない、使わないという価値観が普通になった。右肩上がりの経済状況下での夢や目標を共同体の中で持つことのできた、そんな終身雇用時代への幻想は、もはやほとんどない。
世の中の構造が、少しずつ変化してきていることを実感する。
こういう先行きの見えない時代には、外から社会を傍観している当事者に寄り添い、思いを聞くと、たくさんの気づきを得ることができる。
昨日、「ひきこもり大学」を発案した当事者のMさんから、こう言われた。
「池上さんも、いつも一方的にコラムを発信しているけど、読者の引きこもりの人たちにも、記事へのリクエストを呼びかけてみてはどうですか? こういう情報を知りたいとか、こんなことを取材してほしいとか。双方向なんだから…」
なるほど、その通りだと思った。
ネットを通してつながり始めた
引きこもる当事者たち
当連載の下記のアドレスにも、毎日、メールは寄せられてくるが、中でも最近増えているのは、自宅に引きこもっている全国各地の人たちからの切実な思いだ。
外に出たい。でも、どこに行けばいいのかわからない。私の住む地域には何もない。行ってみたいけど人と関わるのは怖い。どうすれば自立できるのかがイメージできない。