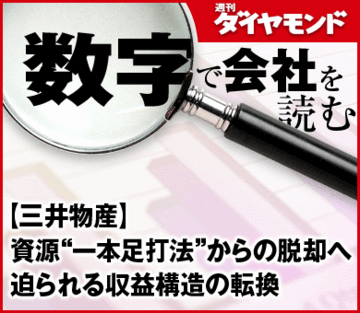鉄鉱石価格などが低迷し、「資源で稼ぐ時代は終わった」というのが商社のコンセンサスだ。だが、相変わらず三井物産は資源で稼ぐ。そのカラクリを解明する。
「資源で簡単にもうかる魔法なんてない。かつて鉄鉱石事業は赤字続きでさんざん批判されてきたが、それでも数十年かけて海外に販路を広げてきた。まさに涙と汗の歴史だ」と言うのは、三井物産の岡田譲治副社長兼CFOだ。
8月に公表された総合商社各社の2014年度第1四半期(14年4~6月)決算。純利益トップは三井物産の1278億円で、2位の三菱商事1100億円をはじめ、伊藤忠商事808億円、丸紅690億円を大きく引き離した。
その三井物産の稼ぎ頭は“資源”である。中身を見ると、エネルギー(原油・ガス)が567億円、金属資源(鉄鉱石・石炭)387億円で全体の75%を資源分野で稼いでいる。三菱商事の40%、伊藤忠の20%と比べても、大きく偏重している。
2000年代半ば、中国経済の急拡大に伴い鉄鉱石や石炭などの資源価格は高騰し、大手商社は資源バブルに沸いた。だが、それも11年をピークに下落の一途。そこで、三菱商事や伊藤忠などは、「これからは非資源で稼ぐ」と宣言し、方針転換を図っている。
そうした転換期にあって、三井物産だけが、なぜ今もって資源分野に傾注するのか。その解は、同社の鉄鉱石権益のコスト競争力の強さにある。
60年代取得の鉱山コストは低い
拡張案件に恩恵も
三井物産は、1965年にリオ・ティントとオーストラリア鉱山の権益を取得したのに始まり、67年にBHPビリトンのオーストラリア鉱山に参画した。今ではブラジルのヴァーレも加えた“鉄鉱石三大メジャー”の権益全てに絡んでいる。