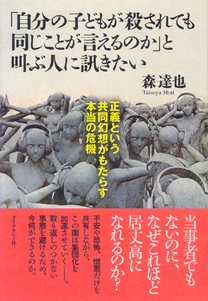読書は吾を救ふてくれた。
11月30日に93歳で他界した水木しげるさんは、1943年4月、美術学校への進学を目指して夜間中学で学んでいた頃に臨時召集の令状を受け取り、5月に出征した。
水木しげる+荒俣宏『戦争と読書』の副題は「水木しげる出征前手記」。水木がまだ20歳だった1942年10月から約1カ月にわたって綴った手記(+戦地などから送った書簡)に、水木の門弟を自認する荒俣宏が長い解説をつけた本である。
当時の水木は徴兵検査を受けた直後と推測される。〈それまでに形成してきた水木しげるのイメージが、一変しました〉と荒俣が書くように、本書から浮かび上がるのは、ひょうひょうとした自由人としての水木しげるではなく、他の青年と同じように悩み苦しむ20歳の武良茂(水木の本名)の哲学する姿である。
〈画家だろうと哲学者だろうと文学者だろうと労働者だろうと、土色一色にぬられて死場へ送られる時代だ。/人を一塊の土くれにする時代だ。/こんな所で自己にとどまるのは死よりつらい〉〈幸福とは将来を空想するにすぎぬ。生は苦だと言ふ事。明白に知る事が必要だ〉
新約聖書を読み、ニーチェに共感し、エッカーマンの『ゲーテとの対話』に心酔した水木。「生きて虜囚の辱めを受けず」という圧力の下、死への恐怖や不安すら口にできなかった異常な時代だ。それまで無縁だった死への恐怖がいよいよ現実となった若者たちは、切実な欲求から哲学書に向かったのだと荒俣はいう。
〈読書は吾を救ふてくれた。/世に文字なかりせば吾は今頃如何なるものとなつていたか。/思へば読書は恩人である。教師である。吾に於ては、正に唯一の教師であつた〉
平時の知識人の口から出たのだったら聞き流しそうなこんな言葉も、言論が封殺され、活字が払底していく時代の手記にしたためられた言葉だと思うと重みがちがう。哲学や教養は極限状態の人を救うのだ。水木さんは南方の戦線から生還したが、まるで20歳の遺書のよう。
※週刊朝日 2015年12月25日号