米国(15) サブカテゴリ
第37回
中央銀行の懸命の努力で、危機は短期金融市場内に封じ込められている。だが、それは取りも直さず納税者と政治家の見えないところで一触即発の危機が続いていることを意味する。

第50回
上海出張時に「上海書城」という大きな書店に行ってみた。以前の売れ筋本は、“株式投資ハウツー本”だったが、“世界経済の先行きを憂える本”へと変わっていた。

第24回
米大統領選の行方を左右するのはネガティブ広告の優劣だ。過去2回の中傷合戦は共和党の勝利に終わった。今回も民主党は押され気味。オバマ氏は主導権を取れないでいる。

第49回
野村や三菱UFJの動きを受けて、留飲を下げている日本人は多いことだろう。だが、金融ノウハウは、使いこなせなければ、宝の持ち腐れ。日本勢の逆襲が始まったと考えるのは早計だ。
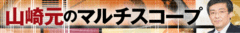
第47回
サブプライム惨禍が続く米国で、リーマンを破綻に追い込んでAIGを救済したポールソン財務長官の「手腕」に、にわかに注目が集まっている。緊急事態の収拾には成功したものの、「強い米国金融」に幕を引いた現実は重い。
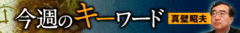
第199回
米国の「不良債権買取策」に重大懸念損失覚悟で売却する銀行はない?
金融不安解消の切り札として、米国政府が不動産担保ローン関連を中心とする不良債権を買い取ると発表した。しかし、安心はできない。金融機関の不良債権売却には、思わぬデメリットが多いからだ。

第45回
ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーはFRBの承認を得て、「銀行持ち株会社」に転換する方針を打ち出した。これにより、投資銀行業は、資本主義国の米国から消滅することになる。
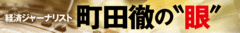
第10回
この1週間で状況は一変し、多くの米国民が「経済問題が大統領選挙の最大の焦点である」と認識するようになった。最大の責任は破綻した金融機関の経営者にある。次に事態を放置してきた行政当局の怠慢にあると思う。

第49回
拡大する米国の金融不安は、FRBを直撃している。担保受け入れにより資産の健全性が損なわれること、銀行部門の超過過条の発生がFF金利の低下を招くことなど、不安が山積しているのだ。

第48回
一部の専門家だけに許され、狭い世界にとどまっていた写真撮影を、イーストマンはこのような写真撮影のプロセスを簡略化し、誰にでも楽しめるものにした。
![ジョージ・イーストマン[コダック社創業者]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/4/240wm/img_9474db63807d3e88bd9144b17225e6b29984.jpg)
第34回
米政府の金融安定化策には3つの課題がある。不良債権の買取り対象と買取り価格の確定、そしてその結果生まれる債務超過組の救済だ。難易度は、1990年代の日本の金融危機の比ではない。

第39回
REIT(不動産投資信託)を取り巻く環境は一時的に好転したかに見える。しかし、高い利回りに騙されてはいけない。疑問符が付く総合経済対策の実効性や金融検査不況など、懸念材料は少なくない。

第33回
米国の大手証券会社リーマン・ブラザーズの破綻は、世界を震撼させた。巨額損失の連鎖が止まらず、パニックはどこまで広がるかわからない。日本の金融機関にとっても、決して「対岸の火事」ではないのだ。
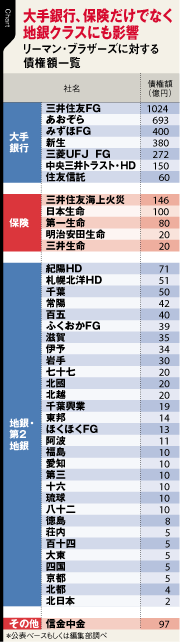
第32回
グルジア紛争を契機に、米ロ関係が急速に悪化している。だが、この角逐は今に始まったことではない。「米ロ新冷戦」は今後も続き、想像を絶する事件が何度も起こることになろう。
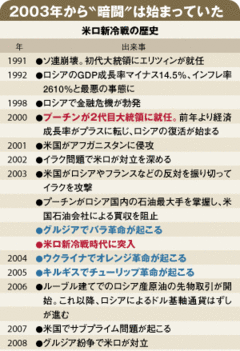
第44回
米国では9月14日を、大恐慌の幕開けとなった1929年の「ブラック・サーズデー」になぞらえて、「ブラック・サンデー」と呼び始めた。この危機は、どのようなメカニズムで引き起こされ、誰が責めを負うべき問題なのか。
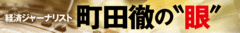
第46回
私が今回のリーマン破綻で強く感じたのは「国際倒産手続きの問題点」。経済はグローバル化しているにも関わらず、グローバル企業の倒産手続きは国ごとに行なわなければならないのが現状である。

第9回
大統領候補を決める共和党大会が9月1日から開催された。マケインは拳を振り上げて何度も何度もFight(戦おう)を連呼した。聴衆の99%は白人だった。マケインはこの演説で「Fight」を43回も言った。

第47回
リーマン・ブラザーズの経営破綻は、官民を挙げた大騒ぎの末に決まった。証券会社を一つ潰すのにこれほど苦労するとは、投資銀行のビジネスの在り方に問題があるのではないか。
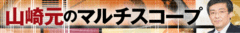
第44回
米金融当局の高いリテラシーへの期待の表れなのか、リーマン処理の決断を評価する声が日本のメディアで増え始めている。だが、その期待は裏切られる可能性もある。
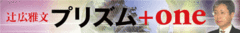
第13回
世に数多ある医療・健康情報サイトの中で、最も早いペースで成長しているのがウェブMDだ。グーグルに買収を仕掛けられたとも言われる同社の躍進の秘密を探った。
