米国(17) サブカテゴリ
第41回
株価下落や商品高騰に悩む米国では、金融市場における「規制強化」のトレンドが強まっている。しかしそれが長期化すれば、「暴力的な相場変調」さえ生み出しかねない危険がある。
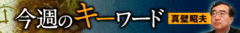
第2回
クリエイティブ産業の今後を考える上で、押さえておかねばならない現実がある。コンテンツは無料という時代の流れだ。ここでは特に重要な米国発の新しい議論を2つ紹介する。

第43回
「世界中で売れるコンピュータはおそらく5台程度にすぎない」。コンピュータの市場予測は間違えたものの、ワトソンはIBMを工業的にも技術的にも巨人に育て上げた。
![トーマス・ワトソン・シニア[IBM社CEO]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/240wm/img_bc4b76f1db7441ef18aaa4c2ef8074a07181.jpg)
第43回
1年前の金融パニックの遠因「パングロスの罠」とは?
サブプライム問題に代表される、クレジット市場の「行き過ぎた楽観主義」の背景に何があったのか。吉國眞一氏が近著『国際金融ノート』で興味深い指摘をしている。

第8回
読者投票型ニュースポータル「ディグ」が急成長している。グーグルも買収に動いたといわれる同サイトの台頭は、メディアの新旧交代を加速させそうだ。

第18回
オバマ氏を外交音痴と呼ぶ専門家は多い。だが、本当にそうなのか。元国防次官補のコーブ氏は、イラクで判断ミスを繰り返すマケイン氏こそ看板倒れであると指摘する。

第39回
イチロー選手が日米通算3000安打を達成した。日本では新聞・テレビを問わず、上を下への大騒ぎである。ところが蓋を開けてみれば、イチロー選手のこの「偉業」を取り上げる米メディアは皆無であった。
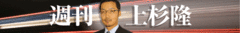
第7回
オバマvsマケイン。その勝敗はネット活用の優劣ではすでに決している。オバマの圧勝である。本場のアルファブロガーたちも舌を巻く民主党大統領候補のネット活用法を紹介しよう。

第4回
連載開始以来、反面教師として取り上げてきたデルもここ数年はソーシャル・ウェブに力を入れている。全社的な顧客との対話で、「Dell Hell(デル地獄)の汚名を返上しつつある。

第41回
米住宅公社問題で投げ売りの恐怖 いまだ残る「ドル暴落危機」の火種
7月6日、ヌリエル・ルービニ・ニューヨーク大学教授が発表した、“第二ブレトンウッズ体制”の崩壊の可能性を問うレポートが話題になっている。

第17回
原油高の要因を巡っては、OPEC陰謀説、ファンド悪玉説などさまざまな論調があるが、真実はそのいずれでもない。注目すべきは、需要を肥大化させる中国と産油国のガソリン安だ。

第37回
米国の真の危機は、足元の金融システム危機ではない。それはむしろ中長期的に基幹産業たる金融産業が衰退し、それに伴って潜在成長率が低下していくことにある。
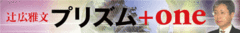
第34回
昨年夏に始まった世界的な経済混乱は、終息するどころかますます深刻さを深めているように見える。この問題に関するニューヨーク・タイムズと読売新聞の記事を比較してみた。
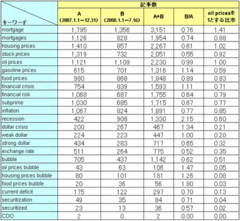
第6回
ITの世界を根底から変容させる巨大連合誕生の憶測が広がっている。グーグルによるセールスフォース・ドット・コムの買収だ。その噂の真相とインパクトの大きさを探った。

第166回
住宅公社への素早い対策の裏に誤算公的資金に手を染めた米金融当局
7月11日金曜、米連邦住宅抵当公社などの経営不安から、ダウ平均は一時、1万1000ドル台を割り込んだ。危険を察知した当局は緊急声明を発表したが、じつは誤算ゆえの対応だった。

第15回
国民的スポーツとまで言われたプロ野球の人気は、何故ここまで凋落したのか? どうすれば回復するのか? 今回はプロ野球人気を立て直す秘訣を考えます。
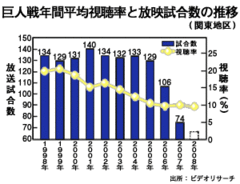
第2回
食料問題に関する洞爺湖サミットのG8共同声明は実はふたつの点で画期的だった。ひとつは農業の拡大支援、もうひとつはバイオ燃料の生産抑制とも取れる表現が盛り込まれたことだ。

第36回
ポールソン米財務長官が緊急記者会見を行い、ファニーメイとフレディマック、住宅公社2社の救済法案の審議を急いでいる。ついこのあいだまでグズグズしていたブッシュ政権が慌てて動き出した本当の理由を探った。
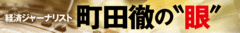
第40回
利上げに踏み切ったECBに「日銀ゼロ金利解除」と似た空気
ECBは欧州市民のインフレ予想の上昇を現段階で阻止することを強調するが、ユーロ圏には成長鈍化の国が多い。利上げ効果は、しばらく慎重に見守られるべきだ。

第3回
前2回でソーシャル・ウェブ革命の申し子、米ザッポスの常識破りの経営手法を紹介した。今回はさらに深堀りし、顧客を虜にする同社のコミュニケーション術を分析する。
