組織・人材(20) サブカテゴリ
第10回
地質工学全般のコンサルティングを行う、高い技術力を持った専門家集団、応用地質(東証一部上場)は、知られざる知識経営の優等生である。単なる報告書のライブラリーではない社員と社員をつなぐ社内ウェブ構築の秘訣に迫る。

第191回
業界初! 営業部間異動を義務化双日が狙う縦割り意識との決別
総合商社は、部門間の縦割り意識が非常に強いく、業界内では人材戦略を見直す動きが活発化している。その中で、双日が、営業部を越える異動を義務化した。それは業界に根づいた旧弊との決別を意味する。
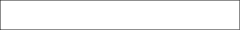
第6回
成功確率が高いと思われる戦略を打ち出しても、組織がなかなか動かないことは多々あります。ですが、現場でのマネジメントレベルで細かい工夫やアイデアの積み重ね次第で“組織のダイナミズム”は刺激できるのです。
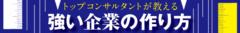
第5回
企業は「企業の目的」「価値観」「将来の展望」の3条件を満たしているビジョンを持つことが必要です。それを掲げることで、全社員が同じ方向を向き、同じ判断基準で物事を捉えて、企業活動を推進できるのです。
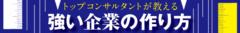
第3回
日本では製造業を中心に“業務の標準化”には強いと思われがちです。しかしながら、果たして皆さんの職場ではいかがでしょうか? 利益責任を担っているポジションほど、“標準化”が進んでいないようなのです。
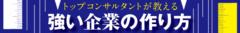
第5回
今回は個別企業論ではなく、すでに紹介した三社のモデルを改めて咀嚼し、社内ウェブの成功の条件を検証したい。共通して言えることは、人中心のコミュニケーションの重要性である。しかし、道筋は一つとは限らない。

第6回
グロービス・マネジメント・スクールで教鞭をとる林恭子氏が映画を切り口に、組織論の様々なテーマやフレームワークを紹介する連載。第6回は、「モーターサイクル・ダイアリーズ」で、キャリアについて考える。
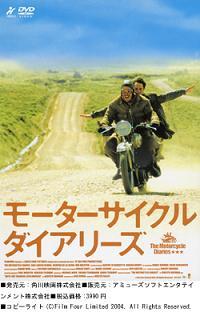
第2回
年間の数値目標(予算)を確実に達成するためには、どう目標を立案するかという点、立てた目標達成に向けていかにマネジメントするかという2つのポイントがあります。今回はそのポイントについて考えます。
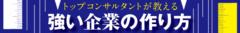
第4回
話題先行の社内SNS――。日本には確かにお手本は少ないが、この企業だけは違う。それどころか海外でも通用する先行モデルだろう。全社員の8割以上が参加するNTTデータの社内SNS「Nexti」の成功の秘密を探った。

第1回
企業におけるリーダーは、結果を出すことが求められます。しかし実際には結果を出せるリーダーと出せないリーダーが存在しています。この要因として上げられるのが「人を動かす力」を持っているか否かなのです。
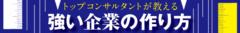
第6回
人材ビジネス会社は「中国人を採用するときには、最初から書類の内容をあてにしないように」と注意を促す。実際、中国では「就職のための偽造証明書つくります」とうたった看板をあちこちで見かけ、繁盛している。
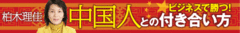
第3回
社内ウェブを導入する企業は増えているが、経営の意思が入っている事例はまだ珍しい。世界各地のR&D拠点の人員を結びつけたP&Gのイノベーション・ネットは、そんな稀有な存在の一つである。
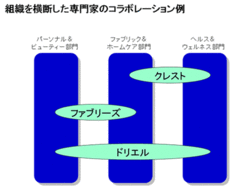
第2回
人手をかけて本社から現場への情報発信をサポートしているというと、システム化が遅れた会社かと思う方もいるだろう。しかし、前回に続いて取り上げる三菱東京UFJ銀行は、ナレッジマネジメントの先行例として注目できる大組織だ。
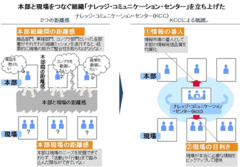
第57回
感動を呼ぶサービスで世界の富裕層を魅了してきた超高級ホテル「ザ・リッツ・カールトン」。同業から異業種まで、世界各国でさまざまな企業やビジネスマンがこぞって学ぶ同ホテルのサービスは、未曾有の世界同時不況でも通用するのか。ラーニングエッジ主催のセミナー講演で来日したリッツ・カールトンの教育機関責任者、ダイアナ・オレック氏に聞いた。

第110回
日本で就職を希望する外国人留学生が急増している。就職支援サービス会社や就職サイトに群がる優秀な人材を獲得しようと、争奪戦に参入する企業も増えている。このトレンドは、日本の採用事情を変える可能性もある。

第3回
労使間でのトラブルが最も多い時期の1つが、採用から数ヵ月の期間です。採用における適性のミスマッチは、労使にとって不幸なことです。今回はそれを防止する運用方法、就業規則作成のポイントをお話しします。
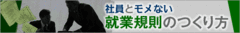
第5回
グロービス・マネジメント・スクールで教鞭をとる林恭子氏が映画を切り口に、組織論の様々なテーマやフレームワークを紹介する連載。第5回は、サスペンス・アクションの名作「逃亡者」で、権威について考える。

第2回
現在支給している手当をいわゆる「定額残業代」として、残業代を前払いしていると認識している経営者も多くいらっしゃいます。しかし、ここに意外な落とし穴があります。
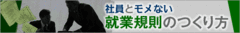
第150回
自らの成長のためには自らに適した組織において自らに適した仕事が必要だ
大きな組織のほうが仕事ができるか、小さな組織のほうができるかはわからない。自らの成長のためには、自らに適した組織において自らに適した仕事につかなければならない。

第149回
成長とは資金の余剰ではなく不足を意味する
財務上の見通しを持たないと、成功するほど大きな危険となる。製品やサービスで成功し、急成長。バラ色の見通しを発表。株式市場が目をつける。流行の分野であれば大きな注目が集まる。ところが1年半後に挫折する。
