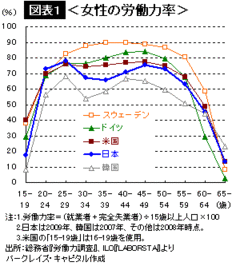組織・人材(18) サブカテゴリ
第14回
入社後の適応・活躍は、大学時代の経験と密接な関係があると、多くの採用担当者が確信している。しかし、それを問いかけて採用しても、適応・活躍できずに社内でくすぶる若手が出てくる。入社後の適応・活躍を促す「いい経験」とは、どのようなものかを考えてみよう。
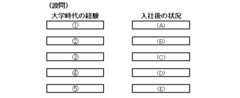
第13回
いつの時代にも「いまどきの若いやつは……」との声は耐えない。批判するのは簡単だが、批判される側にも言い分はある。リクルートの調査を基に、なぜ若手社員がやる気を失くすかを分析すると、コミュニケーション不足であることが浮かび上がってきた。
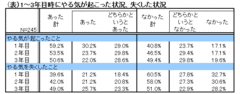
第9回
少数精鋭のコンサルティング企業には、「Up or Out」(昇進、さもなくば去れ)という厳しい掟がある。しかし、それを以てして、単なる切り捨てやエリート選抜だけが行われていると決めつけるのは間違いだ。ボストン コンサルティング グループのトップに、人材育成の要諦を聞く。

第12回
日雇い派遣には、ワーキングプアやホームレスの元凶という否定的なイメージが強い。日本で長くスタンダードとされてきた正社員と対極にある働き方だからこそ、日雇い派遣で働く人の目的、事情、能力…は実に個人差が大きい。日雇い派遣の一般的なイメージと実態には、大きなギャップがある。
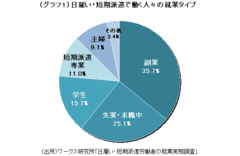
第11回
非正規社員の比率が高まり、問題視されている。解決法としては正規社員化が叫ばれているが、本当にそうだろうか。雇用する側は、非正規社員の実態を正しく理解する一方で、雇用される側は、正社員で雇用されるには、責任が伴うことを自覚すること、両側からの改善が必要である。
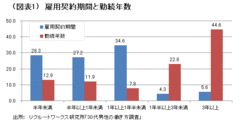
第10回
有期雇用者の「雇い止め」に関わるトラブルを避けるためには、現場のマネジャーの役割が重要である。多くの裁判例を通じて、何が雇い止めという判断に影響するか分析し、現場のマネージャーが心得ておくべき事柄を明らかにする。
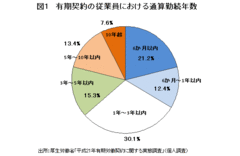
第9回
「若者がなかなか育たない」「ミドルの成長が停滞している」「シニアのキャリアが描きにくい」といった声が企業に渦巻いている。こうした現象は実は個人がもつ“自己信頼”と深く関わっている。キャリアデザインや人材育成において、この自己信頼の構造を捉え直すことが必要である。
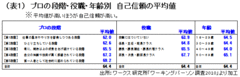
第3回
東日本大震災を契機として、有事のリーダーシップのあり方をめぐる議論が盛んになっている。しかし、危機に直面したリーダーに求められる要件は、平時に比べてそれほど違うものなのだろうか。サイデル社長は、本質的には不変であると語る。

第164回
福島原発事故への政府や東京電力の対応に、不信感が募っている。彼らの対応は本当に「不誠実」なのか? 小川真人・ACEコンサルティング代表が、震災を機に組織が考えるべき「誠実性」と「社会的責任」について提言する。

第8回
2006年から2007年にかけて、日本企業のあいだでは「女活」がブーム。これによって、結婚・出産しても仕事を続ける女性が増えたものの、責任ある地位に就いた女性の比率はあまり高まっていない。この両輪があいまってこそ「女活」が本当に意味のあるものとなる。

第7回
ミドルマネジャー問題が話題にのぼる頻度が減っている。だが、問題が解決したというわけではない。この問題の解決にはリーダーシップ議論から組織制度議論への転換が必要である。組織制度の問題に対する改善策・解決策を提案する。
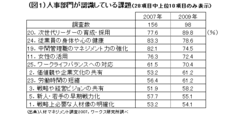
第6回
20代のビジネスパーソンは7割が草食系だ。こうした世代性も踏まえると、成長にはどのよう要因が関わっているのだろうか。さまざまなアンケート調査をもとに、彼・彼女らの成長のヒントを考えてみよう。
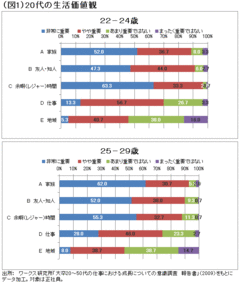
第5回
新卒の就職難が喧伝される昨今だが、欧米の就職事情はどうなっているのだろうか。米国を例にとると、そのあり方は日本と全く違う。新卒、中途という区別もないし、就活期間もばらばらだ。どのようにして企業と求職者が出会っているのか、その実情を見てみよう。
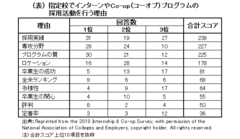
第131回
社員の約半数が65歳以上で、最年長者はなんと99歳。高齢労働者の潜在能力を見事に引き出し、過去10年間で売上高3倍という驚異的な成長を続けるヴァイタニードル社。世界が注目する、その経営の秘密に迫る。

第4回
現在の就活を巡る議論のほとんどは、就職弱者にスポットを当てたものになっている。しかし、現代の就活における問題の本質は、周到に準備し第1志望に就職した就活エリートの躓きである。なぜそのような事態が起こっているのか。その原因と対応を考えてみる。
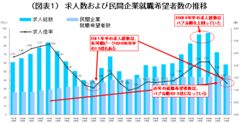
第16回
「将来に希望が持てない」「長生きしても仕方がない」と、厭世観を唱える人々が増えている。哲学者の内山節氏は、この状況を「経済が全ての人を幸せにできなくなった社会」と捉え、幸福の尺度を考え直す必要性を説く。
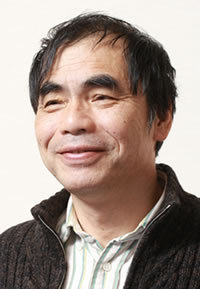
11/02/12号
誰も教えてくれなかった「就活のウソとホント」学生、企業、大学をめぐるミスマッチの実態
「超就職氷河期」と言われるなか、学生の就活がいよいよヤマ場を迎えています。しかし、巷には虚実ないまぜの情報が溢れています。今回の特集では、それらを徹底検証し、就職・採用活動の実態を明らかにします。

第28回
いよいよ経営学教室の執筆者4人による座談会の最終回。現場力を上げるには、第1には本社の役割が重要。どこで付加価値を上げているかを見直し、現場に出向き、匠を大切にし、お祭りを仕掛けて、「ノリ」のいい企業とする。そんな人にフォーカスした施策が求められている。

第52回
最近、「ディフュージョンライン」がブームになっています。特にファッションの世界では、そのラインのブランドを持っていない企業はないほど、増えているのが実態です。では、そもそも「ディフュージョンライン」とは何なのでしょうか。
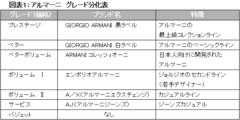
第5回
日本の女性の労働参加率を年齢別に見ると、その形は「M字」となる。ここにきて、そのM字の落ち込みが浅くなりつつある。しかし、喜んでばかりもいられない。背景には、女性の未婚化や夫の失業増加という、少子化に関わる問題もあるからだ。