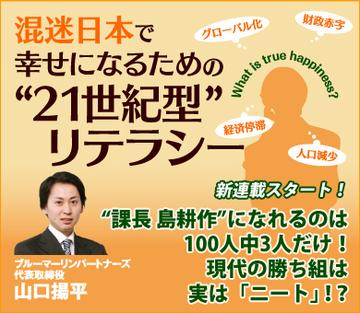山口揚平
第10回
お金は「手段」であり「最終目的」でもある。だから人は、お金の先に自由と可能性を見出す
お金は手段であり、メディアであり、最終目的でもある――。『リフレはヤバい』著者で慶応義塾大学ビジネススクール准教授の小幡績さんと、山口揚平さん、職歴も考え方も異なるふたりが、共通の関心事である「お金」をテーマに多いに語り合います。
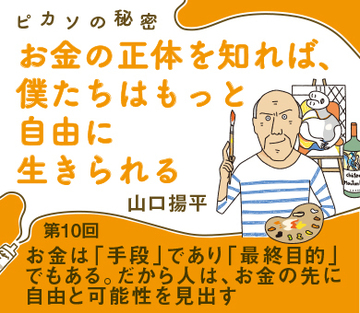
第9回
信用が貯まって初めて評価される社会だからこそ目先のお金より豊かさを、“何を”より“誰と”を大切に
山口揚平さんと大石彩佳さんの対談の前編では、お金の話から大石さんの夢を実現するためのアドバイスが、山口さんから贈られました。後編では、まさに就職活動真っ最中の大石さんの進路の話を皮切りに、お金と愛と信用にまつわる価値観を語り合います。
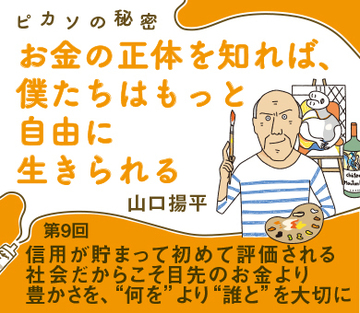
第8回
お金があることと豊かさの違いは何か?人生における愛とお金の最適バランスを考える
対談シリーズ第2回のゲストは、東京大学法学部4年生の大石彩佳さんです。2011年のミス東大コンテストで準ミスに選ばれる一方、東北被災地にボランティアを派遣する団体「東大‐東北復興エイド(3月で活動終了)」の渉外・広報担当として奔走される、まさに才色兼備の現役学生さんです。
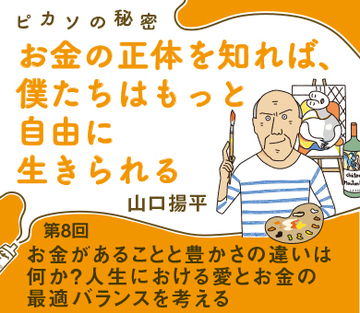
第7回
お金による市場メカニズムなしに価値を直接交換する仕組みは長続きするか?
ライフネット生命保険社長の出口治明さんをゲストに迎えた、『なぜゴッホは貧乏で、ピカソは金持ちだったのか?』著者の山口揚平さんによる対談は、本の内容からさまざまな方向へ広がっていった。対談後半は、出口さんのフィールドである保険について、山口さんが持論を展開するところから始まった。
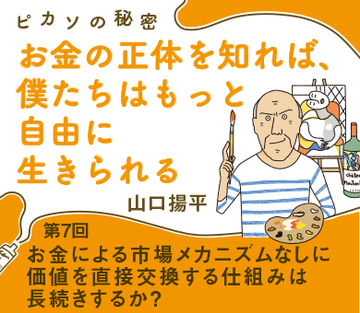
第6回
アメとムチのどちらが有効か?「好きなことで食べていく」リテラシー育成法
今回から『なぜゴッホは貧乏で、ピカソは金持ちだったのか?』著者の山口揚平さんが「お金」をテーマにさまざまな人たちと語り合う、対談シリーズとなります。第1回のゲストは、ライフネット生命保険社長の出口治明さん。「好きなことで食べていく」リテラシー育成法について議論が盛り上がります。
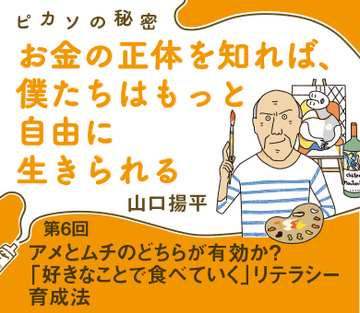
第5回
仕事や家庭が忙しいビジネスパーソンが新しいライフスタイルの準備をするには?
人びとは物理的な近さに関係なく、価値観の合う友人との結びつきを強め、価値を直接交換するようになる。その土台となる新たなコミュニティ・ネットワークづくりこそ、私たちが今まさに取り組むべきことだ。
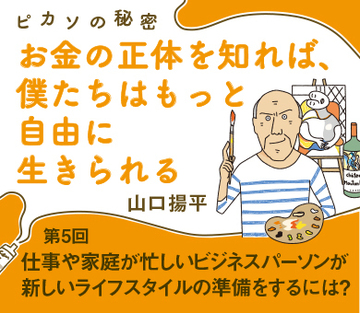
第4回
信用がお金に換わる世界で、僕たちは「上場」し「株価」を付けられて生きている
信用のありかは国家だけでなく、企業や個人に多極化している。よりよく生きていくコツは、今、流通しているハードマネーを1億円持つ、といったことではなくなった。誰とつきあうか、どう信用を創造するか、信用とは何か、などを丁寧に考え、咀嚼し、日頃から信用を貯めていく生活習慣こそ大切だ。
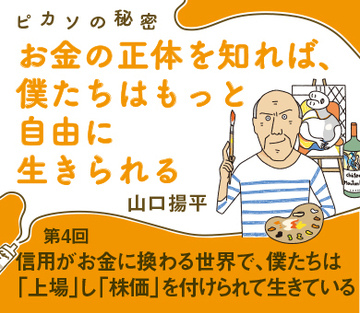
第3回
自分の産む価値をお金に換えたいなら好きなこととやるべきことを追求しよう
人はみな、価値を産み出す源泉を内に秘めている。仕事とは、その才能をお金に変換する作業にすぎない。もし、世界に価値を産み出したいなら、何よりもまずは“好き”を追求しよう。それでも、やりたいことがみつからないなら、やるべきことをやろう。
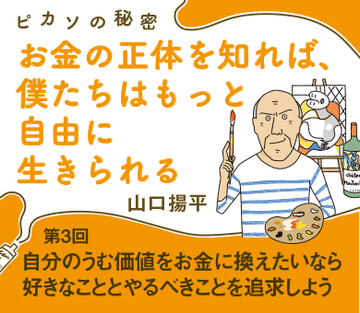
第2回
「お金はメディアのひとつでしかない」と知れば、呪縛と偏見から解き放たれる
お金は強力だが、絶対的存在ではない。それを理解しているだけで、僕たちはお金の呪縛から放たれ、お金に対する偏見から少し距離を置いて、冷静な目でそれを捉え直せるようになる。それは、僕たちがお金と良い関係を築くためのきっかけだ。
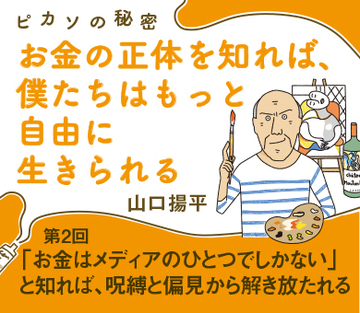
第1回
経済的にも大成功したピカソに倣う「お金」の本質
生前、ピカソは言ったそうだ。「私は、対象を見えるようにではなく、私が見たままに描くのだ」。僕たちは、お金の正体を知らなければならない。そうでなければ、僕たちは自分の人生を自由に創造し、幸せに暮らすことがますます難しくなるだろう。
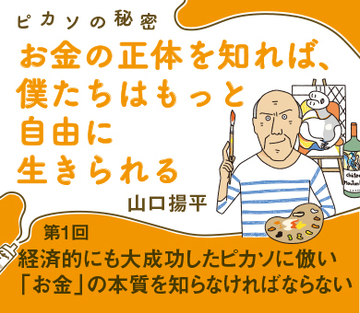
最終回
「生きる」とは「創造する」こと起業の経験から見えてきた本当の“自由”
本連載の最終回。著者が自身の経験を振り返りながら、連載を総括する。幸せとは何か? 自由を得るにはどうすれば良いのか? 世界はどう変わっていくのか? 真に「生きる」ことで心身をすり減らしながらも自分の得手不得手を知り、将来を模索し続けながら発する、渾身のメッセージをお届けする。
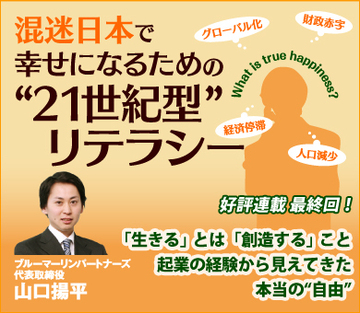
第7回
「頭が良い」の定義は変わる。ロジカルシンキングより“メタ思考”
ビジネスパーソンなら、誰しも頭が良くなりたい、と思っている。しかし今日の「頭が良い」とは何のことだろう? 僕は「メタに考える力」だと思う。それは「物事を一歩上の次元から見ること」であり、「本質に迫る」ことだ。このメタ思考とは何か? そのために心がけるべき事は何か?を整理してみた。
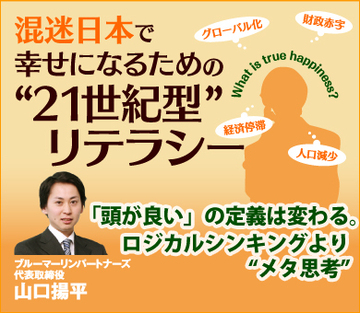
第6回
「好き」で「食う」を実現するには?AKB48とハーバードに共通する成功法則
日本社会の「平等性」や「平均性」は経済衰退に伴って失われていくだろう。そんななか個人の才能を土台として、社会にどのような価値を提供できるか? 「好き」なことでは「食えない」と諦める人が多いが、そんなことはない。カギは、「好きを継続させる土台(システム)」をつくることにある。
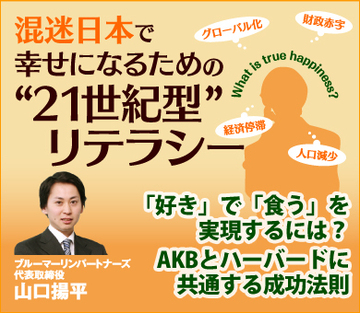
第5回
“引く”ことで浮かび上がるもの21世紀型 幸福の新方程式
世界第3位の経済大国でありながら、自殺者が非常に多い日本。“幸せ”とは言えない状況だ。幸せを実感するには、自分の目的や利便を「追求」するのでなく、あえて「引く」ことで、心をコントロールする必要がある。その上で、好きなことや貢献することに注力すれば、改めて生きる意味も見えてくる。
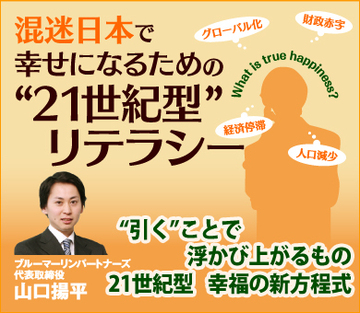
第4回
世界は三層構造でできている「国家」「企業」より重視したい所属先は?
僕たち生きる世界は、「国家」「企業」「個人間の紐帯」の三層にまたがっている。このうち特に「企業」や「個人間の紐帯」の重要性が増しており、そこでの自分の存在感を増す努力をすべきである。英語とITリテラシーは不可欠だが、プラスαの能力が必要になってくる。

第3回
貨幣は『ショートカット(中抜き)』される時代へお金を介さない価値交換を実践しよう
貨幣の電子化やネットワークによる信用の可視化によって、お金の発行母体は多様化した。さらに進むと、お金を介さず(ショートカット=中抜きして)取引が実現する世界に突入する。そこで必要なリテラシーの学習法は、やりたいことをお金を介さずいかに実現するか、考え愚直に実践していくことだ。
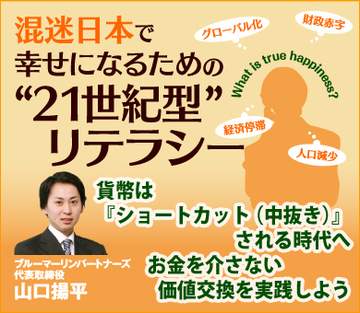
第2回
札束を積むより信用を築け!~FacebookやTwitterがつくる21世紀の“信用主義経済”をよりよく生きるコツ~
お金は所詮、人間が経済活動のために信用を数値化して、価値を仲介するために作り出した道具に過ぎない。しかも今や、その発行主体は各国の中央銀行に限らない。信用があれば、企業のみならず、個人も“お金”を発行できる。そのためには、個人として信用され、その証明を客観視できる状態が必要だ。
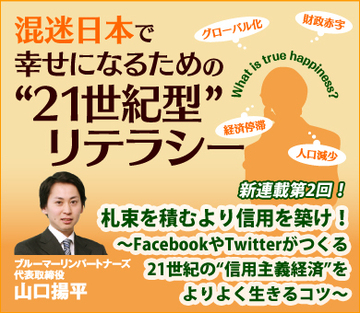
第1回
“課長 島耕作”になれるのは100人中3人だけ!現代の勝ち組は実は「ニート」!?
日本の財政は危機的状況にあり、経済も低成長化が加速するなか、将来の見通しは不明瞭だ。高度成長期に一般的に良いとされた働き方や価値観も大きく揺らぎ、特に若者世代には元気がない。今、どんな生き方をすべきなのだろう?いったん、立ち止まって考える「ニート」という選択も、意外と有効かもしれない。