
森信茂樹
第119回
英国のブレグジット(EU離脱)は、税制に大きな影響を及ぼすだろう。英国とEUとの取引が「域外」取引になるので、ヒト・モノ・カネ・サービスの自由な移動を裏付けていた様々な税制上の特権を、一気に失うことになる。日本企業への影響も大きいだろう。

第118回
英国の国民投票ではEU離脱という結果が出た。この対立構造の背景には、貧困と格差がある。日本でも、所得分布、資産分布の両面で中間層が二分化する、欧米同様の状況が始まっている。これまでのアベノミクスは失敗したのだ。では、今後どうするべきか。

第117回
この参議院選挙から選挙権年齢が18歳以上に引き下げられ、新たに240万人程度の有権者が増えることになる。この機会に、わが国の世代間の負担構造がどのようになっているのかを考えてみたい。その構造は、若者にとって不利なシルバー民主主義そのものだ。

第116回
安倍政権による消費増税延期は、大きな波紋を広げた。国民全員に負担増を求める消費税は、これまで多くの政権の基盤を揺るがせてきた。しかしこのままでは、日本の社会保障の充実も財政再建も図れない。増税延期から見えてきた課題を4点にまとめてみた。

第115回
安倍総理は、消費増税の先送りを決断したようだ。それだけならまだしも、財政出動という小泉内閣以降葬られてきた政策を復活する。全てサミットの議論のせいにしてのことだ。これ以上の茶番劇は見当たらない。アベノミクスはなぜ失敗したのだろうか。

第114回
パナマ文書問題で浮き彫りになったことは、脱税の問題とは別に米系多国籍企業を中心とする「租税回避」の問題である。アグレッシブな租税回避は、企業倫理に関する問題だけに、日本型コーポレートガバナンスの成熟度が試されていると言える。

第113回
5月10日に公表が予定されているパナマ文書に関して、マスコミの報道が日に日に大きくなっている。先週ワシントンDCで開催されたG20会合の声明文を解読しながら、個人課税を念頭において、パナマ文書問題に関わる3つの論点について述べてみたい。

第112回
世界中に波紋を広げているパナマ文書だが、日本居住者へのインパクトはいかほどだろうか。今後日本でも、個人や法人の名前が明るみに出てくることが予想される。その場合、何が問題となるのだろうか、何を問題とすべきだろうかを考えてみたい。

第111回
安倍首相は官邸に米国の経済学者らを招いて、国際金融経済分析会合を開催した。しかし、一国の租税政策、消費増税の是非についてのアドバイスを他国の専門家に求めることは、筋違いではないか。安倍政権が真に考えるべき政策とは何か、提言したい。

第110回
2017年4月から予定されている消費税10%への引き上げの先送り論が、官邸周辺から出てきている。それが現実となれば、アベノミクスは行き詰まるだろう。適切な分配政策による成長を実現するため、本当にやるべきは所得税改革だ。

第109回
税制改正法案が国会に提出され、消費税軽減税率問題が議論の俎上に上っている。この機に、英国とドイツの例を見ながら、実際に日本で軽減税率が導入された場合、食品価格表示においてどんな混乱が生じ得るのかを考察してみよう。

第108回
2014年に最も注目された税務訴訟に、ヤフーとIBMの「租税回避行為」に関するものがある。「損失」を利用することで、自らの税負担を軽減する取引だ。2社の訴訟を通じ、国際標準から大きく遅れた日本の租税回避議論を検証する。

第107回
予算委員会で、軽減税率導入にまつわる議論がこれから本格化する。国民の軽減税率に対する支持率も、次第に落ちてきている。軽減税率導入によって空く「1兆円」の大穴をどう考えるべきか、政府の国会答弁の論拠はあまりにも怪しい。

第106回
公明党への配慮・選挙対策として決まった印象が強い、消費税の軽減税率導入。最大の問題は、軽減税率の導入で社会保障財源に1兆円の穴が開いたことだ。その穴を、政府の言う「確実に恒久的な財源」で埋めることなどできるのか。
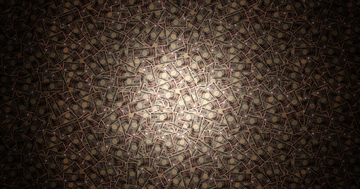
第105回
2017年4月の消費税率10%引上げに向け、軽減税率の導入が決まった。 驚くことに、「新聞」にまで軽減税率の適用が決まったのだ。これで、軽減税率の旗振り役だった読売をはじめとする新聞社は、安倍政権に大きな借りをつくった。

第104回
安倍首相の発言により、4000億円の財源がかかる総合合算制度の導入を取りやめ、その財源の範囲で軽減税率を導入する流れが見えてきた。これは、生鮮食料品に加えて一部の加工食品が軽減税率の対象になることを意味するが、「2つのパンドラの箱」を開けることになる。

第103回
消費税軽減税率の自公協議が難航しているが、その際の議論の1つに消費税の「益税」という問題がある。インボイス制度のない日本では、消費税率が上がり複数税率になると、問題はますます大きくなる。「益税」とは何だろうか。

第102回
軽減税率の議論が連日行われているが、それと合わせて議論されているインボイスについては、マスコミ報道を含めて多くの誤解や理解不足がある。「欧州型」を例にとりながら、インボイスを正しく理解するための4つの論点を述べる。

第101回
消費税の軽減税率議論に際し、公明党は欧州型インボイスの導入なしで、現行とほとんど変わらない簡易なインボイスを導入すれば十分と主張しているようだ。しかし、これは不正と益税の温床を生む可能性もある。

第100回
消費税率10%増税時における低所得者対策がもめている。こうした現状の中で、読売新聞は軽減税率にこだわっている。それは、新聞経営の厳しさからきているのではないか。仮に新聞が軽減税率の対象となれば、消費税のさらなる減収につながる。
