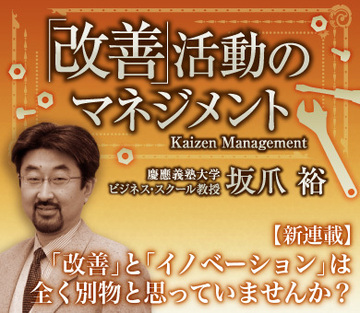坂爪 裕
整理・清掃・整頓という3Sは、その内容が極めてシンプルかつ理解容易であるがゆえに工場文化の創造にもつながる。グローバル化のいま海外工場で3S活動を続けることが、日本の「ものづくり」文化と現地文化との融合を促進し、現場発の新たな「ものづくり」を創造する。

発見型改善は企業の持続的競争優位を確立することができます。しかし、実際に活動を長期間継続する際には、様々な難しさがあります。このような発見型改善を推進し長期間継続するために、ミドル・マネジャーはどのような役割を演じれば良いのかを考えます。

第3回
発見型改善の1つの典型例は、3S(整理・清掃・整頓)の徹底だ。地味でシンプルな活動のように見えるが、3Sの徹底は問題の発見に結び付きやすく、長期間活動を継続させやすい。今回はその理由・論理を明らかにする。
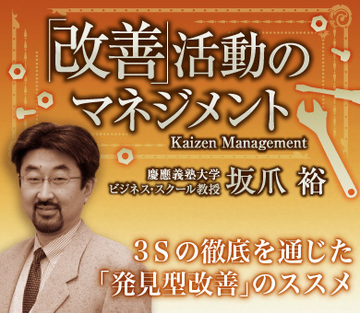
第2回
改善活動の継続は、直接得られる効果だけでなく、間接的な効果にも結びつきます。この間接効果が持続的競争優位の確立にとって、極めて重要です。「消耗型」、「発見型」という2つのアプローチを比較しながら、改善活動を長期間継続させ、間接効果をも生み出すコツを考えてみます。
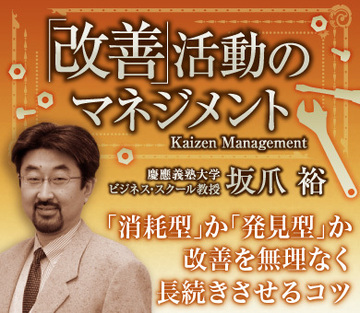
第1回
最近、「改善」の話をすると「激動の時代の今、必要なことは改革やイノベーションなのではないですか」という反論を受ける。だが、改善とイノベーションは問題解決という点では、構造的には同じものだ。では、改善とは何か、その利点と効果について考えてみよう。