みわよしこ
コロナ禍で生活困窮者が増える中、生活保護を申請できるにもかかわらず、積極的になれない人は少なくない。そこには、家族に知られてしまうことへの抵抗感がハードルになっている現状がある。生活保護を役所に申請すると、家族への扶養照会が行われるからだ。

今年は、新型コロナに対する緊急事態宣言に加え、全国的な寒冷と日本海側を中心とした大雪で始まった。寒冷や豪雪に襲われる地域に住む生活保護世帯は、暖房費を節約しようにもできず、悲鳴を上げている。極限状態ともいえるその生活実態と、打つべき対策とは。

コロナ禍の中、2020年から2021年にかけての年末年始には、生活に困窮した人々を支える多様な活動が全国で行われた。食事配布イベント「年越し大人食堂」や生活保護申請の支援サービス「フミダン」の利用状況はどうだったのか。生活困窮者の実態に迫る。

コロナ禍の生活困窮者にとって、行政のサポートを受けられない厳しい年末年始の時期がやって来た。しかし例年と違うのは、厚労省が生活保護の申請や利用に関して、本気で情報発信を行っていることだ。給付抑制の「水際作戦」から打って変わり、何が起きたのか。

一般社団法人・つくろい東京ファンドは、生活保護申請を支援するウェブサービス「フミダン」の運用を開始した。なぜ、このようなサービスが必要となるのだろうか。その背景にあるのは、あの手この手で申請を抑制しようとする役所の、いわゆる「水際作戦」だ。

渋谷区で野宿をしていた60代のホームレス女性が、46歳の男性に撲殺された。この事件は決して他人事ではない。私たちは誰でも、自分たちの安心安全のために誰かを排除したいという「ホンネ」を暴走させかねない。過ちを繰り返さないために、どうしたらいいのか。

コロナ禍で春先から始まった住居確保給付金が、年末年始にかけて期限切れを迎える。それにより、住居喪失リスクを負う人々が続出しそうだ。東京都は春に続いて借り上げビジネスホテルの用意に奔走しているが、本当に支援が必要な人にその情報は届いているのか。

今年9月、東京都下のある自治体では、指定の可燃ごみ袋の容量が突然半分へと減った。ごみ収集を有料化している自治体では、これは実質的な費用増に繋がる。生活保護などで暮らす貧困世帯にとっては、小さくない打撃だ。自治体の弱者保護の姿勢はどうなっているのか。

新型コロナ感染症拡大の「第3波」と前後して、コロナ禍による住居喪失リスクの「第3波」が迫っている。3月から4月にかけて住居確保給付金を利用し始めた人々が、12月から2021年1月にかけて期限切れを迎えるリスクだ。路頭に迷う生活困窮者に支援の手は届くのか。

米国大統領選挙の結果は、バイデン候補の勝利で決着しそうだ。トランプ政権の4年間は、生活困窮者や障害者など、生きづらい状況に置かれている人々の生きづらさをさらに増やす政策が多かった。いま「暗黒の4年間」を振り返ると共に、新しい希望を見つめよう。

11月1日、大阪府で「大阪都構想」の賛否に関する住民投票が行われる。実はこの都構想、生活保護に注目すると、少なからぬ課題がありそうだ。そもそも大阪市が新特別区に分割されても、生活保護や困窮者施策の先行きについて、何も具体的に示されていないのだ。

東京・池袋を中心に定期的に行われる非営利法人の炊き出しには、ホームレスたちが集まる。中でも深刻なのは、「こころの相談」に訪れる人たちだ。メンタルヘルスに関する課題を抱えた人々は、医療に傷つけられた経験を持つ人が多い。彼らを間近で見続ける医師が語る。

『週刊文春』で、俳優のいしだ壱さんが生活保護を不正受給していたことが報道された。「あの人気俳優がなぜ?」と驚く人も多いだろうが、そもそもいしださんは本当に不正受給をしたのだろうか。実は、生活保護の不正受給については、世間に基本的な誤解がある。
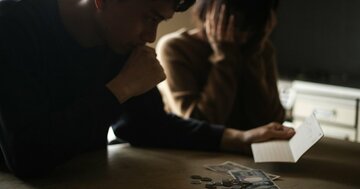
北海道でコロナ禍の打撃を受けた人々には、北海道ならではの公的制度の蓄積がある。その一例は、「冬だけ生活保護」というスタイルだ。また、北海道独自の制度である「薪炭費特別基準」も存在する。柔軟な公助の在り方として、学ぶべきことは多いのだ。

終わりの見えないコロナ禍の中で、春以降、生活困窮者自立支援法の「住居確保給付金」が広く利用された。しかし今、「最長9ヵ月」の期限と厳冬が、同時に迫りつつある。最も生活の危機に晒されるのは、日本に滞在している外国人の留学生や労働者たちである。

経済学者・竹中平蔵氏がテレビ番組で「ベーシックインカム」論を提唱し、にわかに議論が盛り上がっている。ベーシックインカムは、実現可能性、効果、持続可能性といったあらゆる観点から考察しても「亡国の制度」と言うしかない。その理由とは何だろうか。

認定NPO法人Homedoor代表の川口加奈さんは、ホームレス支援の中で異彩を放っている。中学生だった14歳のころからホームレス問題に取り組み続けた。人がホームレスになる理由は自己責任ではない。彼女が問い続ける「何度でもやり直せる社会」とは。

7年8ヵ月にわたる長期政権となった2度目の安倍内閣で、子どもの貧困問題はどのように変化しただろうか。日本全体の相対的貧困率、子どもの貧困率、一人親世帯の貧困率を時系列で比較すると、大きな改善は見られない。なぜ、貧困は解消されなかったのだろうか。

内閣府は「第5次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(素案)」を公開し、パブリックコメントを募集している。「男女共同参画」の内容は幅広いが、気になるのは、生活保護をはじめ現金給付に関する記述がほとんど見当たらないことだ。

猛暑が続き、熱中症による救急搬送が急増している。そんな中、窮地に立たされているのが、エアコンを買えずに暑さを耐え忍ぶ低所得層だ。公費でエアコンを買える道もあるが、まだ制度が徹底されていない。日本が唱える「健康で文化的な生活」は、どこへいったのか。
