
倉都康行
第538回
原油価格の続落を背景にロシアの通貨ルーブルが暴落。世界の資本市場の眼をロシアに釘付けにした。市場には1998年のロシア危機の再来に怯えたパニックの気配も感じられた。やはり歴史は繰り返されるのだろうか。

第5回
バーナンキ・ショック後の新興国危機過去との類似点と相違点は?
アメリカが量的緩和縮小を示唆したことが、どのように新興国経済に影響を与えたのか。2013年に起こったバーナンキ・ショック前後の動向から、振り返ります。
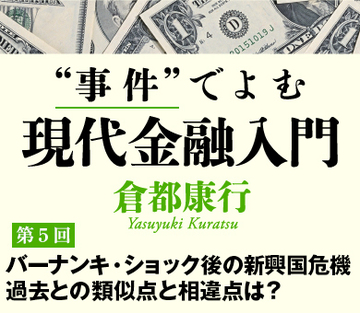
第4回
日本のバブルとその崩壊の裏で邦銀が海外業務を定着・拡大できなかった要因
1989年末の大納会で日経平均株価が3万8915円87銭を記録し、国内はすっかり浮き足立ち、空前の好景気に沸いていた。しかし、それをピークに株価は下落が続き、さらには1991年以降の地価下落を経て急激に景気が後退し、邦銀は巨額の不良債権処理に苦しむこととなった。
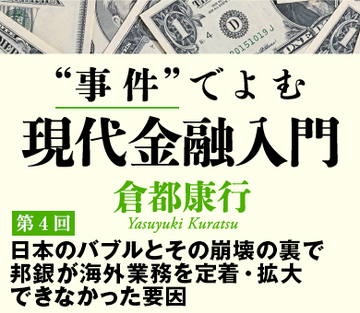
第3回
プラザ合意の副産物としてドル安が生んだ日本のバブルの萌芽
今回は「プラザ合意」の背景と影響についてひもときます。先進国による協調的なドル下げ宣言だった「プラザ合意」によって、ドル円は直前の240円台から1988年に120円台まで下落しました。ただし、その効果は短期的に終わり、日本は円高不況対策によって、その後取り返しの付かないバブル経済へ追い込まれていったのです。
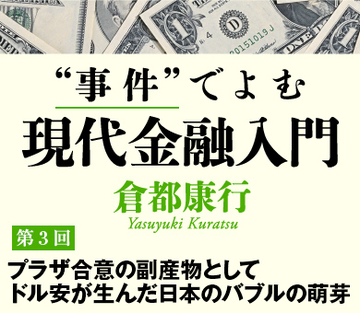
第2回
日本にとってのニクソン・ショックは金融問題にとどまらぬ実体経済の問題だった
アメリカが世界に向けて「ドルと金の交換を停止する」と宣言した「ニクソン・ショック」の背景には、どのような問題があったのでしょうか。資本市場の本格的なグローバル化が始まった、1971年のニクソン・ショックを検証します。

第1回
最近の金融危機にみられる2つの特徴とは?過去から学ぶ経済の仕組みと歴史的な背景
金融業界で国際化と自由化が急激に進んだ40年余。この間の“金融危機=事件”はどのように起こったのか?過去に起こった事件を丹念に追いながら、グローバル経済の仕組みや、その歴史的背景を明らかにしていく本連載。今回は、本論に入るまえに、近年の危機を読み解く意義を考えます。
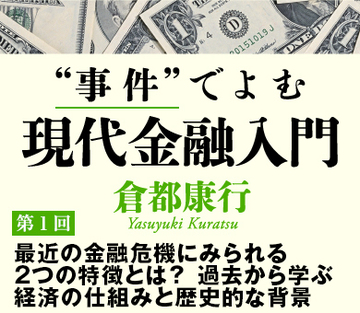
第380回
米議会でようやく暫定予算と連邦債務上限引き上げが合意され、市場が懸念していたデフォルトは回避されることとなった。こうした茶番劇はいつまで繰り返されるのか。米国経済に精通する専門家が、「決められない政治」の本質を斬る。
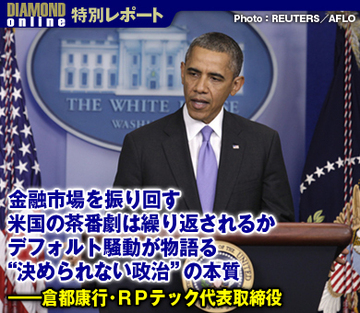
第342回
金融市場の乱調を受け、かつてなく注目が集まった今月18、19日のFOMC。政策現状維持が決められたものの、バーナンキFRB議長の会見は、緩和縮小に明確に舵を切ったという印象を与えた。世界や日本にはどのような影響が及ぶのか。
