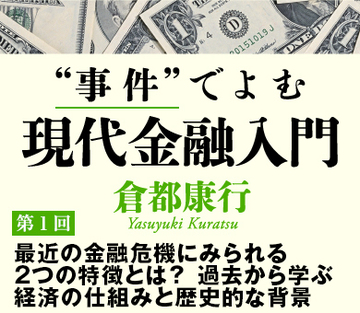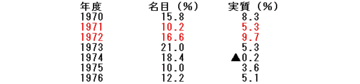アメリカが世界に向けて「ドルと金の交換を停止する」と宣言した「ニクソン・ショック」の背景には、どのような問題があったのでしょうか。また、日本では、どのように受け止められていたのでしょうか。そして、その後の変動相場制は本当に理想的なのでしょうか。資本市場の本格的なグローバル化が始まった、1971年の“ニクソン・ショック”を検証します。
1971年8月15日
ドルと金の交換はなぜ停止されたのか?
8月15日は、日本人にとって今も特別な日と言えるでしょう。欧米の人びとのなかでは第2次世界大戦が終了したのは必ずしもその日ではなく、日本がポツダムで降伏文書に署名した9月2日とみなすことが多いようです。しかし、日本人が玉音放送の流れた8月15日を強く意識していることはご存知のとおりです。
その1945年から26年たった8月15日、アメリカは世界に向けて「ドルと金の兌換を停止する」と電撃的に発表しました。いわゆる「ニクソン声明」です。日本時間ではすでに8月16日の月曜日に日付が変わっていましたが、中高年層には、この衝撃的な日と敗戦記念日とは無関係だと分かっていても、何か因縁めいたものととらえてしまうようです。
長い歴史を通じて、通貨とは金に変換できるもの、という考えが定着していた中で、世界で唯一、金と自国通貨ドルとの交換を約束していたアメリカが突然、金との交換を停止すると宣言したこの「ニクソン声明」とその後の市場の混乱を「ニクソン・ショック」と呼びます。現在でも「オイルショック」や「リーマン・ショック」など、経済における想定外の出来事は「ショック」と表現されますが、この「ニクソン・ショック」こそ、その先駆けです。そしてこの声明は、後述する1944年以来の「ブレトン・ウッズ体制」の終焉を意味する、重要なものでもでした。
1971年8月16日の夕刊を見ると、朝日新聞では「米、ドル防衛に非常措置」というヘッドラインに続く「10%の輸入課徴金」という大きな見出しが目に付きます。また、日本経済新聞にも「米、金交換を停止」「輸入課徴金10%」という見出しが躍っています。日本にとって最大の輸出先であるアメリカが、輸入品への課徴金を導入することが相当の衝撃であったことがうかがえます。
つまり、当時の日本経済にとっての「ニクソン・ショック」は、金融システムの大問題というよりも、輸出が減少するのではないかという、いっそう現実的で差し迫った実体経済の問題だったわけです。
実際にニクソン大統領が打ち出した「新経済対策」と呼ばれる政策には、景気刺激対策として種々の項目が盛り込まれていましたが、なかでも世界が目を見張ったのは、やはり「ドルと金の交換停止」でした。
この声明の直後、欧州諸国は混乱を回避するために為替市場を閉鎖します。それまで金との交換性を保っていた唯一の通貨であるドルが、もはや金と交換できないとあっては、ドルへの信頼が揺らぐのは当然でしょう。市場を開ければドル売りが殺到するのは目に見えていたことから、欧州各国は市場閉鎖を決断したのでした。
その一方で、日本は市場を開いたままにしました。東京市場は予想通りドル売りの嵐が吹き荒れました。この措置は、当時の大蔵省が輸出業者を救うために、できる限り1ドル360円でドルを売れるように配慮したためだった、とも言われています。猛烈なドル売りの嵐に応えた結果、日本の外貨準備は前年の43億ドルから一気に146億ドルへと3倍以上増えました。そして8月28日には、ついに日本政府も固定相場の維持を断念し、1949年から続いてきた1ドル360円の時代は、ここで幕を閉じることになったのです。