加谷珪一
あなたの「お金の偏差値」はどのくらい?3つの質問からわかる「成功する人」の流儀【経済評論家・加谷珪一の分析】
人との関わり方には、「当たり前」だと思われているルールがいくつもある。ただ、仕事でもお金でも成果を出し続ける人は、その「当たり前」を一度立ち止まって見直している。相手がどう感じるかを丁寧に読み取り、自分の価値観だけで判断しない。そんな姿勢が、信頼やチャンスを呼び込む下地になっているのだ。経済評論家・加谷珪一による3つの問いは、単なる性格診断ではない。お金や人間関係との向き合い方に、ひとつ新しい視点を加えてくれるはずだ。※本稿は、加谷珪一『本気で考えよう!自分、家族、そして日本の将来 物価高、低賃金に打ち勝つ秘策』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。

老後を支える公的年金は本当に破綻するのか?経済評論家・加谷珪一が日本人の最大の不安に答える
目の前には物価高、少子高齢化、膨張する政府債務などネガティブな要素ばかりが広がる。多くの日本人は将来不安の中で生きているが、心の拠り所となる年金についても、「いつか破綻するのでは」という声が絶えない。しかし、制度の仕組みや人口構造の変化を丁寧に読み解くと、世間のイメージとは異なる“本当の論点”が見えてくる。経済評論家・加谷珪一は、どのような答えを提示するのか。※本稿は、加谷珪一『本気で考えよう!自分、家族、そして日本の将来 物価高、低賃金に打ち勝つ秘策』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。

「コメも卵ももう値下がりしない」世界を作ったのは誰なのか?【経済評論家・加谷珪一の分析】
コメも卵も、価格が高騰して久しい。私たちはまだ「いつか下がる」と信じているが、経済評論家・加谷珪一氏は「それは幻想だ」と断言する。卵とコメに共通する「値下がりしない構造」を分析し、日本の消費と生産の歪みが生んだ現実に迫る。※本稿は、加谷珪一『本気で考えよう!自分、家族、そして日本の将来 物価高、低賃金に打ち勝つ秘策』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。

東京証券取引所がこの4月に市場を再編し、プライム、スタンダード、グロースの3市場編成となった。各市場には新たな上場基準が設けられているが、基準未達のまま「経過措置」でプライム市場入りした企業も多い。こうした状況下では、どの企業に投資すべきか迷っている投資初心者もいるだろう。その助けとなるべく、東証再編の現時点での課題や、「絶対にやってはいけない」ポイントについて詳しく解説する。

去る1月、ビックカメラが「5年以内にメーカー派遣の販売員の受け入れを停止する」と発表し、話題を呼んだ。家電量販店では、すでにノジマが自社社員だけで店頭販売を行っており、接客内製化が進みつつある。だがよく考えると、派遣元の製品だけを薦めるスタッフが集まってお客を奪い合う接客スタイルは不思議である。家電業界では、なぜこんな慣行が定着したのか。そして、派遣販売員はなぜ切り捨てられようとしているのか。これらの理由を歴史的観点から詳しく解説する。

TikTok Japanが、インフルエンサーに報酬を支払い、Twitter上で特定の動画を紹介させていた。TikTokは若者に大人気で、2021年にはGoogleを超えて世界最多のアクセス数を記録するなど、今最も影響力のあるプラットフォームのひとつだ。にもかかわらず、なぜ運営元はステマに走ったのか。その主な要因と、ステマにだまされない「リテラシーの高め方」を解説する。

アルゼンチンは19世紀以降の世界で唯一、先進国から脱落した国家だ。農産物の輸出で成長したが、工業化の波に乗り遅れ、急速に輸出競争力を失った。時代背景は違うが、似た現象が起きているのが現代の日本である。IT化の波に乗り遅れ、工業製品の輸出力が衰退しているにもかかわらず、社会は現状維持を強く望んでいる。この状況が続けば、アルゼンチンの二の舞いになっても不思議ではない。

日本の国際的な地位が急激に低下している現実について、多くの国民が認識するようになってきた。日本が主要先進国から転落しつつあることは、各種のデータを見れば明らかだが、そうなった理由について積極的に議論されているとは言い難い。これ以上の凋落を防ぐためには、現実を直視し、国際的地位が低下した根本的な原因について検証する必要がある。
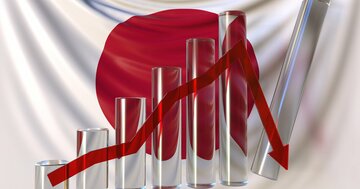
豊富な資産を持つ富裕層。彼らが資産を守り、そして増やすために取っている手段の一つが「投資」である。投資には当然リスクも伴うが、資産を増やしてきた富裕層たちはどのような判断基準、行動原理を有しているのだろうか。その原則は、いたってシンプルなものだといえる。

金融庁は今月22日、みずほ銀行と親会社のみずほフィナンシャルグループに対して、銀行法に基づく業務改善命令を出した。みずほのシステムを実質的に管理するとも取れる、「異例の措置」であり、注目が集まっている。ただ、こうして管理を強化することで一連の問題が解決するとは限らない。場合によっては、さらに状況が悪化する可能性すらある。

みずほ銀行が再びシステムトラブルに見舞われている。2021年2月に多数のATMが使えなくなるという大規模障害が発生し、対策を進めていた最中のことだった。ここまで来るとシステムの設計そのものを疑問視せざるを得ない状況であり、メガバンクとしての存在意義すら問われる事態といってよいだろう。この事態を招くに至った、みずほの「IT戦略不在の20年史」を分析し、今年だけで6度目となるシステム障害が必然といえる理由を解説する。

鉄道車両向け空調装置で長年にわたって不正を行っていたことが発覚し、三菱電機の杉山武史社長が引責辞任を表明した。今回のケースではデータをねつ造するソフトウエアまで開発しており、組織ぐるみであることは明らかだ。同社は過去にもパワハラ問題や不正アクセス事件など不祥事を起こしており、組織的な問題を指摘する声は多い。問題が繰り返される根本原因とは何か。歴史も踏まえて考察したい。

東芝の株主総会運営の適正性について調査を行った弁護士が、「東芝と経済産業省が緊密に連携し、株主に対して不当な影響を与えた」とする報告書を公表した。経産省は反論しているが、このような疑義が生じていること自体が、資本市場の信頼性を低下させ、国益を大きく損ねている。報告書の内容が示唆する、本質的な問題とは何か。

政府が緊急事態宣言の延長を決定した。とりあえず6月20日までの延長だが、感染状況がどう推移するのか予断を許さない。宣言の延長で経済がより大きな打撃を受けるのは間違いないが、一方である種の「宣言慣れ」も起きている。宣言延長の経済的な影響について探った。

英投資ファンドCVCキャピタル・パートナーズによる東芝への買収提案。この提案を受け入れた場合、どんな効果が期待できるのか。また、安全保障上のリスクも指摘されているが、買収差し止めは現実的な判断といえるのだろうか。指摘されている懸念と、買収によって期待されていることについて解説する。

2月28日、みずほ銀行で大規模なシステム障害が発生した。同行におけるシステム開発・運用の経緯と銀行が置かれた状況を考えると、今回のシステム障害は邦銀のIT戦略における大きな転換点になるのではないか、と筆者はみている。

米アマゾンの創業者であるジェフ・べゾス氏が、同社の最高経営責任者(CEO)を退任することが発表された。世界的企業となったアマゾンはこれからどんな成長をもくろんでいるのか。これまでのアマゾンの経営戦略から、今後起こり得る変化について考えてみたい。

新型コロナウイルスの感染拡大の長期化に伴って、ポストコロナ社会に対する不透明感が高まっている。人の移動が減り、大規模な業界再編が起こるという大胆な予想がある半面、感染が終わればすべて元に戻るとの楽観的な見方もある。感染終息後の社会に対して不安を抱えている人も多いだろうが、こうした時に頼りになるのが歴史である。

2020年はコロナ危機で大変な1年だったが、2021年も引き続き、ウイルスの感染拡大が経済の足を引っ張る可能性が高い。だが水面下では、コロナ危機を超えるインパクトをもたらす大きな変化が始まっている。それは全世界的な脱炭素シフトである。

政府からの通信料金引き下げ要請を受け、最大手のNTTドコモが踏み込んだ料金プランを打ち出した。競合各社の追随はほぼ確実であり、通信料金は大幅に下がる可能性が高くなってきた。だが、通信会社というのは典型的な設備産業であり、簡単にコストは下げられない。料金引き下げは利益の低下に直結する可能性が高い。消えた利益は最終的に誰が負担するのか。
