岡田光雄
頼んでもいないのに、自分が知っている限りの知識を語り始め、しばしば知識のマウンティングすらも仕掛けてくる厄介な存在。そんな「こじらせ博学」は、あなたの周囲にもいるのではないだろうか。そんなめんどくさい人のトリセツを、カウンセリングサービス所属の心理カウンセラー・近藤あきとし氏に聞いた。

いま書店のビジネス書の棚でひときわ目を引くのが「縄文力」というワード。現代人が失ってしまったビジネスの価値観が、約1万5000年前の日本に存在したというのである。いったいそれはどんなメソッドなのか。

ブラック企業が蔓延する日本社会に突如出現し、ネットを中心に話題を集めている「退職代行サービス」。「辞めたくても辞めさせてもらえない…」と嘆くビジネスマンに代わって、その名の通り退職業務を代行してくれるというものだ。現代ならではの新ビジネスの実態に迫ってみた。

1975年に「秘密戦隊ゴレンジャー」が放送されてから実に43年もの間、日本で愛され続けている東映の特撮ドラマ「スーパー戦隊」シリーズ。その人気は海外にも及び、各国でローカライズ作品も数多く生まれ、世界の人々がこれまで持っていたヒーロー像を根底から覆してきた。何故、スーパー戦隊はロングセラーとして世界に愛されるのか、特撮研究家の氷川竜介氏に聞いた。

成人年齢が20歳から18歳に引き下げることが閣議決定された。これに対して若者の責任感の欠如などデメリットばかりが取り沙汰されている。そんな中、「今こそ若者の金融リテラシーを育むチャンス」と語るのは、高校生の“金融知力”を競う「エコノミクス甲子園」を主催するNPO法人金融知力普及協会事務局長の鈴木達郎氏だ。

子どもに生活習慣や情操面での教育を施す上で欠かすことができない「絵本」。そして今、日本の絵本が中国で爆発的に売れているという。その理由について、ポプラ社の中国法人「北京蒲蒲蘭文化発展有限公司」で董事長を務める永盛史雄氏に聞いた。

麻薬・銃器売買からサイバー攻撃代行まで、「ダークウェブ」の実態
通常のネット検索ではたどり着くことができないサイバー空間「ダークウェブ」。先のコインチェック不正送金事件を含め、ここ近年でよく耳にするワードだが、この空間では、どんな違法ビジネスが行われているのか。『闇ウェブ』(文藝春秋)の著者で、株式会社スプラウトの代表である高野聖玄氏に聞いた。

外国人が日本に来て感動するものの一つが自動販売機。設置台数や技術の先進性は、世界でもトップクラスだ。しかし、海外に目を転じると、日本ほど自販機は普及していない現実もある。日本自動販売システム機械工業会の恒川元三氏に詳しく聞いた。

かつては日本のライブ配信サービス業界を席巻した「ニコニコ生放送」。しかし、近年は衰退の一途をたどっている。人気放送主(生主)たちは、他社サービスへ続々と流出し、業界は戦国時代を迎えているのだ。初期からの“ニコ生ファン”を自負するITジャーナリストの三上洋氏に話を聞いた。
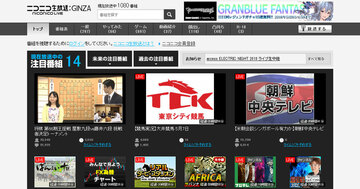
学校教育のブラックぶりがクローズアップされている。しかし、これを「質の悪い教員が増えている」と考えるのは、少し短絡的だ。カウンセリングサービス所属の心理カウンセラー・近藤あきとし氏に、教育現場に蔓延するブラックの真相を聞いた。

近年、健康志向の高まりや食育ブームなどもあって、注目されている「管理栄養士」。その職業に対する世間一般的なイメージとしては、「専門性が高いので給料が良さそう」「国家資格なので就職先はいくらでもありそう」といったポジティブなものだろう。今回紹介する3人の女性も、そんな未来に憧れて業界入りしたのだが、あまりの現実に愕然としたという。

近年、癌医療において、オプジーボやキムリアなど免疫薬が飛躍的に進歩している。しかしその一方で、「免疫療法は胡散臭い」という話もよく聞き、患者はどの情報を信じていいか分からない状況だ。そこで日本医科大学武蔵小杉病院・腫瘍内科教授の勝俣範之医師に、免疫療法はどんなもので、何が問題なのかを聞いた。

就活で難関大手企業にコネなし学生が挑むための「人脈術」
空前の売り手市場で終わりそうな2018年卒の就職活動。しかしその実態は、大手企業に学生の応募が殺到するという根本的な構図は変わっていない。そんな状況の中、来年度の就活生に向けて“人脈”作りの必要性を訴えるのは、“就活のプロ”ことLeaGLO代表取締役の上田浩史氏だ。

スマートフォンのSiriやOK Googleなどでも使われている「音声認識・合成技術」。昨年7月には、東芝デジタルソリューションズも、この技術を利用した新たなサービス「コエステーション」を発表した。“コエ”のマーケットが急速に拡大している今、国立情報学研究所の准教授・山岸順一氏にその技術の最前線を聞いた。

社内に必ず1人はいる「指示待ち人間」。彼らに対して「何でもかんでも質問してくるな!」「臨機応変に行動しろ!」と叱責する上司は多いかもしれないが、現実はそう簡単ではない。そこでカウンセリングサービス所属の心理カウンセラー・山田耕治氏に、あえて「指示待ち人間のまま生き残る術」を聞いてみた。

近年、“愛国”を商材としたビジネスが流行している。書店の棚にはセンセーショナルなタイトルの“嫌韓・嫌中”本が並び、少し前に話題となった森友学園(塚本幼稚園)は、園児たちに熱心な愛国教育をしていた。一体どういう背景があって、愛国に日本人の需要が集まるようになったのか。専門家に話を聞きながらその歴史をたどってみた。

世界的に飲酒による健康被害が問題視され、2020年の東京オリンピックに向けて日本でも酒規制の動きが強まっている。そんななか、「産業と文化としても酒場という場は大切です!」と語るのは、『コの字酒場はワンダーランド ―呑めば極楽 語れば天国』(六耀社)の著者で、漫画『今夜はコの字で』(集英社)の原作者である加藤ジャンプ氏だ。

今や日本人の間では“嫌韓”を語ること自体が珍しいことではなくなりつつあり、インターネット上には、「韓国と国交を断絶するべき」「韓国人を入国させるな」など“日韓断交”論を賛美するコメントが目につくようになっている。だが、こうした主張に対して「合理性がまったく見当たらない」と警鐘を鳴らすのは国士舘大学21世紀アジア学部教授で経済学者の平川均氏だ。

近年、海外での日本食ブームもあって、健康志向の高いセレブからも人気の「豆腐」。しかし現在、大手豆腐メーカーの独占などによって“まちのお豆腐屋さん”が次々と消え、豆腐本来の製法技術が絶滅の危機に瀕しているという。1927年創業の老舗「手づくり豆腐 いづみや」(東京都中野区)の店主で、一般財団法人「全国豆腐連合会」の相談役を務める青山隆氏に話を聞いた。
