浅島亮子
#9
トヨタ自動車と取引のある「下請け企業数」において、トヨタの城下町・愛知県が東京都に負けるという異常事態が発生した。将来的に、愛知経済が地盤沈下し、サプライヤーに再編成の機運が高まっている。愛知県で加速する「ケイレツ大再編」の最終形を大胆に予想する。

#3
満を持して、トヨタ自動車が「2030年にEV(電気自動車)350万台を販売する」大方針を掲げた。トヨタはこの大本営発表をもって「EVに及び腰」という世間の認識を払拭したい構えだ。それでもトヨタにとって、EVシフトはガソリン車やハイブリッド車(HEV)で極めた「勝ちパターン」を自ら取り下げるようなものである。EV350万台を達成した時点のトヨタの業績を大胆に試算し、EV大攻勢へ舵を切るトヨタの苦悩に迫った。

#1
血は水よりも濃し──。トヨタ自動車が創業家である豊田家本家による支配力を急速に高めている。あえて“トヨタムラ”のフィロソフィーや流儀を貫くことで社員の求心力を維持し、表層的なグローバル経営とは一線を画しているようにも映る。だが近年、豊田章男社長による独裁の弊害が「現場のひずみ」となって噴き出すようになってきた。電動化・脱炭素化により、折しも自動車業界はモビリティの価値が一変する大動乱期に突入したところだ。もはやトヨタの敵は、自動車メーカーだけではない。ITジャイアントであり、テスラであり、あらゆる水平分業プレーヤーである。常勝集団トヨタをさいなむ苦悩を明らかにする。

#10
欧州の電池産業は勃興期にある。中でも、ノルウェーに本拠地を構える新興電池フレイル・バッテリー(FREYR Battery)は「提携戦略を駆使する」異彩ベンチャーとして知られる。2018年の創業からわずか3年で米ニューヨーク証券取引所に上場を果たし、量産前から巨額の資金調達に成功した。実は、フレイルのCTO(最高技術責任者)は、日産自動車や米ダイソンで電池技術の腕を磨いた日本人である。川口竜太氏はどのようなチャレンジに挑んでいるのか。フレイル独特のビジネスモデルの要諦や欧州の電池産業について聞いた。

#8
スウェーデンの新興電池メーカー、ノースボルトが存在感を高めている。創業5年にして独フォルクスワーゲンや独BMWなど上客を味方につけて急成長を遂げているのだ。実は、ノースボルトの開発総責任者を務めているのは日本人エンジニアである。日中韓が中心の電池産業を欧州でゼロから立ち上げられたのはなぜなのか。ノースボルトの阿武保郎氏を直撃した。

日本企業の間で人員リストラの実施が常態化している。しかも、従来の人的整理とはタイプが異なる「新種リストラ」が横行しつつある。本稿では、早期・希望退職制度を実施した56社リストを明らかにすると共に、22年に増えそうなリストラの“特徴”を炙り出す。

2021年の自動車産業は電気自動車(EV)一色だったといっていい。世界の主要自動車メーカーはこぞって強気なEV投入計画をぶち上げており、その極めつきはトヨタ自動車のEV大投資計画である。ところが22年の自動車業界では、早くも「EV一辺倒からの揺り戻し」が起きそうな気配になっている。その理由はどこにあるのか。22年の自動車業界の明暗を分ける鍵を大胆に解説していこう。

#15
2021年3月期まで2期連続の赤字に転落した日産自動車が自信を取り戻しているかのように見える。22年3月期の通期見通しでは、売上高予想が約1兆円も下振れするのに、営業利益は上方修正したのだ。半導体不足に伴う減産の長期化や原材料高騰などに警戒感を強める自動車メーカーが相次ぐ中、日産が上方修正できたのはなぜなのか。そのカラクリの背景にある値引きの裏事情に迫る。

トヨタを襲う「脱炭素の六重苦」、エネルギーと技術の覇権争い
『週刊ダイヤモンド』11月6日号の第1特集は「脱炭素地獄 生き残りランキング」です。脱炭素に対応しない“非エコ企業”の株価急落・業績悪化は避けられなくなりました。特集では、トヨタを例に日本企業が直面している「脱炭素地獄」の実態を徹底解説すると共に、日本企業の「脱炭素」脱落危険度を初めてランキング化しました。

#19
トヨタ自動車は「脱炭素地獄」に耐えられるのか。トヨタは、グループ・サプライヤーへの炭素削減のプレッシャー、欧州・中国に仕掛けられたEVシフトのゲームチェンジ、半導体・車載電池の欠乏、電力コスト高騰による国内生産の危機、輸出に伴う炭素税の賦課――など脱炭素シフトに伴う「あらゆる負荷」に苦しめられている。トヨタをケーススタディーに採り、日本企業が見舞われている脱炭素地獄の実態を徹底解説する。

#16
日本のエネルギー基本計画に「水素」の二文字が盛り込まれたのは2014年のこと。トヨタ自動車が水素で動く燃料電池車を発売したが、当時の水素革命は不発に終わった。そして今回、再び水素エネルギーが脚光を浴びている。協議会メンバーは1年足らずで253社・団体に激増。中でも水素にご執心なのが3メガバンクの一角、三井住友フィナンシャルグループだ。水素を巡る企業の思惑を探った。
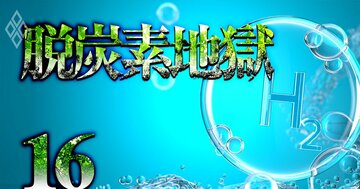
#13
企業の競争力を測る物差しが「利益」から「炭素」に変わる――。急激な脱炭素シフトは企業業績を直撃することになりそうだ。そこでダイヤモンド編集部では、統合報告書を開示している大手企業を対象に「炭素排出量と財務データ」を掛け合わせた独自ランキングを作成した。本稿では、脱炭素シフトで勝ち残るランキング【ベスト50社】を公開する。

#9
企業の競争力を測る物差しが「利益」から「炭素」に変わる――。炭素をたれ流す“非エコな企業”は世界の「脱炭素シフト」の波に乗れずグローバル競争から脱落する危機にある。そこでダイヤモンド編集部では、統合報告書を開示している大手企業を対象に「炭素排出量と財務データ」をミックスさせた独自ランキングを作成した。本稿では、自動車や電機、機械など製造業100社に絞って、脱炭素「脱落危険度」の高い「ワースト100社」を公開する。

#6
企業の競争力を測る物差しが「利益」から「炭素」に変わる――。非エコな企業はビジネスの参加資格すら得られず、“脱炭素地獄”に転落する危機にある。そこでダイヤモンド編集部では、統合報告書を開示している大手企業を対象に「炭素排出量と財務データ」を掛け合わせた独自ランキングを作成した。本稿では、炭素排出量の多い12業種に限定した「ワーストランキング100社」を公開する。
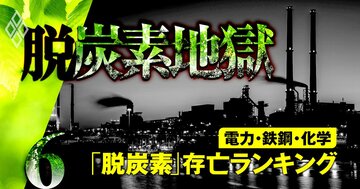
脱炭素「脱落危険度」が高い会社ランキング【ワースト5社】5位JFE、1位は?
企業の競争力を測る物差しが「利益」から「炭素」に変わる――。非エコな企業はビジネスの参加資格すら得られず、“脱炭素地獄”に転落する危機にある。そこでダイヤモンド編集部では、統合報告書を開示している大手企業を対象に「炭素排出量と財務データ」をミックスさせた独自ランキングを作成した。脱炭素による「脱落危険度」が高い企業の総合ランキングを抜粋して公開する。
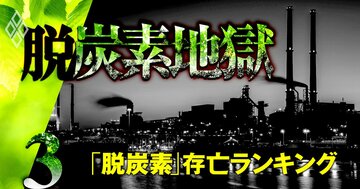
#3
企業の競争力を測る物差しが「利益」から「炭素」に変わる――。非エコな企業はビジネスの参加資格すら得られず、“脱炭素地獄”に転落する危機にある。そこでダイヤモンド編集部では、統合報告書を開示している大手企業を対象に「炭素排出量と財務データ」をミックスさせた独自ランキングを作成した。脱炭素による「脱落危険度」が高い企業の総合ランキングを大公開する。
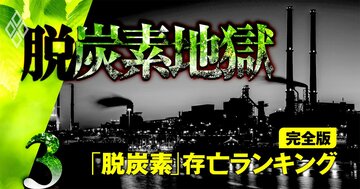
#10
1990年代まで一世を風靡していた日本の総合電機メーカーは、リーマンショック時に全社が沈没した。それから13年。最近では、電機6社(日立製作所、パナソニック、ソニーグループ、東芝、三菱電機、シャープ)の二極化が鮮明になっている。独自指標の「設備年齢」を用いて電機6社の明暗を分けた理由を解説するとともに、歴代経営者の通信簿も大公開する。

#7
コーポレートガバナンスの強化を背景に、経営者が受け取る報酬の“妥当性”が問われる傾向が強まっている。かつて日本の産業界を席巻した「総合電機メーカー」の役員はどの程度の報酬を得ているのか。電機6社(日立製作所、東芝、ソニーグループ、パナソニック、三菱電機、シャープ)の役員報酬を徹底検証したところ、意外な「企業間格差」が浮き彫りになった。

#4
日本の産業界では、7大企業グループ(三菱、三井、住友、トヨタ自動車、NTT、ソフトバンク、日立製作所)などが、主要業種に中核企業を持つことで大きな経済圏を築いている。近年、トヨタとNTT、三菱商事とNTTがデジタル分野で提携するなど大企業同士でのタッグが相次いでおり、経済圏がさらに広がる動きが目立つ。約220兆円の経済圏を持つ日立グループはどう出るのか。連結子会社865社を有する「日立財閥」の反撃が始まった。

“旧中間階級”は年収127万円減、貧困大国ニッポンの全「階級格差」データを初公開!
『週刊ダイヤモンド編集部』9月11日号の第1特集は「新・階級社会 上級国民と中流貧民」です。日本社会は、格差社会よりもシビアな「階級社会」へと変貌を遂げていた。一握りの上級国民を除き、誰も上昇することができない理不尽な世界だ。その残酷な実態を明らかにする。
