猪熊建夫
第51回
織田信長の城下町として栄えた岐阜。街の真ん中には、全国指折りの清流である長良川が流れている。長良川の東側にある県立岐阜高校は、2023年に創立150周年を迎える。飛び抜けた伝統と進学実績を誇っている。

第50回
佐賀県の北西に位置し、玄界灘に面する唐津市。幕末には小笠原家唐津藩6万石が領する城下町だった。佐賀県立唐津東高校のルーツは、唐津藩が1871年に設立した英学校「耐恒寮(たいこうりょう)」という藩校までさかのぼることができる。わずか1年3カ月の短い間にすぎなかったが、この藩校で学んだ者の中から、後に建築界などで活躍する多くの俊英が輩出した。

第49回
東京タワーのすぐ近く、東京・港区にある私立の男子校で、高校からの募集は行わない完全中高一貫校だ。浄土宗をバックに明治時代に設立され、名門の進学校として各界で活躍する多くの人材を、送り出してきた。

第48回
西京高校は、その名のごとく京都市の西郊・中京区にある。ルーツは1886年に創立された京都府商業学校だ。だが現在、「商業」の面影はない。未来社会創造学科エンタープライジング科というユニークな名称の学科だけがある。
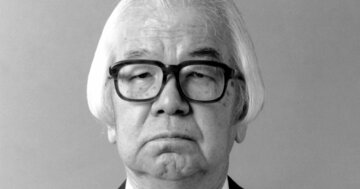
第47回
東筑高校は福岡県北九州市の八幡西区にある。前身の福岡県東筑尋常中学校は、1898年に開校した。校是は文武両道、質実剛健だ。それを体現した卒業生を出している。

第46回
JR小田原駅の南西・相模湾側には小田原城址がある。線路を挟んだ山側の八幡山の、中世に存在した小田原城西曲輪跡に、神奈川県立小田原高校がある。自由でのびのびとして、活力にあふれた校風だ。そんな同校では個性豊かな人物が数多く育っている。

第45回
東京の西郊にある国立(くにたち)市。桐朋高校はその文教地帯にある。武蔵野の面影をとどめる緑と調和したキャンパスだ。私立で、男子のみの6年制中高一貫教育だ。個性が突出した卒業生がいる。弁護士の河合弘之だ。

第44回
細川家54万石の城下町として栄えた熊本。その熊本市に県で2番目の旧制県立中学として設立されたのが、熊本高校の前身だ。国公立大医学部に進学する生徒が多い。

第43回
東京東部の墨田区は明治時代初めから人口が急増し、繁華街もできた。そこに1901年に設立された東京府立第三中学校が、都立両国高校の前身だ。文化勲章の受章者を5人出すなど、多くの文化人を輩出してきた。
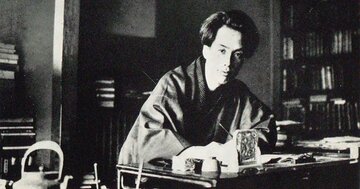
第42回
茨城県南西部の田園地帯にある人口4万2000人の下妻市。下妻第一高校は、県内2番目にできた旧制中学を前身とする伝統校だ。22年春には付属中学が開校、6年制一貫教育校になった。知名度が高い2人の大物経営者が、この学校を巣立っている。
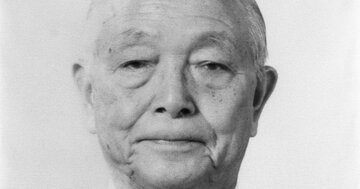
第41回
本州最北端にある青森県。県立青森高校は、八甲田連峰を背に陸奥湾に臨む青森市の東南に位置する。青森という独特の風土に育まれた、個性が際立った卒業生を多数、送り出している。
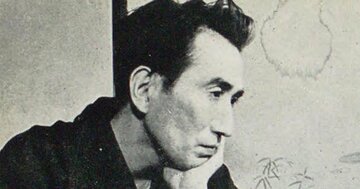
第40回
日本女子大学附属高校は、新宿から小田急線で30分という神奈川県川崎市多摩区にある。校舎もグラウンドも広い森に囲まれており、静かで落ち着いた環境だ。1901年以来、日本女子大の創立とともに歩んできた。6年制一貫教育の私立女子校だ。

第39回
生野高校は、かつては大阪市の一角・生野区にあったが、昭和時代に大阪府の中南部のベッドタウン・松原市に移った。比較的、裕福な家庭で育つ生徒が多く、文武で活躍する卒業生を多数輩出している府立高校だ。

第38回
東京学芸大学附属高校は、戦後に設立された国立高校だ。東京・世田谷区の住宅地にありながら、校地は広く緑豊かだ。「本物教育」を目指している。男女共学で、有数の進学校だ。とりわけ、女性の卒業生の活躍ぶりが光っている。

第37回
埼玉県南西部に位置する人口35万の川越市。江戸時代には、川越藩8万石が領する城下町だった。川越高校は、1899年に設立された県第三尋常中学を前身とする伝統校だ。男子のみを貫いている。

第36回
秋田高校は2023年に創立150周年を迎える全国屈指の県立伝統校だ。東北地方の雄であり、「自主自律」「文武両道」の校風を受け継いでいる。さまざまな分野で日本や秋田をけん引するリーダーを多数、輩出している。
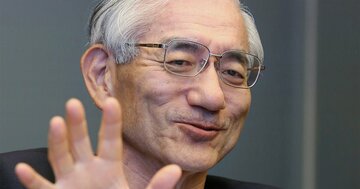
第35回
徳川御三家の一つ、紀州藩55万5000石の城下町だった和歌山市。和歌山城の南にある桐蔭高校は、中学校を持つ6年制の県立中高一貫校であり、「文」と「武」がうまく融合している伝統校だ。「旧制一中伝統校」というのが、すべての都道府県にある。そこで最初に設立された旧制中学のことだ。東京都の場合は東京府立一中=現都立日比谷高校、大阪府は大阪府立一中=現府立北野高校だ。

第34回
兵庫県立第三神戸中学校として1920年に開校した。神戸市の長田区北方の高台にある。公立高校では兵庫県内屈指の進学校になっている。体育の授業が厳しいことで知られている。ダイエーを創業し「流通革命の旗手」といわれた中内功が、神戸三中・長田高校を代表する卒業生だろう。
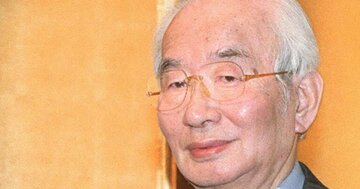
第33回
江戸時代には堀田家佐倉藩11万石の城下町で、「南関東の学都」といわれた千葉県佐倉市。その藩校をルーツとして230年の伝統を誇るのが、千葉県立佐倉高校だ。「ミスタープロ野球」と呼ばれる長嶋茂雄は、昭和時代が生んだ国民的スーパースターだ。その長嶋が学んだのが佐倉高校だ。

第32回
明治時代はまるで田舎で、立川村という田園地帯にすぎなかった。東京府はその立川村に1901年、府立第二中学を開校させた。これが、立川高校の前身だ。2022年4月からは、都立高校では唯一の創造理数科がスタートした。
