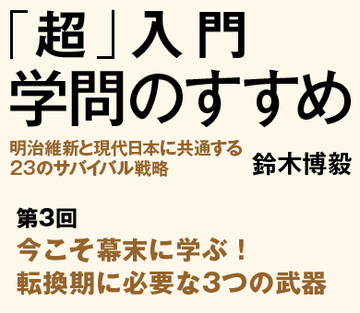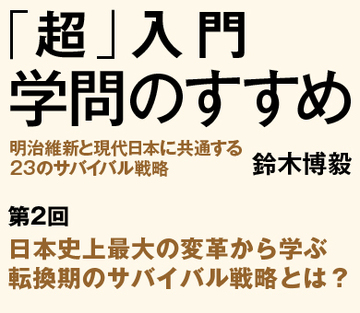明治維新とは
「民族としての過ち」ではなかったか
そういう江戸という時代は、明治近代政権によって全否定された。歴史から抹殺されたといっても過言ではない位置づけをされて、今日に至っているのである。
その存在力は、新政権の正統性を示すためだけに土深く埋められたといっていいだろう。
しかし、今、世界がこの「江戸」という時代とその様式、価値観に何かを求めて視線を当てている。
国内でも、リーマンショックで覚醒させられたかのように、無意識であろうが「江戸」へ回帰する「時代の気分」が、特に「江戸」が何たるかを全く知らないであろう若年層を中心に充満している。
私は、一連の著作に於(お)いて、史実に忠実に従えば、明治維新とは民族としての過ちではなかったかと問いかけてきた。
これは、一度国家を壊しながらも今もなお政権を維持している薩長政権に対する問いかけでもある。
もし、明治維新が過ちであったとすれば、その最大の過ちが直前の時代である江戸を全否定したことである。或いは、少なくとも江戸を全否定したことだけは、明白な過ちであったといえるのではないか。
「西南の役」直後の明治十二(1879)年に生を受け、昭和維新という「武の機運(きうん)」が沸騰していた昭和十年代を体験していた永井荷風(ながいかふう)は、江戸の残り香を求めて日夜東京をまさに徘徊した。彼に安息を与えたものが、江戸の忘れ物のような玉ノ井の私娼窟(ししょうくつ)であったことはよく知られている。
夏目漱石が、槌音(つちおと)高く近代都市へ変貌しようとする東京の“土建屋的喧噪(けんそう)”に神経を病むほどの嫌悪を抱いたこともまた、その作品を通してよく知られるところである。
彼らの心情を懐旧(かいきゅう)の情と受け留めるか、惜春(せきしゅん)の想いと理解するかは別にして、私にも同種の心情の軸ができ上がっている。
但し、私の場合は、「武」によって、いや、“究極の暴力”によって江戸を抹殺し、それを土深く埋めてしまって、あたかもそれが存在しなかったかのように振舞った明治近代政権に対する憤りである。
明治近代政権が何といおうと、脈々とその政権の意思を受け継ぐ者が何と教えようと、江戸は確かに存在したのである。
それも、政権がいうような姿ではなく、全く違った独自の姿かたちで存在したのだ。
文明開化の大合唱と共に彼らが尊崇した西欧システムが明らかに破綻しつつある今、土中から芽吹いてきたものがある。
そして、「近代」という価値を誇り、文明開化を売りつけた西欧社会そのものが、芽吹いてきたものに「近代」以上の価値を見出し、それを「よすが」としてこれから先を生きようとしているように見受けられるのだ。その芽の根が「江戸」という「近代」とは異質の価値であることは疑うべくもないのである。
是非はともかく、また目的は別にして、社会を変えようとする時、既成のもの=エスタブリッシュメントを倒すことは当然であり、必然であるといってもいい。
本書は、その是非を問うことをメインテーマとするものではなく、埋められたままの江戸を一度掘り返してみて引き継ぐべきDNAを解き明かしてみようと試みるものである。
しかし、江戸は多様であり、多彩である。この拙(つたな)い一篇の書き物で解き明かせるような貧弱な仕組みで成り立っていたものではない。
そのことを理解しながら、その一端でも掘り起こすことができれば、私たちが子どもたちの時代の「無事」のために何を為すべきかのヒントが得られるものと信じたい。
そして、世の諸賢が“寄ってたかって”全容を解明すれば、江戸は確かに未来構築の一つの指針になるであろうことを、私自身が固く信じたいのである。