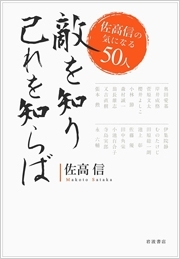まだ30代だった私は、電話に手をかけて大きく深呼吸した。これから、あの名匠、木下恵介にインタビューの申し込みをするのである。
『二十四の瞳』『野菊の如き君なりき』そして『喜びも悲しみも幾歳月』など、少年期の私に忘れがたい刻印を残した映画をつくった監督に電話をする。その緊張を解くために、深く吸い込んだ息を吐き出して、私はダイヤルをまわした。
「僕は先生なんかじゃないから」
1984年のことである。『夕刊フジ』で「ドキュメント 師弟」を連載することになり、木下と山田太一を取り上げようと思った。
企画の趣旨を話すと、木下は「僕は先生なんかじゃないから。山田君も先生なんて言ってないでしょう」と否定する。
「いえ、山田さんはいろいろなところで、木下さんを先生と書いていますが…」と食い下がると、「いや、友だちづきあいなんですよ。強いて言えば先輩で、師弟なんて言われると、テレちゃいますよ」
言葉はやわらかいが、断じて「師」であることを認めようとしない。
困った私は、そのままを山田に伝えた。
「まちがいなく、木下さんは私にとって先生ですからね。映画のことだけでなく、人とのつきあい方とか、実にたくさんのことを教えてもらいました」
こう語る山田の助けを得て、私は山田への取材だけで、この師弟を書いた。
その後しばらくして、山田が山本周五郎賞を受賞したパーティで木下と初めて会い、この記事の礼などを言われたが、目の前で山田と小説家の黒井千次が話しているのを見て、木下が私に、「太一はどこで黒井さんと知り合ったのかな」と尋ねるでもなく、聞いた。それは、まぎれもなく、愛弟子の成長に目を細める師の口調だった。
そのころ、木下はNHKテレビの『この人』に出演して、「(母がとにかく働く人で)だから私も、動くのが当たり前だと思ってまして、今でも監督をやってても腰かけてませんネ、動いてますヨ。ボクはバカとのろまが大嫌いで、ボクの助監督さんは走りまわってます」と話している。走りまわった助監督は小林正樹や吉田喜重だろう。ただし、山田は編集担当のスクリプターということで、あまり走りまわらずにすんだ。