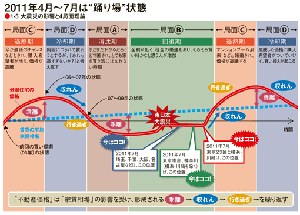「住まいを選ぶなら中古」という人が増えている。「古くて劣化した住宅」という負のイメージが薄れ、利便性や可変性を評価する声が高まってきているのだ。住宅市場を塗り替えつつある大きなトレンドに迫る。
少子高齢社会の
新たな「住宅の価値」
新築はどれも画一的、中古のほうがずっと個性的──
中古住宅にそんなプラスのイメージを抱く若い世代が増えている。近年、中古住宅の人気が高まってきた背景には、実際に買い求めやすい、質のいい中古住宅が増えてきたこともあるが、大前提として社会の変化があることにも注目したい。
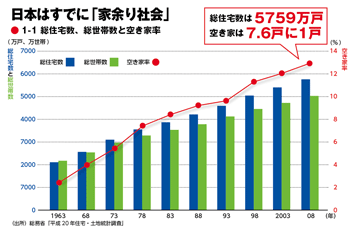 じつは、すでに日本は「家が余っている状態」に突入している。
じつは、すでに日本は「家が余っている状態」に突入している。
新築と中古を合わせた日本の住宅総数は、2008年時点で5769万戸。世帯数よりも762万戸も多い。日本はすでに「家余り社会」なのである。
さらに全体の13.1%が空き家だ。このままいけば、30年には空き家率が4割に達するという推計もある。
「なんと、もったいない」と、感じる人が多いのではないだろうか。少子高齢化により、すでに日本の総人口は減少に転じた。雇用情勢が悪化し所得環境が厳しさを増すなか、住宅取得により慎重な行動をとる人も増えてきている。
従来、新築一辺倒だった日本の住宅選びだが、新築の供給量は09年が78.8万戸、10年が81.3万戸と、100万戸を大きく下回る数で推移している。「希望するエリアに、条件を満たす新築が出ない」という声も多い。
そうした変化を背景に、トレンドを変えた分水嶺が、08年のリーマンショックだった。世界不況を受けて09年の新築の着工数が大幅に落ち込んだ結果、中古の流通量が初めて新築を上回ったのだ。