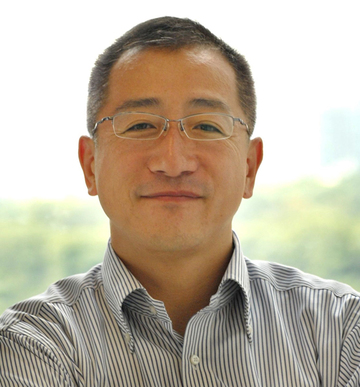トランプ政権発足後の新たなグローバル秩序の胎動の中、真に必要な組織モデル、人材像のあり方とは何か。大手日系IT、外資系ファームのマネジメントを経験し、現在も外資系IT企業の日本代表を務める筆者が論考する。
Brexitとトランプ政権誕生
 インフォシスリミテッド 日本代表
インフォシスリミテッド 日本代表大西 俊介
おおにし・しゅんすけ/1986年、一橋大学経済学部卒業後、同年日本電信電話株式会社に入社、株式会社NTTデータ、外資系コンサルティング会社等を経て、2013年6月より、株式会社NTTデータ グローバルソリューションズの代表取締役に就任。通信・ITサービス、製造業界を中心に、海外ビジネス再編、クロスボーダーな経営統合、経営レベルのグローバルプログラムの解決等、グローバル企業や日本企業の経営戦略や多文化・多言語の環境下での経営課題解決について、数多くのコンサルティング・プロジェクトを手掛ける。NTTデータグループの日本におけるSAP事業のコアカンパニーの代表として事業拡大に貢献した。2017年1月1日、インフォシスリミテッド日本代表に就任
2016年11月9日の朝、私は成田空港にいました。12月末で当時社長を務めていた会社を去ることになっていたので、引継ぎに向けてのいろいろな準備を始めていました。行先はアメリカ合衆国。ニューヨーク州の地方都市にある日系企業のお客様のプロジェクト拠点を訪れ、ともにプロジェクトを進めているグループ企業のマネジメントメンバー達と自分が去った後のことについて、いろいろと話しておくことが目的でした。
朝9時過ぎに、ラウンジでニュースをチェックしました。すでにアメリカ大統領選の開票が始まっていましたがトランプ氏がリード、おまけにカギとなる州の1つと言われたフロリダ州がトランプ氏勝利の可能性と報道されていました。なんとなく気になって、先に客先の拠点に入っている社員にメッセージをいれると「海岸部の出口調査ではヒラリー氏が圧倒的みたいですよ」というレスポンスがありました。
とはいうものの、何かが起きそうな予感がして、離陸した後も有料のWi-Fiのチケットを買って、チェックしていると、どんどん信じられないような結果が目の前で起きていきました。
機内で昼食を食べ終わるころには、ほぼ大勢も決まり、この後、起きるかもしれないことを考えると「失望」の一言しかなく、そのまま眠り込んでしまいました。JFK空港から国内線へのトランジットの合間の時間で朝食を食べていると、ヒラリー氏の敗戦スピーチがLIVE放送されていました。彼女の後に続く、若い女性たちへの勇気づけのメッセージで有名なスピーチでしたが、時差ボケ、眠気もあって、未だに目の前に起きていることが信じられず、まさに「茫然自失」という体だったと思います。
お客様の拠点訪問を終えた後、自社グループ会社の幹部とのミーティングのためにアトランタに向かいました。アトランタは南北戦争で南軍の拠点だった都市ですが、公民権運動の指導者として有名なキング牧師が生まれた場所でもありますね。移民受け入れを拒否し、マイノリティを否定する発言を繰り返すトランプ氏の勝利から2日後、200年の歴史をもって、キング牧師ら多くの先人達の苦闘の結果として、黒人大統領を選出するまでになったこの国の歴史が根本から変わるかもしれない、そんな歴史的な大きな転換点に自分がいるような気がしました。
最終日はニューヨークに戻りましたが、マンハッタンでは至る所でデモがくりひろげられていました。
また、これより前、2016年6月23日にはイギリスの欧州離脱是非を問う国民投票(United Kingdom European Union membership referendum)が実施されました。開票の結果、残留支持が1614万1241票(約48%)、離脱支持が1741万742票(約52%)であり、離脱支持側の僅差での勝利でした。Brexit(英国のEU離脱)が方向づけられた日でした。
2016年という年は、後年、歴史の教科書において転換点として記載される可能性をもった1年だったのかもしれません。