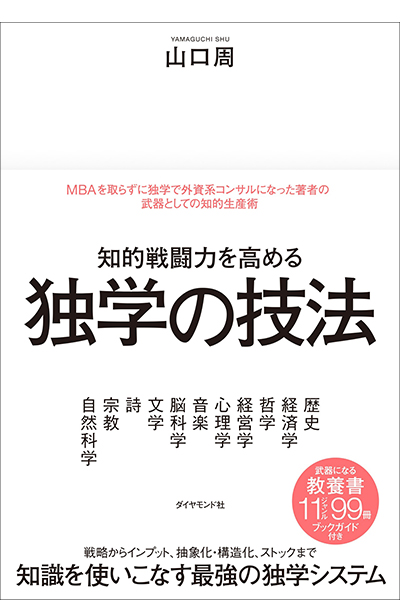さて、歴史がケーススタディの宝庫だとすれば、重要なのは、そのケースの当事者として自分を置いてみた場合、どのように振る舞っただろうかを考えてみることです。
経営学ではケーススタディが極めて重視されますが、ケーススタディを学ぶ際にもっとも重要な点は、自分自身を当事者、つまり経営のケーススタディであれば経営者ということですが、に当てはめて考えてみるということです。そうすることで、初めて人や組織の振る舞いに関する洞察を得ることができるわけです。
人の振る舞いを研究するといえば、一般にこれは行動心理学ということになり、組織の振る舞いを研究することになると、一般にこれは社会心理学ということになるわけですが、実は歴史を学ぶ意味も同じで、要するに歴史というのは「人や組織の振る舞い」について、過去の事例をもとにして考察するという学問なんですね。
ですから、このような「考察」を抜きにして、ただ単に雑学的に知識を仕入れても、人や組織の振る舞いに関する洞察は得られません。つまり、論語が指摘する「学んで思わざれば則ち罔し」というのは、ひたすらに年号や固有名詞などの歴史的知識を暗記するだけで、その背後にうごめいている「人間の性や業」について考察しない、ということを戒めているわけです。
論語が指摘する二つ目の過ちが、「考えるだけで学ばない」ということです。論語はこれを「危うい」と指摘している。つまり「独りよがりの考えに凝り固まって危なっかしい」と言っているわけです。
日本企業の中間管理職には、よく切れ味の悪い自己流の理論を薙刀のように振り回しては、周りも自分も傷つけている人が少なくありませんが、こういう人は論語のいうように、数少ない知識と狭い範囲の自分の経験だけに基づいた自己流の考えに凝り固まってしまっているわけです。
論語の指摘を、そのまま先述した「独学のメカニズム」の枠組みに当てはめて考えれば、インプットは「学び」に該当し、抽象化・構造化は「思う」に該当します。この両者がバランスよく機能することで、知的戦闘力の向上に直結する独学のシステムが完成するということです。