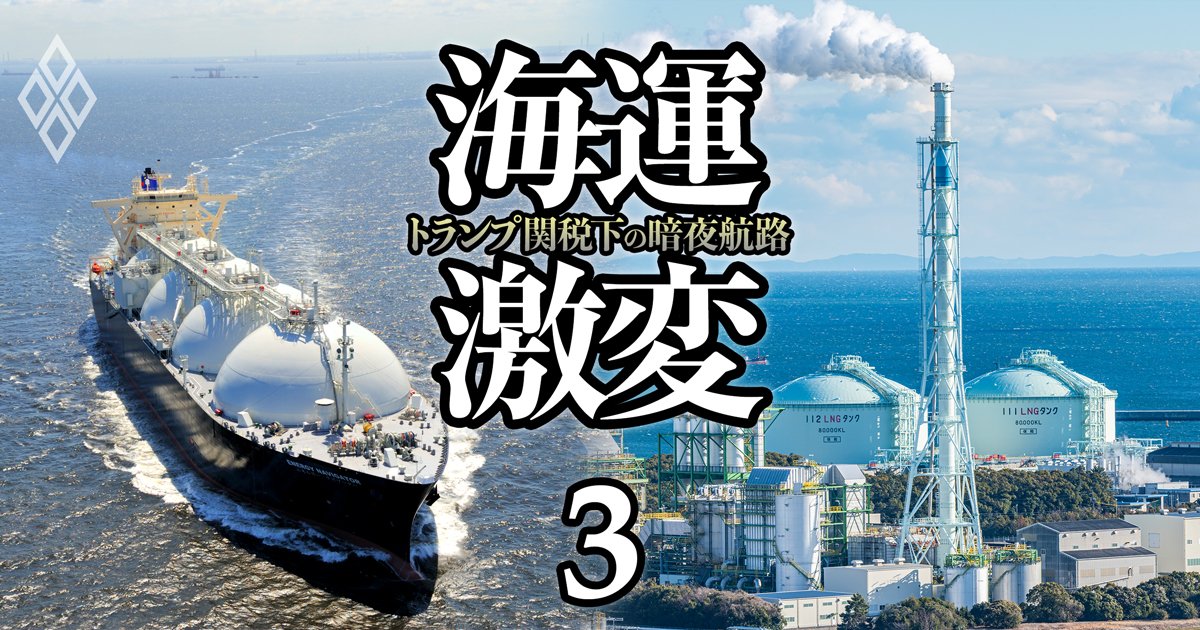ロボットに仕事を譲り渡すことになったからといって社員を首にすることなど、もとよりできない。いきなり「単純作業から高付加価値の作業にシフトを」とうたっても、無理難題というものだ。
テンポラリーワーカーの契約更改、社員の自然減などで対応していくしかなくなる。こうして次第に熱が冷めるのは、往々にしてあるパターンだ。
では、どうすべきか。これまでに60件を超える導入プロジェクトに携わった経験を持つ福島豊亮・KPMGコンサルティングディレクターは、ロボット導入後の業務をあらかじめイメージし、将来像を描き、人材の配置やスキルといった組織のありようを考えておくべしとアドバイスする。「RPA導入プロジェクトの最初に、ロボットが入った後の業務のあるべき姿を決め、やるべき仕事を定義するのが鉄則」なのである。
例えば、退職や入社関連の手続き、チェック作業に多くの時間を取られていた人事スタッフには、その代わりに、本来やるべきだがこれまで手が回っていなかった社員の健康状態の把握、過重労働の解消、健康増進といったミッションに時間を割くようにする、といった具合だ。
そもそも、ロボット導入で「確実に減るはずの残業代が、なぜか減らない」と担当者が首をひねるケースも珍しくない。
単純作業から解放され、楽になると人はどう出るか。「実は、浮いた時間を埋めにかかろうとする人が結構いる」(福島氏)というのである。8時間要していたものが2時間でできるようになると、その2時間の仕事を6時間かけてチェックする、といった信じられないことが現場では起こるという。
導入後のありようを考えておくことを怠ったために、頭を抱えている企業は思いの外ある。
「大企業ではロボットを着実に使いこなしているところもあるが、流れに乗って、大した準備もせずに導入したことで、幻滅期に入っている大企業も多い」(福原英晃・野村総合研究所コーポレートイノベーションコンサルティング部プリンシパル)。