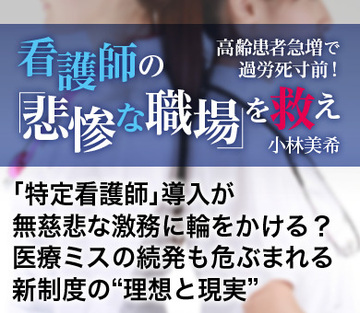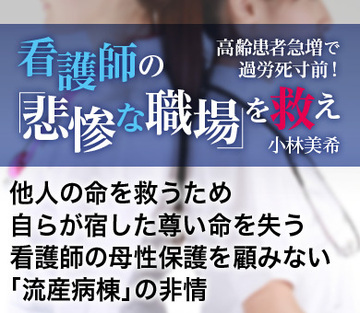夜勤が辛くて訪問看護に転身するも――。
看護師が直面した「さらに恐ろしい現場」
「夜勤のない訪問看護に転身したが、激務は変わらなかった」
都内の訪問看護ステーションで働く看護師の新田京子さん(仮名、40代)は、訪問看護に限界を感じている。
京子さんはもともと病院勤務の看護師だったが、あまりの夜勤の辛さに病院を辞めた。病院では、患者の在院日数が短くなっているため、めまぐるしく患者が入れ替わる。京子さんは、「患者さんが治っていく過程を見ないまま、重症患者ばかりを担当する。もっと、患者に寄り添った看護がしたい」と思うようになった。
一方で、訪問看護は基本的には日勤の仕事。かつ、経験豊富なナースでなければ務まらないこともあり、そこにやり甲斐を見い出せないかと、京子さんは3年前に訪問看護ステーションで働くようになったが、足を一歩踏み入れると理想と現実は違った。
訪問看護では、京子さんは1人当たり60分程度、1日6軒は患者の家を回る。移動時間を考えても、慌ただしいスケジュールだ。訪問先では、「今日はどうですか?」と体調を尋ねながら、検温や血圧などバイタルサインのチェック、点滴や薬の確認、お通じの悪い人には浣腸をするなど、全身の状態に変化がないかを見ていく。
だが、それだけでは終わらない。医療依存度の高い患者が増えてきたため、そのケアも含めると、いくら時間があっても足りない。
たとえば、あるがん患者はこうだ。呼吸困難に陥り人工呼吸器を使用するため、気管切開をしている。さらに、「ポート」という中心静脈栄養の管がつながれ、「胃ろう」もある。胃ろうとは、口から食事を摂れなくなった人の胃に穴を開け、チューブを通して経管栄養をとること。
さらに、「バルーン」という尿道カテーテルによる排尿もしている。がんの痛みをコントロールするため、モルヒネの代わりに皮膚に貼って麻薬成分を吸収させる「パッチ」(デュロテップパッチ)という痛み止めが適切に使われているかをチェックすることも、訪問看護師の大事な役割だ。