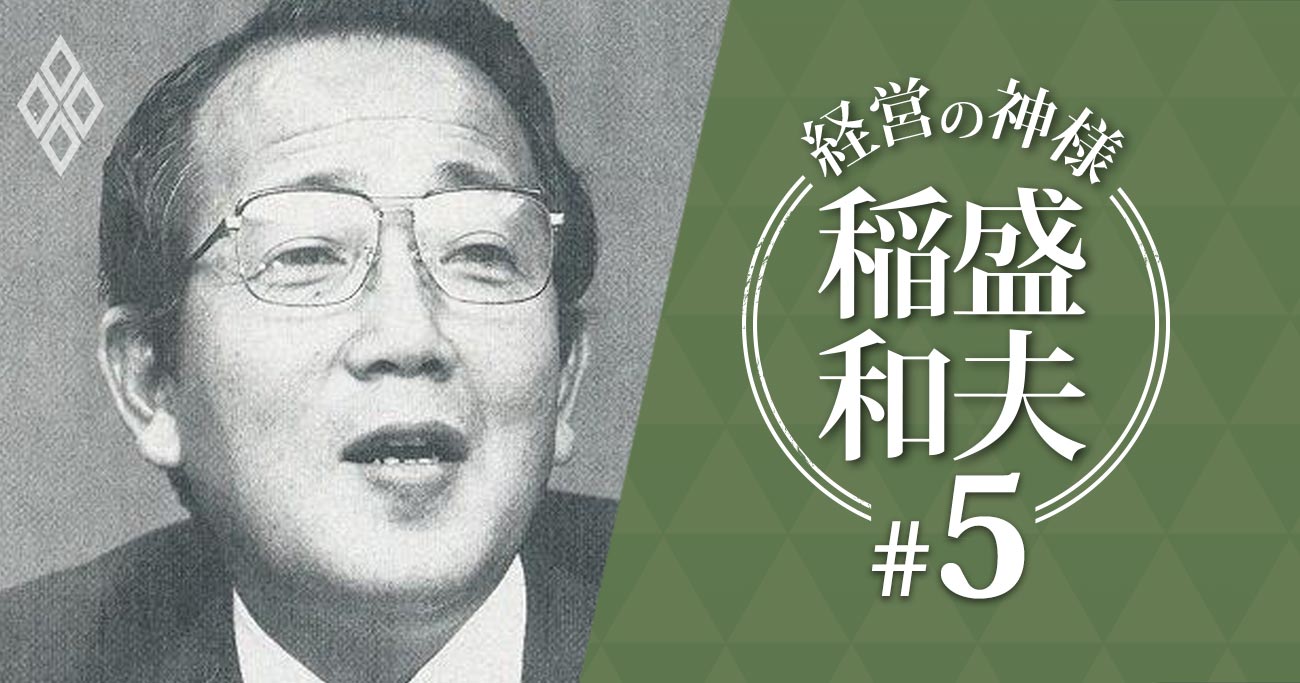
高品質なセラミックスの製造を実現するために、均質化の研究にいそしんだ稲盛氏だが、企業経営もまた“均質化”が一つのテーマだった。全社員が「情熱と思い」を一つにし、目標にまい進する。だから、「同質性を最優先し、批判勢力は排除する」と言い切っている。
組織の規模が大きくなればなるほど、多様な価値観が紛れ込み、いわゆる「大企業病」といわれるようにチャレンジする意識も薄れていくものだ。しかし稲盛氏は、企業の成熟とは平凡化であり、「安全だが成長性は落ちる」と断言するのである。
後段では、日本がサービス産業中心の社会に移行していく中で、ものづくり企業はどうあるべきかについて語っている。
インタビュー当時はバブル経済の真っただ中。多くの企業は手元資金を有価証券や不動産等の投資に回した。メーカーが本業で稼ぐ以上の利益が、財テクから得られた時代だった。忍耐と犠牲を強いられる地道なものづくりなどは新興国に任せ、繁栄した国だからこそ進める新しい道があるのではないか──。そんな浮かれた考え方も幅を利かせていた時代、稲盛氏は「それでいいのか。もう一度、ものづくりに目覚めよう」と問い掛けている。
(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)
正しいと思えば
誰とでも大げんかができる
稲盛 私は大の内弁慶だった。母親の姿が見えなくなると何時間でも泣いていた。兄が1人、妹が2人、弟が1人いて、家は印刷屋をやっていた。母親の着物の裾をつかんで離さないものだから、母親は仕事の手伝いもできない、生まれたばかりの兄弟の面倒も見られなかった。小学校に行くようになっても、母親に付いてきてもらった。
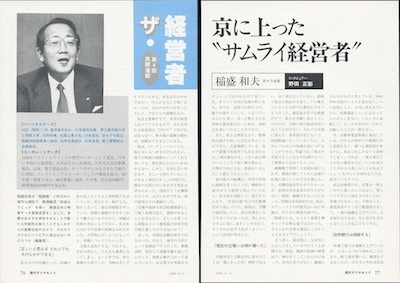 1989年11月4日号より 拡大画像表示
1989年11月4日号より 拡大画像表示
大変人見知りする。けれども、それが済むと、たちまち暴君になってしまう。4~5年では、中小派閥の大将だった。当時は少しどもりだったから、弁舌は爽やかではない。けんかも大して強くなかったが、自分のおやつをやったりして、子分どもの面倒を見た。
私は大変怖がりだ。本当の経営とはケアフルなもので、それをやれる経営者は“びびり”でなければならない。鉄火場の場数を踏めば、決断はできるようになる。
私は、パーティーへ行っても、知らない人へ声を掛けられない。部下が時候のあいさつに行ってくれと言っても、何を話したらいいか分からない。しかし、自分に言い分があり、正しいと信じていることがあると勇気が湧く。小学校でも、特定の生徒にひいきをする先生は許せなかった。役所だろうが警察だろうが、大げんかできる。私の経営はその連続だった。
──言葉やあいさつを社会的潤滑油として使う京都文化と、意味があることしか言わない、正しいと思ったら頑張るという鹿児島の田舎文化の壁を感じたのではないか?
稲盛 あった。当時は京都は好きではなかった。けれど、後半の人生にとって京都はプラスだった。創業当時、苦労して実験を繰り返していた頃、何度も跳び上がって喜んでいると、ある部下が単純な人だと言って冷ややかな目で見ている。そういう空気が京都の町にある。今でも、表面では持ち上げ、裏では偉そうにして、と言っている者も多い。ぱっと燃え上がる単純な鹿児島人だった私が、忍耐力を身に付けることができた。
また、私とは異質なもの、精神的な高さを持った文化を学ぶことができた。大変尊敬している、京セラ創業の出資者でもある方からは、「酒を飲むのも、つまらぬ人間のいる所で安い酒を飲むと、人間が駄目になる、作法が要るんだ」と教えてもらった。
私の最大の転機は、中学入学後に結核を患ったことだ。戦時中で叔父が2人結核で死んでいたから、私も死を覚悟した。寝たきりになり、“生長の家”などの宗教書ばかり読んでいた。結局は、空襲で逃げ回ったり、消火作業をしたりするうちに治ったが、美しきものを心に抱く、良きことを行う、そうすれば必ず人生はうまくいくという信仰が芽生えた。
現在の立場には
神が導いた
旧制中学と大阪大学に落ちたことは、悔しかったが、挫折ではない。全く尾を引いていない。結核で叔父が死ぬのを見て、いい薬をつくろうと大学では薬学をやるつもりだった。鹿児島大学では教養だけで、阪大を受験し直そうとしたのだが、当時の家の経済状況ではとても行けない。それで工学部に進んだ。参考書が買えないで、図書館通いをしているうちに、大学レベル以上の知識を身に付けることができた。卒論では、「東大の生徒でもこんなものは書けない」と教授から褒めてもらった。
就職難で希望した帝国石油に入れず、教授が探してくれた京都の松風工業という小さな企業に入った。有機合成化学をやりたかったが、応用化学出身者が行きたがらない、磁器、焼き物をやることになった。同期は全員辞めたが、私は、セラミックスの均質化はいかに可能か、ひたすら研究を続けた。







