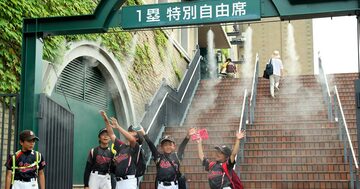甲子園で優勝し、胴上げされる履正社・岡田監督 Photo:JIJI
甲子園で優勝し、胴上げされる履正社・岡田監督 Photo:JIJI
101回目の「夏の甲子園」は、大阪代表・履正社の優勝で幕を閉じた。
開幕前から改革論議が活発に起こり、かつてないほど「高校野球のあり方」に関心が寄せられる中での大会となった。
投手の肩や肘をどうしたら守れるか? 暑さ対策は万全か? 大会日程は現状のままでよいのか? テレビをはじめ各メディアで大きく取り上げられ、さまざまな意見が交わされた。
「1人のエースが投げ抜く」時代から
投手陣の総合力で勝ち上がる時代に
試合の間隔が狭くなってくる準決勝に勝ち上がったのは、優勝した履正社、準優勝の星稜(石川)、そして明石商(兵庫)、中京学院大中京(岐阜)のだった。
明石商は準々決勝でエース中森を先発させなかった。
星稜も、絶対的なエース奥川を登板させず、他の2投手で強豪・仙台育英を退けた。
中京学院大中京は、2回戦は3人、3回戦は4人の継投で勝ちあがった。準々決勝ではエース不後を先発させたが、初回に3点を失ったこともあり、4回まででマウンドを降り、終盤逆転に成功する。
履正社は、エース清水を軸にしながら、2年生の岩崎が控え、準決勝は岩崎が完投して清水に休養を与えた。
いずれのチームも、「1人のエースが投げ抜く」のでなく、複数の投手がマウンドに上がり、投手陣の総合力で戦う姿勢を基本にしていた。連投や極端な投げすぎを避ける投手起用が当然のように展開されたのは、ここ数年の潮流でもあり、大会前からの議論の高まりの影響があったかもしれない。
こうした意識が高まれば、「球数制限」という強制的な制約がなくても、投手の安全や将来は保障されるのではないか。本来は、できるだけ選手やチームに選択の自由が与えられるべきだと思うから、野球の面白さや可能性を高め、確保する上で歓迎すべき傾向だと感じる。
履正社の優勝も、「高校野球の新しい潮流」を象徴する、1つの結果だったように感じられる。「球数制限」「勝利至上主義の是非」などの議論は、見方を変えて大きな視点に立てば、「やらされる高校野球」から「選手の主体性を大切にする高校野球」への転換、さらには「高校野球が頂点」ではなく「高校野球は成長の一過程」とするあり方への移行を前提にしている。この意識と新たな方向性を明確に認識する大会になったともいえるだろう。