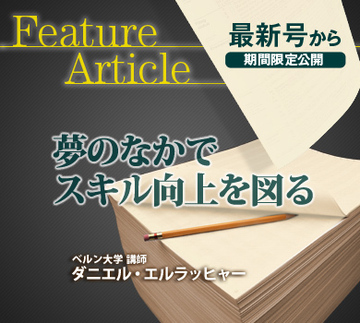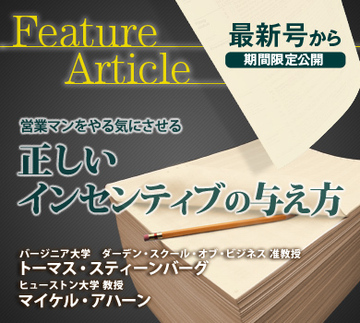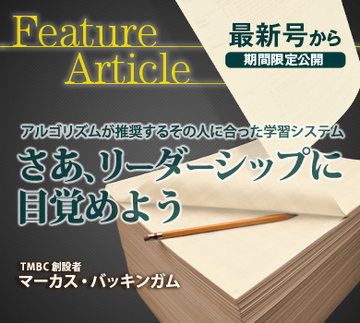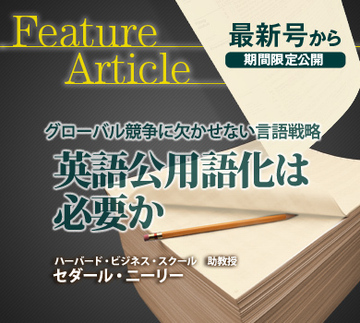タスクを分類する
個々の相互依存度に応じて、意識的にタスクに優先順位をつけるのが第3のステップである。
組織論の専門家ジェームズ・トンプソンが半世紀前に指摘したように、組織は人々の努力を結集するために存在する。結集とは相互依存ともいえ、「拠出型」「連続型」「互恵型」の3種類ある。
拠出型の相互依存は産業革命時代には欠かせないものだった。仕事は細かいタスクに分割され、他者からのインプットがなくても、個々に完結できるし、監視も可能である。現代のプロジェクトでこうした仕事が存在するのは、仕事の時期や場所に融通が利く場合だろう。しかし、現在のタスクの大半は、程度の差こそあれ、個人やチームが互いに影響を及ぼし合うことが求められている。
連続型の相互依存の特徴とは、タスクに第3者からのインプット(情報、あるいは形あるもの、もしくはその双方)が必要なことである。組立ラインはその古典的な例で、各作業員は、前工程の作業員がその仕事を終えて初めて自分の仕事に取りかかれる。
チーミングが求められる状況にはこの種のタスクが数多くあるため、注意深く計画を練らなければ作業に遅れが出るおそれがある。チーミングがうまくいくと、連続するタスク間の引き継ぎ効率がよくなるので、時間の無駄はなくなり、聞き違いなども起こらなくなる。ところが往々にして、人は自分の仕事だけに目を配り、「他の工程も自分と同じようにしている限り、業績には差し支えないだろう」と思い込んでしまう。
互恵型の相互依存とは、密接なコミュニケーションと綿密な擦り合わせが求められる仕事である。このマネジメントがチーミングの成否を最も大きく左右する。
多くの場合、部門横断型の流動的なチームで意見がまとまることは難しい。そのため、互恵型の相互依存関係にあるタスクはボトルネックとなりやすい。したがってこれらに優先順位をつけることが必要になる。
意思決定の前のアレンジや経営資源の調整、あるいは問題の分析と解決には、担当者同士やチーム内のグループが、集まらなければならない(オンラインでもかまわない)。リーダーがこのタイミングを決めることが非常に重要である。
大規模な建築プロジェクトでは、別々のタスクが別々の専門家によって連続的に進められていく。ウォーター・キューブの設計と建設はこれと大きく異なっているところがあった。専門家全員がそろった最初の段階で、ブレーンストーミングをして、さまざまな設計案の潜在的重要性について検討したのだ。わざわざこのプロセスを加える決断を下したことで、従来は連続型の仕事だったものが互恵型なものへと転化した。
その結果、複雑性は増し、調整がより必要になったが、設計の質は高まり、無駄は減った。工期は予定より短縮され、費用は抑えられた。ETFE(エチレン‐4フッ化エチレン共重合樹脂)の使用という英断が下せたのも、互恵型の相互依存のおかげである。ETFEは宇宙探査用に開発された素材だが、大型建造物に使用されたことはそれまで1度もなかった。
ETFEの持つ特性のおかげで、音響、構造、照明などの問題点が解決された。当初ETFEの使用はリスクが高いと思われていたが、アラップのエンジニアが最新のコンピュータ・モデリング・ソフトウエアを使って安全性を確認し、そのデータを使って中国政府当局に見解を説明した。
もちろん、ウォーター・キューブ・プロジェクトでのすべてのタスクが互恵型の相互依存関係にあったわけではない。サブグループでは、耐火性能の評価や図面作成など、個別型のタスクも多かった。
それでも相互依存型の仕事では、彼らの言う「インターフェース」を超えて調整の必要があった。カーフレイは同僚とともに、相互依存の度合いに応じてプロジェクト全体を「ボリューム」(分割可能な部分)に分け、各グループにボリュームを振り分けた。ボリューム間で調整が必要な項目があれば、関係者だけでインターフェース調整会議を持ち、構造上、組織上、手続き上の障害に対処した。
こうして、それぞれの境界線上で起きたであろうミスは事前に回避され、資材の節約、コストの削減、面倒な問題の解消へとつながった。