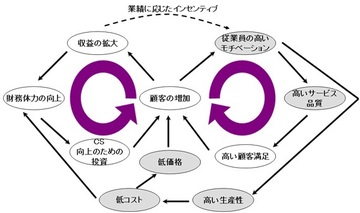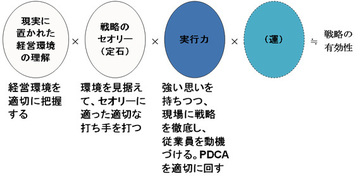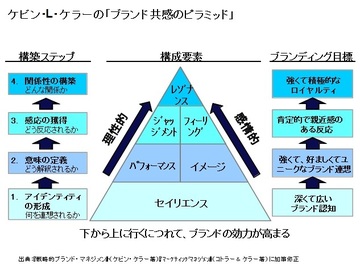スポーツ界をビジネスの視点から見る「スポーツと経営学」。第5回は、様々なスポーツを題材に、スター選手が監督やエグゼクティブとして相応しいかを考える。
スーパーマン、ラリー・バード
リーグきってのスーパースターである“キング”ことレブロン・ジェームズがマイアミ・ヒートで自身初のチャンピオンリングを獲得し幕を閉じたNBA(National Basketball Association)の今シーズン。最大のビッグニュースは間違いなくそのことと、シーズン当初のロックアウトということになるだろう。
しかし、それとは別に筆者の関心をひいたニュースがあった。それは、ラリー・バードがインディアナ・ペイサーズの球団社長(President of Basketball Operations)としてNBAのエグゼクティブ・オブ・ザ・イヤーを獲得したというものだ。球団社長はGMやヘッドコーチの採用も含め、球団のバスケットボールに関するすべての意思決定に責任を持つ仕事である。バードはこの賞の受賞により、最優秀選手(MVP)、最優秀ヘッドコーチ(コーチ・オブ・ザ・イヤー)、そしてエグゼクティブ・オブ・ザ・イヤーの3つをすべて受賞した初の人間となった。
ラリー・バードは、同じ1979年にNBA入りしたライバルのマジック・ジョンソン(ロサンゼルス・レイカーズ所属)とともに、80年代以降のNBAの人気拡大の立役者となったスーパースターである(その流れをさらに加速したのが84年にNBA入りしたマイケル・ジョーダンだ)。79年に当時低迷していた名門ボストン・セルティックスに入団するやいなや、チームを優勝候補へと押し上げ、80年代にセルティックスを3度NBAチャンピオンへと導いた。バード率いるセルティックスとマジック率いるレイカーズの対戦は80年代NBAの超黄金カードとして大きな関心を集める。バードはチームの精神的支柱、主将として存在感を示すだけではなく、記録面でも素晴らしい成績を残し、3年連続のMVPも獲得している。
バードを語るときに忘れてはならないのは、彼が白人選手であったということだ(本稿では、「アングロサクソン系」や「アフリカン・アメリカン」という用語ではなく、スポーツの世界では一般的に用いられている「白人」「黒人」という用語を用いる)。バスケットボールの世界、特にNBAは、伝統的に黒人選手が圧倒的な存在感を示す場であり、ヘッドコーチも黒人の登用が進んでいたことから、選手もファンも「バスケットボールは黒人のスポーツ」という印象を強く持っていた。そうしたところに白人選手のバードが颯爽と登場し大活躍をしたことで、白人のNBAファンの獲得につながったのは紛れもない事実である。
バードは現役引退後、数年してインディアナ・ペイサーズのヘッドコーチとなる。チャンピオンシップ獲得こそ逃したものの、ペイサーズを球団史上唯一のNBAファイナル出場へと導き、コーチ・オブ・ザ・イヤーを受賞する。白人選手として、「黒人のスポーツ」と思われていたバスケットボールに新風を巻き込み、さらにはヘッドコーチとして、そして球団社長として最高の栄誉を手にしたバードはまさにNBAのスーパーマンと言えるだろう。
名監督は名選手だったか?
バードのような例はやはりレアケースなのだろうか? 日本のスポーツ界では古くから「名選手、必ずしも名監督たりえず」という言いならわしがあった。主にプロ野球を意識した言葉だと思われるが、事実、古くは大下弘や別所毅彦などは名選手が監督として大成しなかった典型例とされている。その一方で、V9(読売ジャイアンツの9年連続での日本シリーズ制覇を率いた)監督の川上哲治や、主力選手としてだけではなく、監督や球団会長としてもそれぞれチームを日本一に導いた王貞治などは間違いなく名選手である。